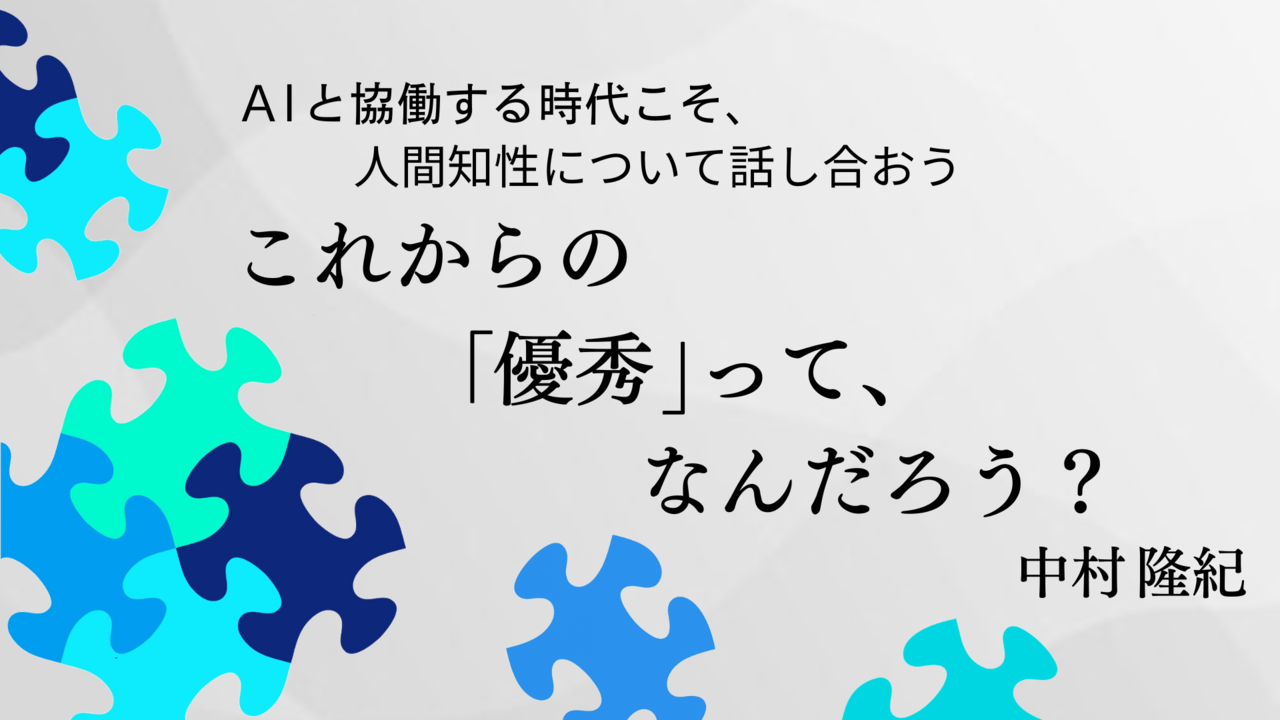【前回記事を読む】日本人独特の“経済的な営み”とは?被災地応援消費や、見返りを求めない献身的な推し活、近所へのおすそ分けなどは全て…
第四章 過去にひそむ未来
駅から〈Patina〉への道すがらでは、夕焼けの時間にツバメが何羽も飛び交うようになった。
このあたり、南東京では、巣立ちの準備がはじまっているのだろう。そんな日常に気づけるのも、毎日残業あたりまえの世界が、変わったからだ。
リョウコさんが店の扉を開けると、今夜は、常連たちの集まる場所が違っていた。大テーブルに、YOさんと連れの男性、シュウトくん、アッちゃん、ジョージとクマくん。
カウンターのほうでは、こわいオッチャンとネイビーが、静かに飲みはじめたところだ。オッチャンは、氷を入れたロックグラスに白ワイン、それをくーっと飲む。
「ぷは~、やはりワインの真髄は、のどごしやな。なっ?」……それほど静かでもなかった。
リョウコさんは、いつものようにタエさんと挨拶を交わし、好きなワインのあるほうへ。
「久しぶり、オッチャン」
「おお、あんたもこっちのオトナ組やな。今日も暑かってん、おばちゃん」
「おばちゃん余計やわ、オッチャン」
大テーブルでは、YOさんが隣りに座る男性を紹介していた。
「茂岡さんは、宮大工さん。全国の社寺建築を修復してまわる、渡り大工さんだ。いまは北陸の方で、後継者を育てる養成学校もやってらっしゃる。ウチはときどき、古い家の修繕を頼まれることがあって、レベルは違うけど、たまに工夫を教えてもらうんだ。この棟梁は、つまり、匠だ」
小柄で白髪混じりの短髪。YOさんと同じように、厚みのある身体つきをした初老の男性は、物静かな佇まいで、こんにちは、と小さくつぶやいた。みんなは少し緊張気味に、ひとりひとり挨拶する。
テーブルの上には、それぞれの飲み物と小皿、そして大きな平皿がふたつ。色とりどりの食材がサーベル型のピックに串刺しされて並んでいる。ピンチョスだ。タエさんが、急なテーブル使いに機転を利かせてくれた。
「棟梁とお会いして酒を飲むなんて、何年ぶりかな。シュウトはこの前、桂離宮の茶屋をつくりたいとか言ってただろ。おれには答えられないから、訊いてみれば?」
シュウトくんが顔を赤らめながら、改めて頭を下げる。
「あ、桂離宮をつくるなんて大それたことでもないんですけど。でもちょっとだけ興味があって……あ、どうしよう」
棟梁は、ベースボールキャップを被った異分野テクノロジストに、柔和な視線をおくる。
「若いひとが伝統建築に関心を持ってくれるのは、うれしいことです。書院や茶屋は、数寄屋職人という、また繊細な拵えの専門家がいるんですが。共通する思想は、ありますよ」
アッちゃんも興味津々、話に加わる。