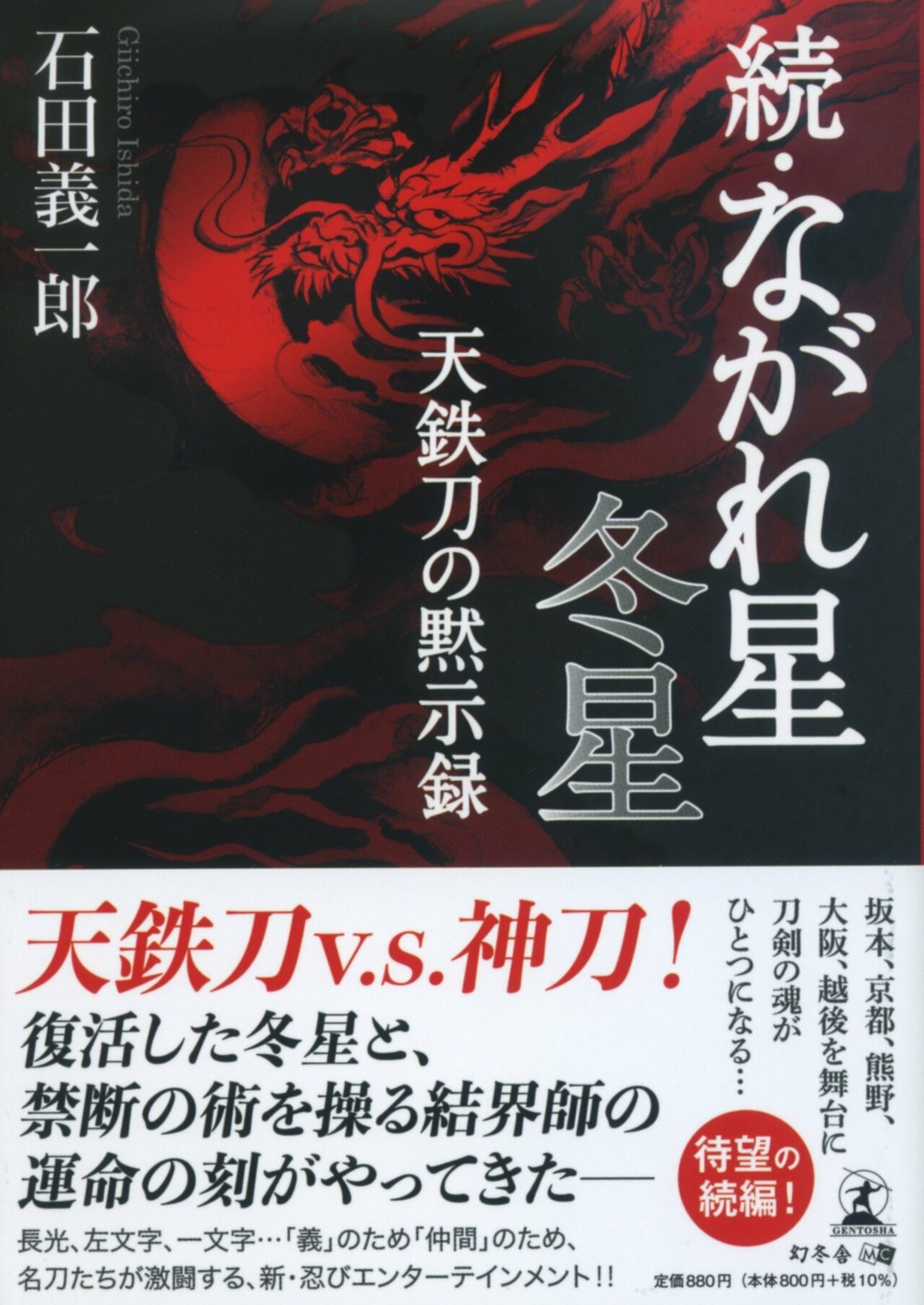第二章 北斗七星舎(ほくとしちせいしゃ)
どれくらいの時が経(た)ったであろうか。
ぐつぐつと鍋で煮物が煮える音と、炭火が爆(は)ぜる音で目を覚ました。
義近はぼんやりと目を開け、天井を見つめていた。煤(すす)けた天井は木の枝で編んだ粗末なもので、壁も戸板を無造作に貼り合わせてある。床には無数の薪や木材が積まれており、窓から入る朝陽に照らされ木の皮が白く映えている。まるで炭置き小屋のような佇(たたず)まいである。
台の上には木を切る大斧や小斧がずらりと並んでいた。
(ここは……、おいらの家か? いや違うな)
囲炉裏(いろり)の向こうに視線を移すと、一人の男が草鞋(わらじ)を編んでいた。
男は髭面(ひげづら)で、肩まである髪を後ろで束(たば)ねている。野良着のようなものを身につけてはいるが赤銅色(しゃくどういろ)の顔は端正な目鼻立ちをしており、一見無造作にみえるが精悍(せいかん)な風貌を醸し出していた。すると男が気づいたのか、義近に視線を向けた。
「よかった、やっと目が覚めたか。それにしてもひどい傷だったな。応急の手当はしてあるが、無理に動くと傷口が開くぞ」
義近は脇腹や肩に手を置き、身体中に白布が巻かれていることに気づいた。止血が施されてあり、幸い骨が折れている様子はなかった。しかしあちこちがじんじん痛む。治るとき傷口に熱を持つのだ。
脇腹の痛みとともに、忘れていた記憶がぐるぐると急回転で蘇ってきた。
(そうだった! おいら達は敵に襲われ、瀕死の瀬戸際で逃げてきたんだ! 源じいも死んじまった……。そんで、あの川底に落っこちてから記憶がねぇ。きっとこの人が助けてくれたのか)
【イチオシ記事】男たちの群れの中、無抵抗に、人形のように揺られる少女の脚を見ていた。あの日救えなかった彼女と妹を同一視するように…