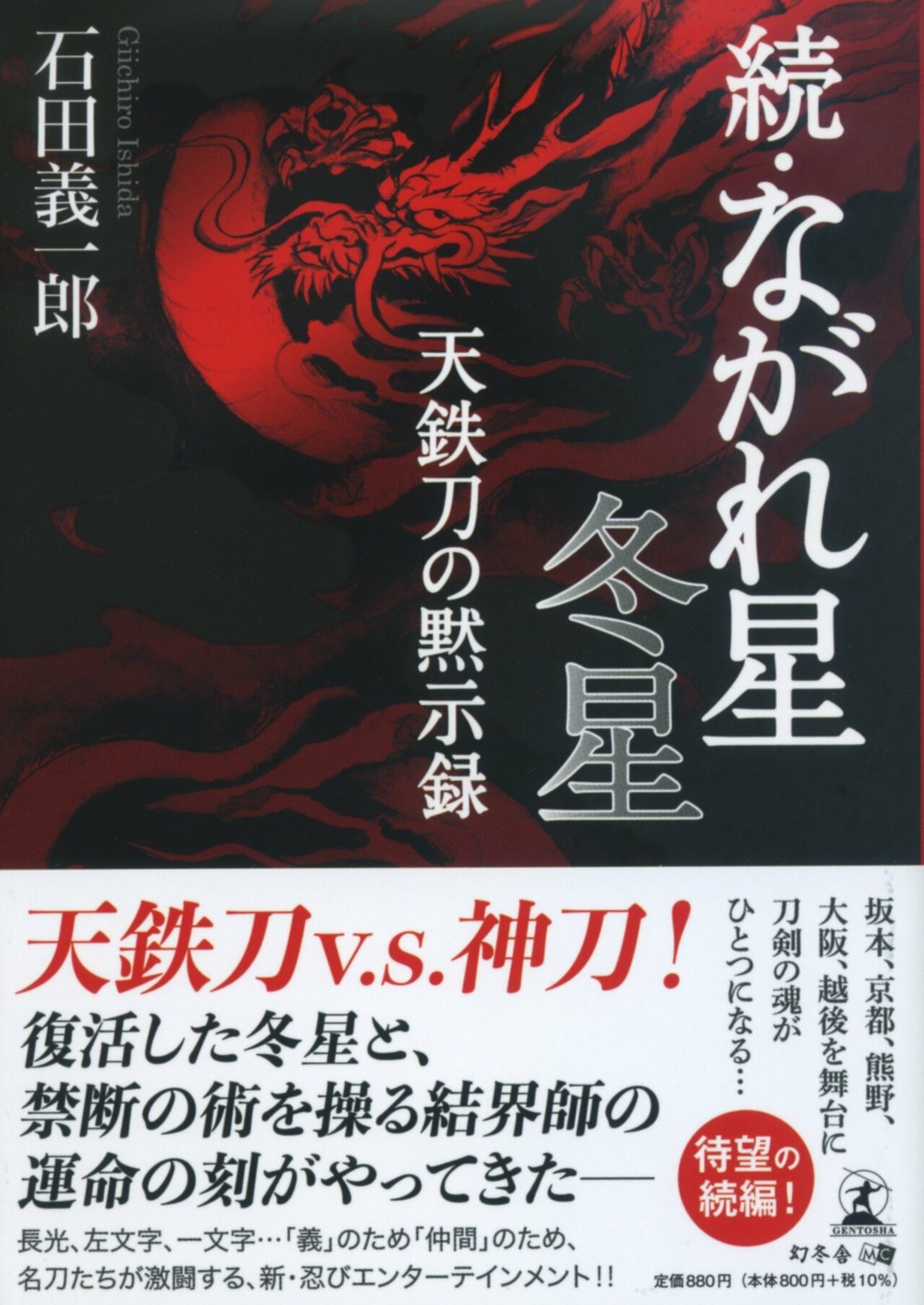「あああ、小僧! なんてことを!」
蘇摩利が崖の淵まで駆け寄り、川底を覗き込んだ。
「まさか飛び込むとは……。小僧にしてはいい度胸をしている。しかし、命はあるまいな。姉貴、あの箱も木端微塵(こっぱみじん)だな」
「この高さからでは助かるまい。箱の中身は何だったのかわからぬが、粉々になってしまってはもはや無(な)いも等しいだろう」
くノ一姉妹はあっさりと追跡を諦め踵(きびす)を返し、もと来た道に戻った。終わったことには振り返らず、無駄な仕事はしない錆鴉組らしい合理的な一面でもあった。
義近は真っ逆さまに落ちていくとき、意識が薄れていくのを感じた。頭の中が霞(かすみ)のようなもので覆われていくのがわかった。そのとき耳元で響く“言葉”を聞いた。
その言葉の主(ぬし)は平らかで穏(おだ)やかで、荘厳ですらあった。
〈おぬしの義、しかと見届けたぞ。われの魂に深く刻みつけようぞ〉心に染み入る深い言葉だった。
しかし義近はその言葉の内容をよく理解できなかった。まだ十一歳だからでもあるが、それでも波動のように伝わってきたのは、ただただ深く、ただただ温かい音色、とてつもなく大きなものにつつまれている感覚……。
そしてそのまま、意識が消えていった。