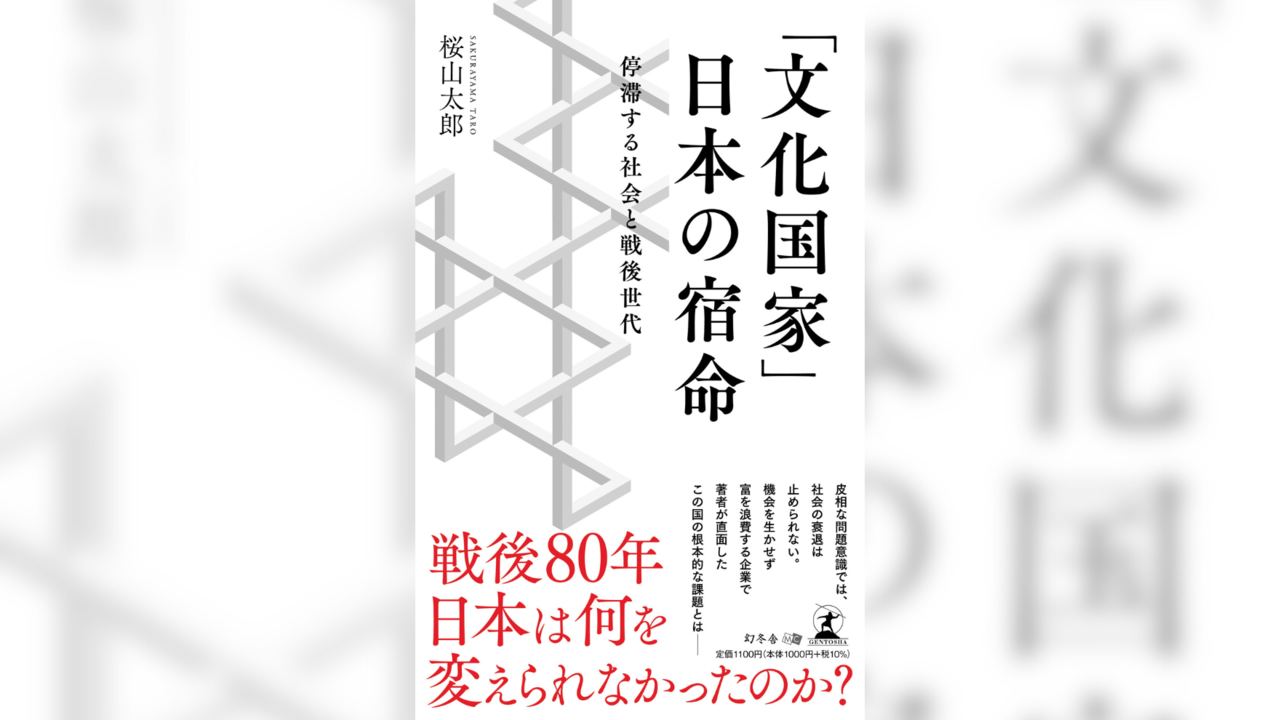【前回記事を読む】部下の女性たちが次々と上司から離れていった理由とは?——原因が分からない上司は部下に対する不満を陰で口にするようになり…
第一章 幸せなおじさんたちの罪
―崩壊する「科学技術立国」の現場
ベンチャー企業X社の事例
問題意識を武器にして他人と衝突を繰り返すP氏を眺めているうちに、問題について語るという営みは一般に似た傾向を伴うのではないかと私は考えるようになった。
事実と虚心で向き合えずに他人を私情や借り物の文脈で問題にする性質は多くの人にあるらしく、P氏のやや極端な言動は、複雑な現実を世間と同じ言い方で問題にする営みのいかがわしさを渾身(こんしん)で示していたかのようであった。
学生運動の世代とリストラ圧
X社はやや特殊な環境にあった。母体であるW社の建物を間借りしており、W社自体が民間企業の傘下にありながら営利を求めずに自由に研究ができるユニークな機関として内外から認められていた。
しかし設立から三十年ほど経ち、W社はその存在意義を問われるようになっていた。
大学でもできる研究に一企業が年間数十億の金を善意だけで出す必要があるのかと疑問を呈する人が上にいるらしく、変革を求める圧力が次第に強まりつつあった。
任期に上限のある契約社員としてW社に在籍していた私にとってその動きは本来他人ごとだったが、大学院時代に着想した計画とP氏やT氏たちが開発している技術を組み合わせれば、W社の存在意義を示すのは可能だとひそかに考えていた。
私がP氏の誘いに応じてすぐにX社に入ったのは、実現できれば不要論が出ているW社への援護にもなると思えるだけの大きな構想を個人的に抱いていたからだった。
一方で百数十人いるW社の社員は、専門が実学寄りの私と異なり発想がビジネスに向かない人がほとんどだった。W社を生き残らせるための策がないままリストラ圧にさらされた人たちは、個々の性格や考え方に基づいて行動した。
Q氏という人物の言動は、W社のユニークなあり方を最も端的に表していた。二〇〇〇年の夏にW社を訪れて将来の変革に触れた親会社の役員に対し、Q氏は立ち上がって我々はその方針に同意できないことを覚えておいてほしいと述べると、相手と話す気がまるでないかのようにすぐに着席した。
五十代だが気分的な若々しさを感じさせるQ氏は、普段は他人に対して友好的で、上下の関係に基づいて構えるところが少しもない人だった。