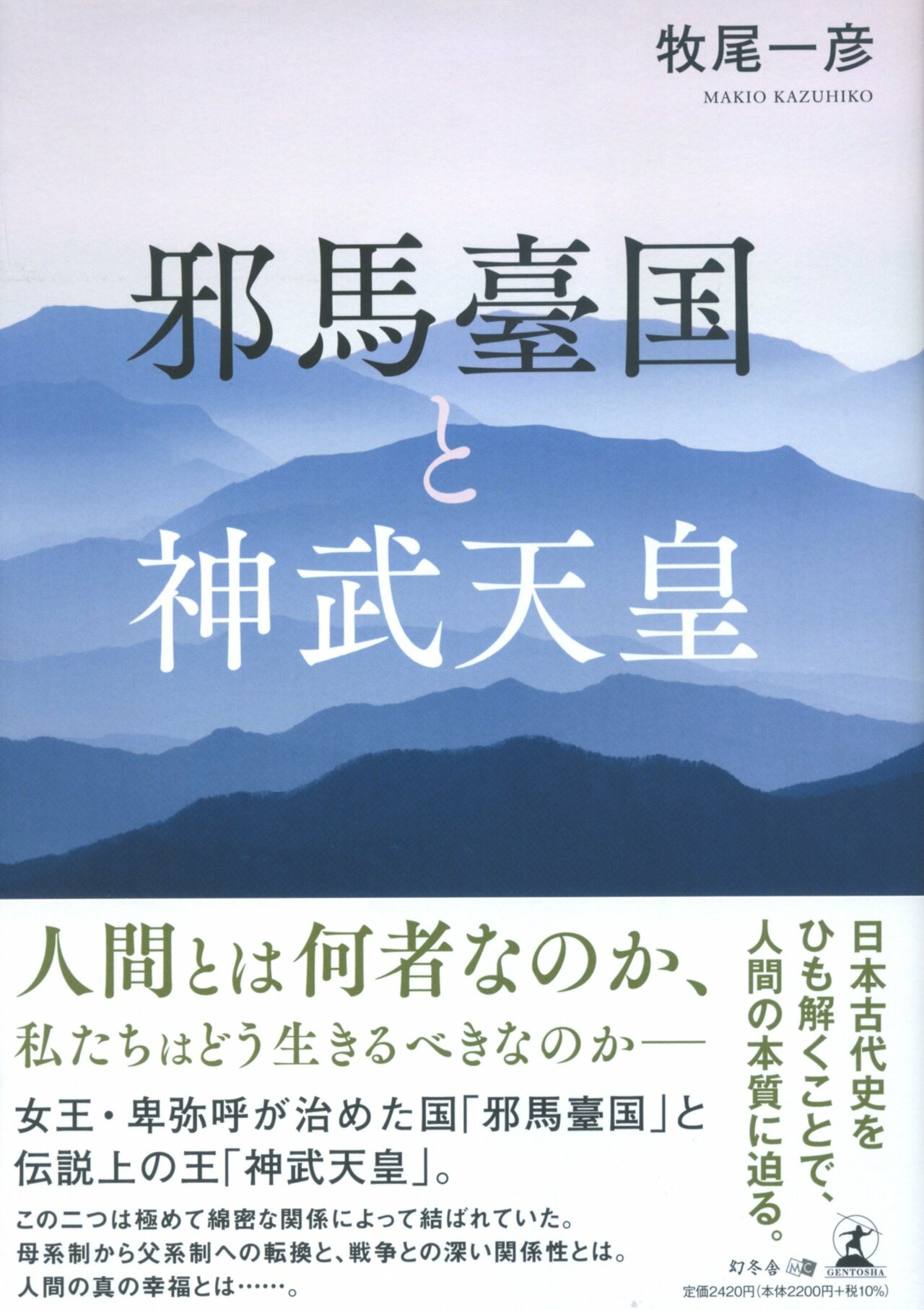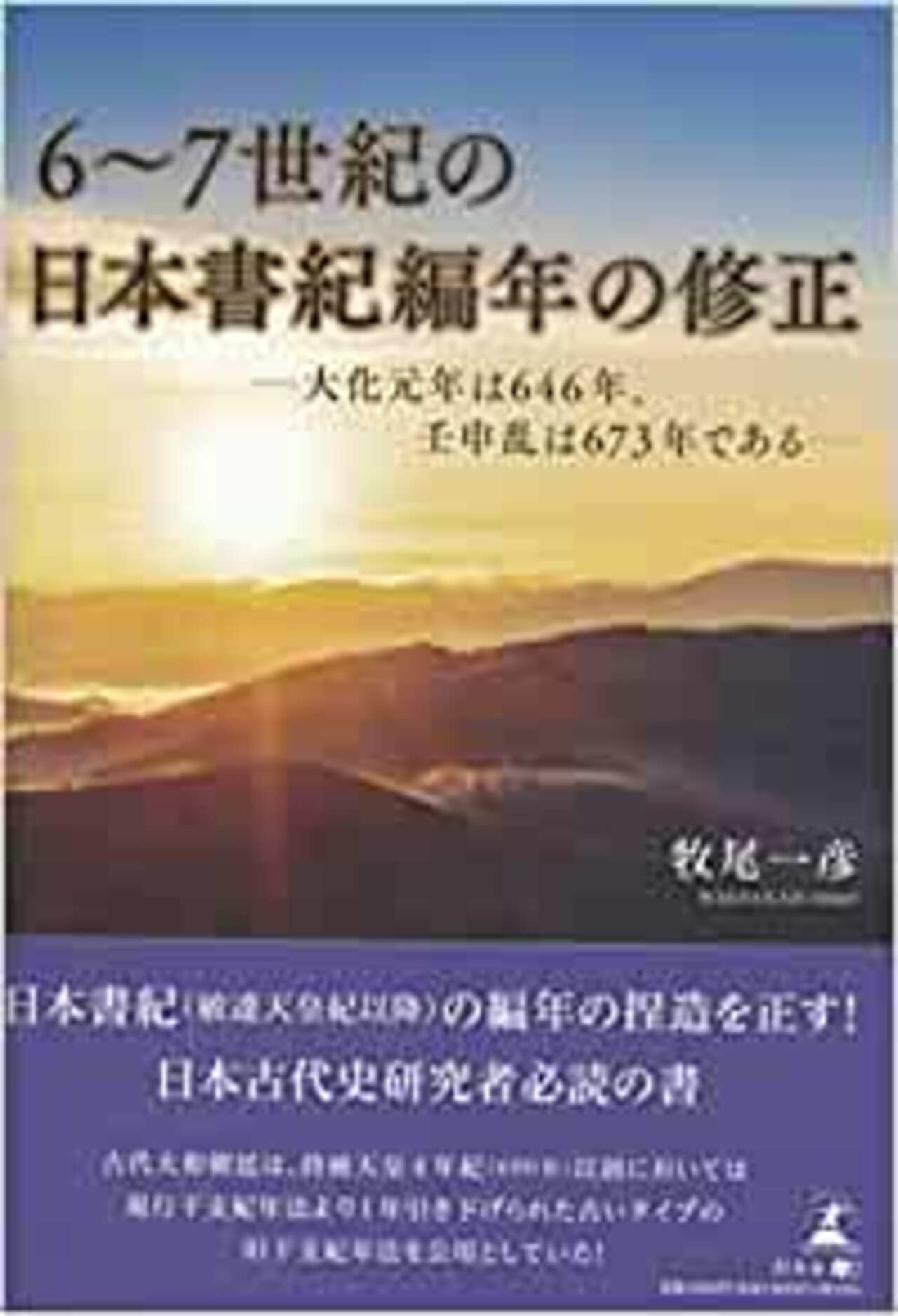原始時代の、なおサルに近かった頃にまで溯るであろう人類の祖先達の、感情・思考・判断の在りようにまで深い根をおろすところの、この人間の普遍的な思考形式のことを、古代ギリシャの哲学者、ソクラテスは、「イデア」、あるいはその根源としての「魂の想起」、というような言葉で説明しようとしたが(山本光雄編『プラトン全集』〔角川書店〕所収『パイドン』『プロタゴラス』『メノン』など)、弟子のプラトンはこの抽象的なイデア概念を、物象化して語ってしまっている。
プラトンの大いなる誤解によって、イデア論が曲げられ、壮大な変奏曲を奏でている様は、因縁律という、今となっては、合理的な、それ故にかえって分かりやすい抽象概念が、後の仏教徒たちによって、曖昧模糊たる空の理論に形を変え壮大な変奏曲を奏でているのと、類似する(蛇足であるが、ソクラテスが、よき友人を持つことを、よき生き方の最も重要な事項としたことも、シャカムニの生涯の実践に共通する)。
ソクラテスは、魂の想起こそ、徳をもたらす源であると見、従って徳は教えられない知識、学習されざる知識であると見る。この魂に内在する徳という知識の総体およびその根源のものを問われて、ソクラテスは結論を出さない。むしろ「知らず」と答える。「知らず、ということを知っている」と答えるのである。
ソクラテスの「無知の知」はこのようなところに淵源をおろすとみてよい。
「名声高き者たちは、却って最も多く思慮に欠け、身分低き者達のほうが、その点でむしろ立派に思われた」(前掲『プラトン全集』所収『ソクラテスの弁明』)とソクラテスの語った、その「思慮」もまた、学習されざる知識、知られざる根源より想起される徳にほかならない。ソクラテスの哲学は、カントの純粋理性批判にも比肩されるべき、深い思想であった。
徳をもたらす魂の想起の力は、ソクラテス自身の魂の想起の力が内省的に証明するものであり、説明は不要、教示も不要、ただただ、己に依拠して、悟るべきものであった。己に依拠し、自己を拠り所とすれば、人間の個性を超えて普遍的な、人間存在の本質に迫ることができる。
人間関係の在りよう、および、人と物との関係律の在りように関する研究、近代風に言い換えるならば、生産関係・消費関係を含むところの社会関係の構造に関する人間学的観点からする研究、この研究に、歴史学もまた、重要な責務を負っている。この責務の遂行に当たって、シャカムニの教え通り、常に、自己を洲として、ここに羅針盤を据えよう。
【イチオシ記事】「私を抱いて。貴方に抱かれたいの」自分でも予想していなかった事を口にした。彼は私の手を引っ張って、ベッドルームへ…