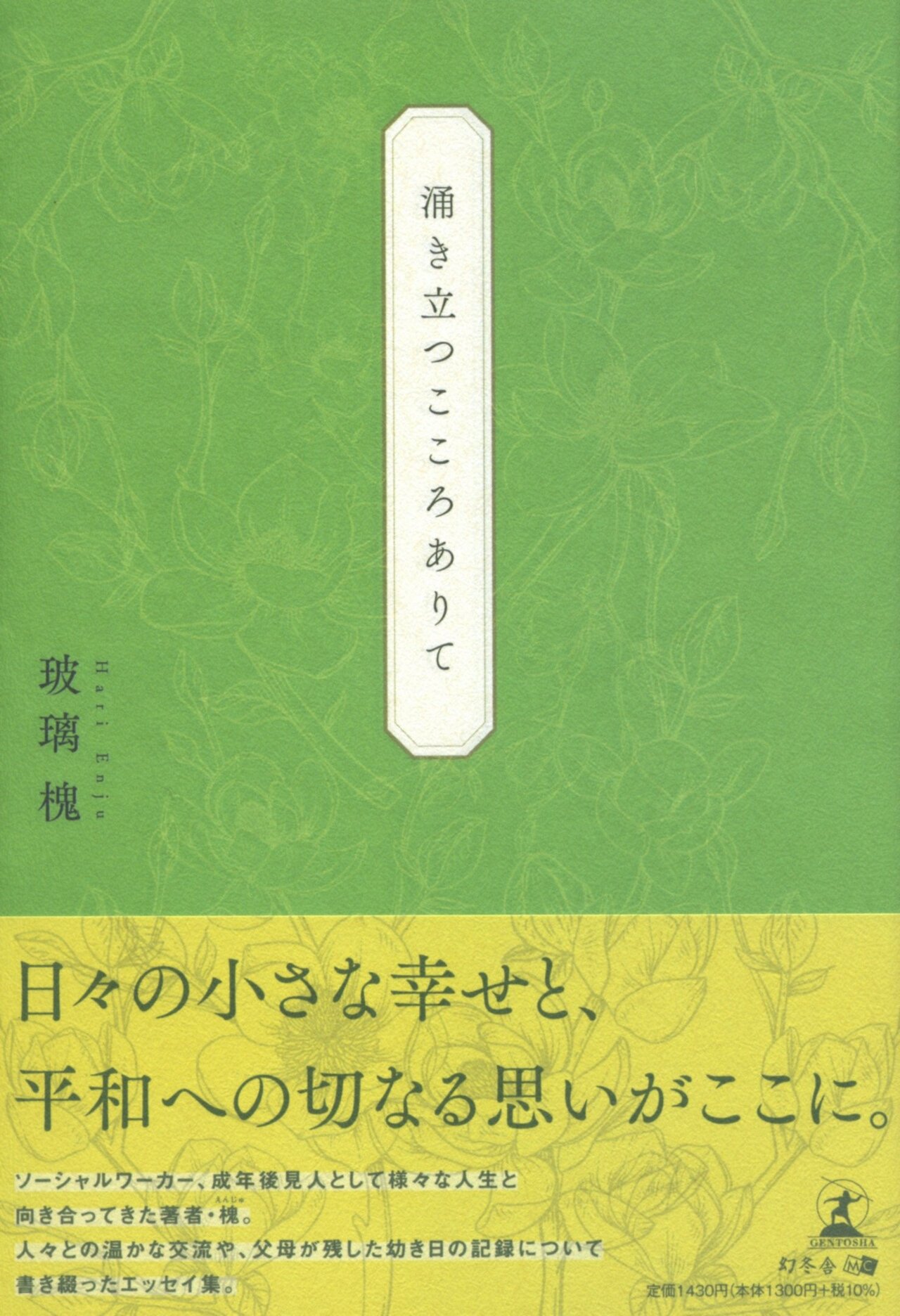【前回の記事を読む】初めてのデートで映画『007』を観る。彼女の青春のひとときには、憧れと別れ、人とのつながりの温もりが静かに流れていた。
第1章
長城詩
ソーシャルワーカーの先輩、シャガさんが患っていると知り、多摩動物公園駅近くの、ご自宅を訪ねたのは二〇〇〇年の秋だった。
福祉事務所のケースワーカー職の槐が、様々な困難にぶつかった時に、教えをいただいた先輩だった。
「やあ! 来たね、どうぞ、体を動かさないとね、芝の庭に雑草が生えて気になっていたところ」
シャガさんは芝生に足を投げ出し、雑草を抜いていた。
「久しぶりだね。皆さん元気かい、懐かしいな。倦怠感があってネ、病人の気持ちや苦労がよく分かる」
小柄のシャガさんは、体を持て余しているようであった。
画家である妻のリンドウさんを、一九八四年に癌で亡くされ、その悲しみと孤独は耐え難く、四年間一人ぽっちだったとおっしゃった。
シャガさんは木曽の景勝地「寝覚の床」の寺の出であった。佛像を慈しみ書画を趣味とし、書道に長け写経を続けてきた。一方、日本の精神医学ソーシャルワークをけん引してきた人でもあった。
訪ねた数日後に、一九七八年に中国を旅した時、万里の長城で詠んだ長城詩を、毛筆で書き送ってくれた。
長城詩
想長城隔海 四十有余年 萬機既整而
比到八達嶺 峰々高荒寥 城今聳眼前
雄姿似九龍 如這其大地 登城眺萬里
廣野浴陽光 群民来何處 旅影投城外
耐風雪幾何 崩朽刻歳跡 黄樹映落日
秋色更深幽 還我蝕城壁 冷気襲我掌
一陣風去空 不知果天涯
於北京 昭和五十三年十月 ○○詩
シャガさんは他界され、三回忌も過ぎた頃、半紙に書かれた長城詩は、皴も染みも色褪せることもなく、静かにシャガさんの言霊に触れることができたのだった。
それは、シャガさんの輝かしい業績を、象徴しているように思われた。器の大きい人でした。