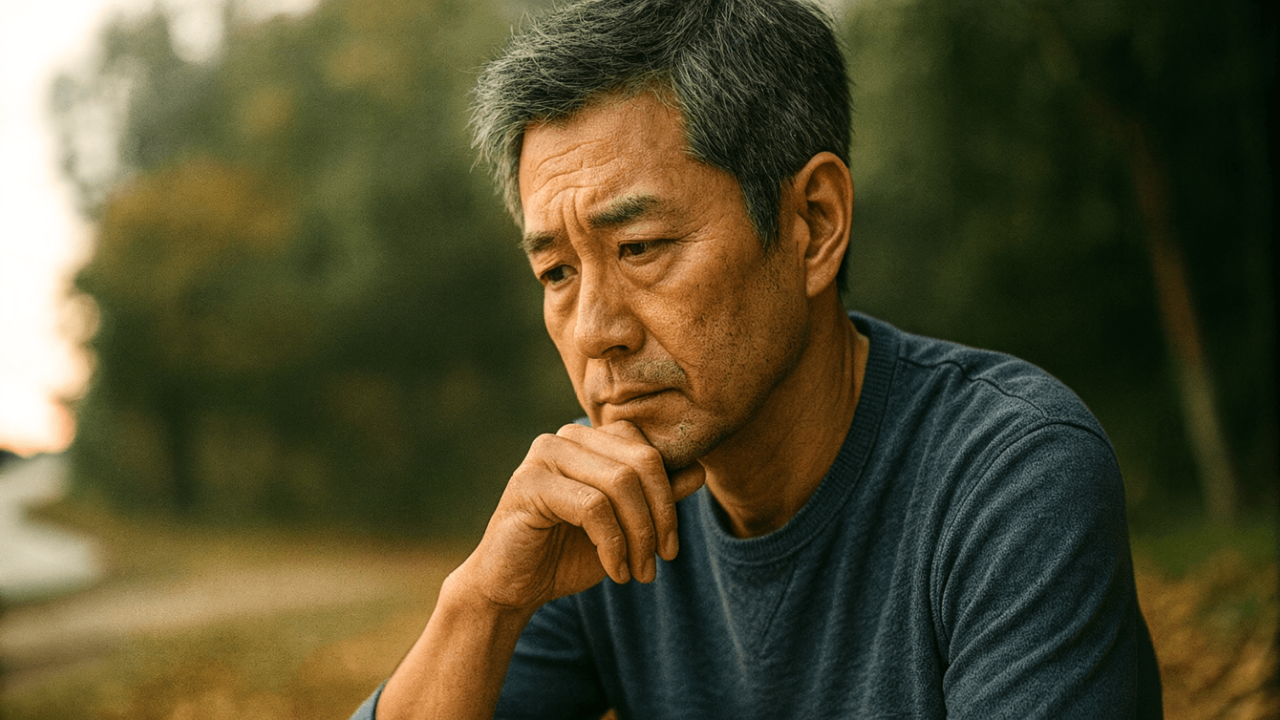いずれも自分の姿や自己のあり様から自己の真実性を見据えることの必要性を示唆している。
自己とは何か?
自己への問いは人間存在の真実性を問う根源的な要求であると言っても過言ではない。
自己とはからだではなく、脳が生み出すこころのはたらきによって賦与される。
幻のように不可得なもので、私、吾、我、自分、自我とあらわされる言葉でもあるが、実体はない。
したがって、自己は環境によって揺れ動く。
その本体は、理知的存在である反面、本能にも依存している。
大脳辺縁系や間脳から中脳にかけての本能的行動(種々の食欲・性欲・睡眠などの欲望、攻撃性、恐怖と憤怒と柔和、母性反応、動機づけなど)と情動(煩悩ともいわれる)は脳内制御回路によってコントロールされている。その脱抑制が起これば容易に解放されてしまうのだ。
脱抑制による解放現象が起きても、脳は可塑性(plasticity)に富んでいて、統制能力を再獲得できる可能性が秘められている。それは、脳内ニューラルネットワーク(神経回路網)に新たなシナプスを形成するはたらきがあるからだ。
したがって、脳はいいかげんで、まちがえることもあるが、それを省察する能力も持ち合わせているのであろう。
そのために、
脳内では常時五人の生きたい自己が巡りめぐっている。
ただ生きていたい、
たくましく生きたい、
うまく生きたい、
よく生きたい、
よりよく生きたい、
自己はいつ何時でもおろかなホモ・スツルツス(シャルル・リシェ『人間論』)(3)に変身する頼りないものなのだ。
親鸞聖人が教える「罪悪深重煩悩熾盛」なのである。