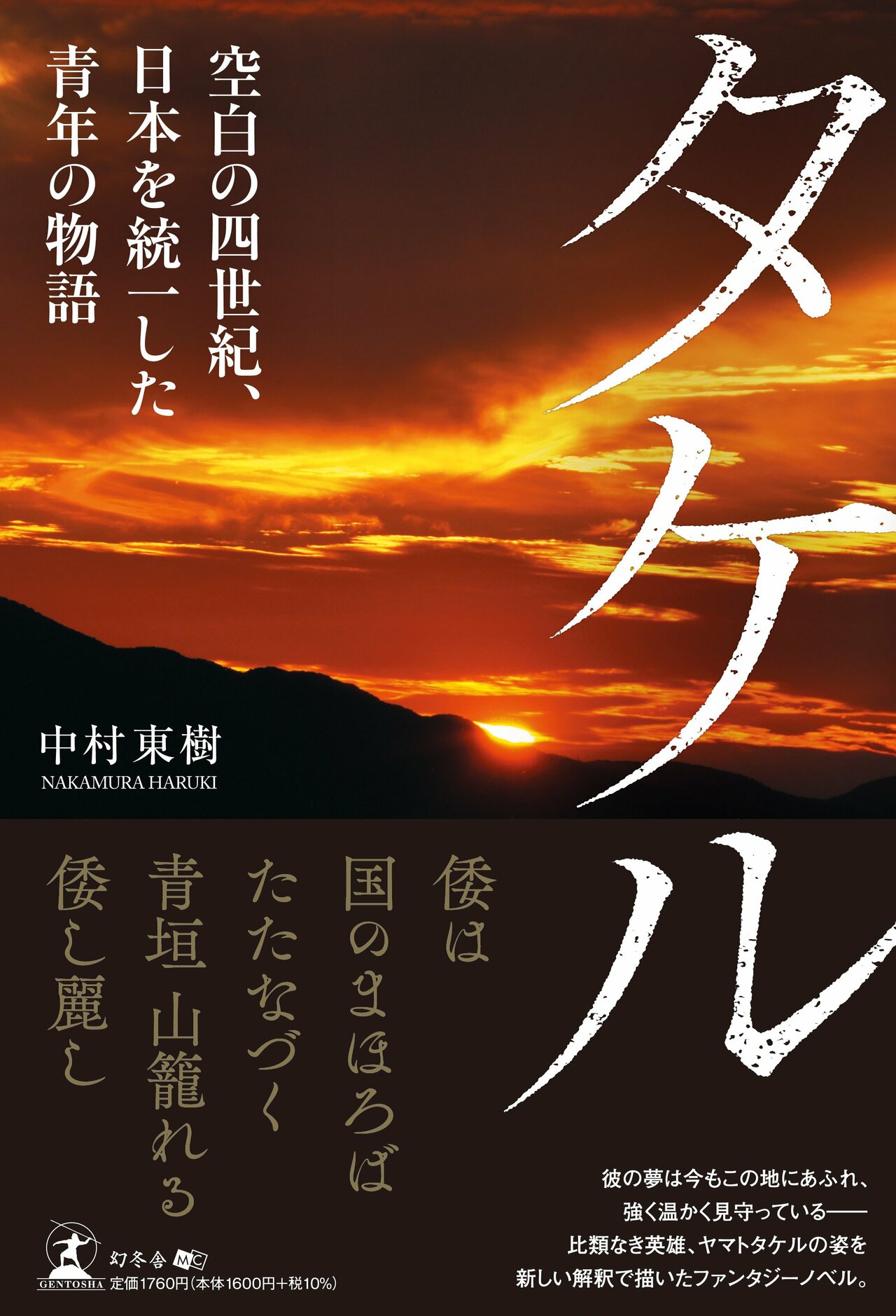フタジは心にもないことを話していた。丹精込めて作り上げた衣服だったのだ。フタジは黙って見つめている小碓にさらに続けた。
「私が二年間いなくて、寂しかったですか。きっと毎日子供たちと朝から晩まで真っ黒になるまで暴れまわっていたのでしょう。それとも可愛い娘たちと仲良くされて、遊び呆けていらしたのですか。私のことなど思い出す暇もなかったでしょうね。
あれから少しは政事(まつりごと)を勉強されましたか。あなたは、大王(おおきみ)になる資格を持っている方なのですから、しっかり政事を学ばなければいけませんよ」
小碓は久しぶりに聞く、フタジのお説教を笑いながら聞いていた。
「フタジ、私よりも一つ若いくせに、いつも母や姉のようなものの言い方をするんだね。もっと可愛らしくしたほうがいいとおもうよ。結構美しいのだから」
「結構とは失礼でしょう」と小碓の言葉に反発しながらも、顔を真赤にしてフタジは続けた。
「私は、あなたの叔母様になるのですよ。あなたの面倒をみるのは、私のお仕事なのです」
家系からいうと、フタジは、小碓の父親の大王の腹違いの妹なので、叔母に相当する。当時二人の結婚は許されるのだが、やはり近縁なのでフタジは小碓との結婚など考えたこともなかった。
小碓は急に真面目な顔になり、思いのたけをしゃべりだした。
「フタジ。私が小さいころから、あなたのことをずっと好きだったのを知らないはずはないでしょう。いつもあなたの笑顔が大好きで、遠くから見ていたのです。だからあなたに何かあった時は、すぐ助けに行ったのです。偶然ではないのですよ。
今度も私はあなたが伊勢の地から帰って来たのを本当は知っていました。機織り工房から出て、五人で山道を行くのを遠くから見ていたのです。だから大きな猪が出てきて、あなたたちを襲おうとした時もすぐ駆け付けることができたのです。
幼いころ崖から転げ落ちて、もう少しで川にはまりそうになった時も、遠くからあなたをずっとみていました。それで助けることができたのです。
子供のころから大好きなフタジに何かあった時には必ず助けようと思っていました。みんな偶然ではないのですよ。物心がついたころからフタジが大好きだったのですから。
あなたが作ってくれた薄い藍色のこの着物は本当に素晴らしいですね。私の寝所に置いてあったこの着物を見て、フタジが織ってくれたものだとすぐわかりました。柔らかくて、暖かく、ほんのりと優しい香りが漂ってくる。
この着物を手にしたとき、大好きなフタジを妻にしようと思ったのです。この服を着ているといつもフタジと一緒にいるような気がしてくる。だがもうこれ以上離れていることは我慢できない、フタジ結婚してください。いつものように私に笑顔で妻になるとおっしゃってください」