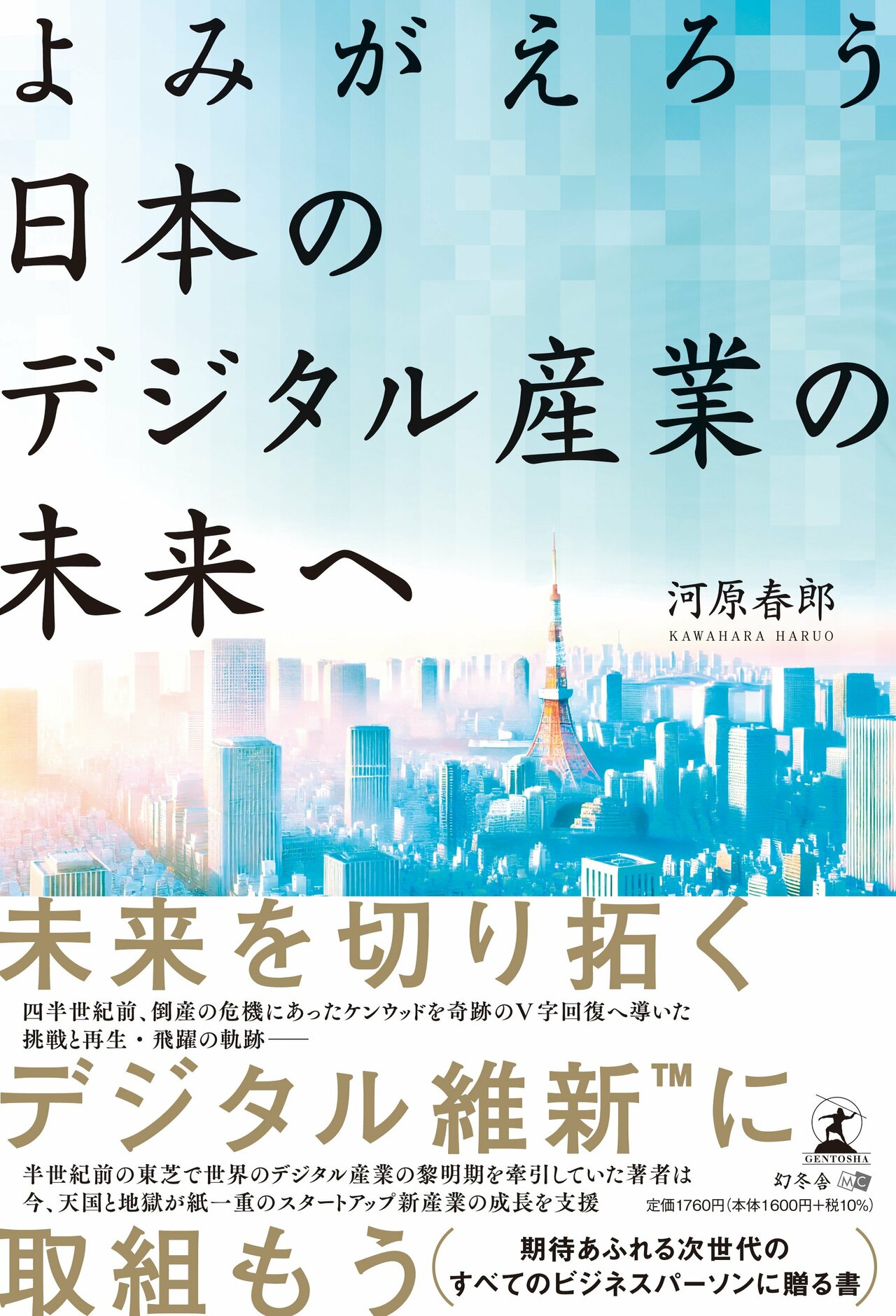集積回路(ICやLSI)が開発される前の個別半導体トランジスターのコンピューターは30分動くと止ってしまうというような時代だった1963年から19年間、黎明期のコンピューターを使って、工場や発電所の現地に寝袋を持ち込んで、昼夜を分かたず、ソフトウエアの開発・調整をした時代から、
データーとアルゴリズムを分離して、ソフトウエアの自動生産、CRTの画面上で、現地調整作業など、学校を出て間もない若いエンジニアのチームの活躍を得て、ソフトウエアの革命を成し遂げて、
1980年、60万KWの大火力発電所のデジタル全自動運転を世界で初めて商用化に成功して、人間の代わりに発電所をデジタルで全自動運転するソフトウェアの地位を確立した。
この実績は、その後、航空・宇宙、そのほかあらゆる産業に、人間に代わってコンピューターによるデジタル自動運転があたりまえになってきて、最近のAIによる新たな産業革命の原点になっていると思う。
後にアメリカの電気電子学会IEEEからフェローの称号注1)をいただき、その開発した発電所のデジタル全自動運転システムのソフトウェアは、2008年、東洋で初めて、米国のカーネギーメロン大学ソフトウエア工学研究所のソフトウエア・プロダクトラインの殿堂入りを果した。
その後、1980年代後半、45歳から7年間、脱炭素を先導して、燃料電池の開発・商用化に携わり、最初の2年間は東芝と米国Pratt & Whitneyとの合弁会社の初代CEOを米国人と共同で務めた。
そこには560人のアメリカ人と13人の日本人が働いていて、かつては米国の宇宙船アポロや当時もスペースシャトルの燃料電池電源をここでつくっていた。
私たちはここで、脱炭素エネルギーの水素によって発電する、陸の燃料電池プラントの開発、商用化を進めた。
宇宙開発では、当時すでにロケットの燃料の液体水素と液体酸素を使って燃料電池で電気を起こし、副産物の純水を宇宙船のパイロットが飲むという脱炭素のサイクルができていた。
注)IEEEフェローとは、当該の分野で、著名な業績を挙げ、比類のない経験と知見を獲得し、また、その業績が世の中の改革と進歩に役立ったという事実、他の誰もがなしえなかった、あるいは考えつかなかった、まったく新しい理論・システム・環境を考案し、その分野に革新的な変化をもたらした者に対して、毎年、全正会員の0・1%を上限で選ばれる最上級のグレードで、大学や研究機関、産業界で、その研鑽を極めた証しとして顕彰される称号となっている。
👉『よみがえろう 日本のデジタル産業の未来へ』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】電車でぐったりしていた私に声をかけてきたのは、不倫相手の妻だった
【注目記事】父は窒息死、母は凍死、長女は溺死── 家族は4人、しかし死体は三つ、靴も3足。静岡県藤市十燈荘で起きた異様すぎる一家殺害事件