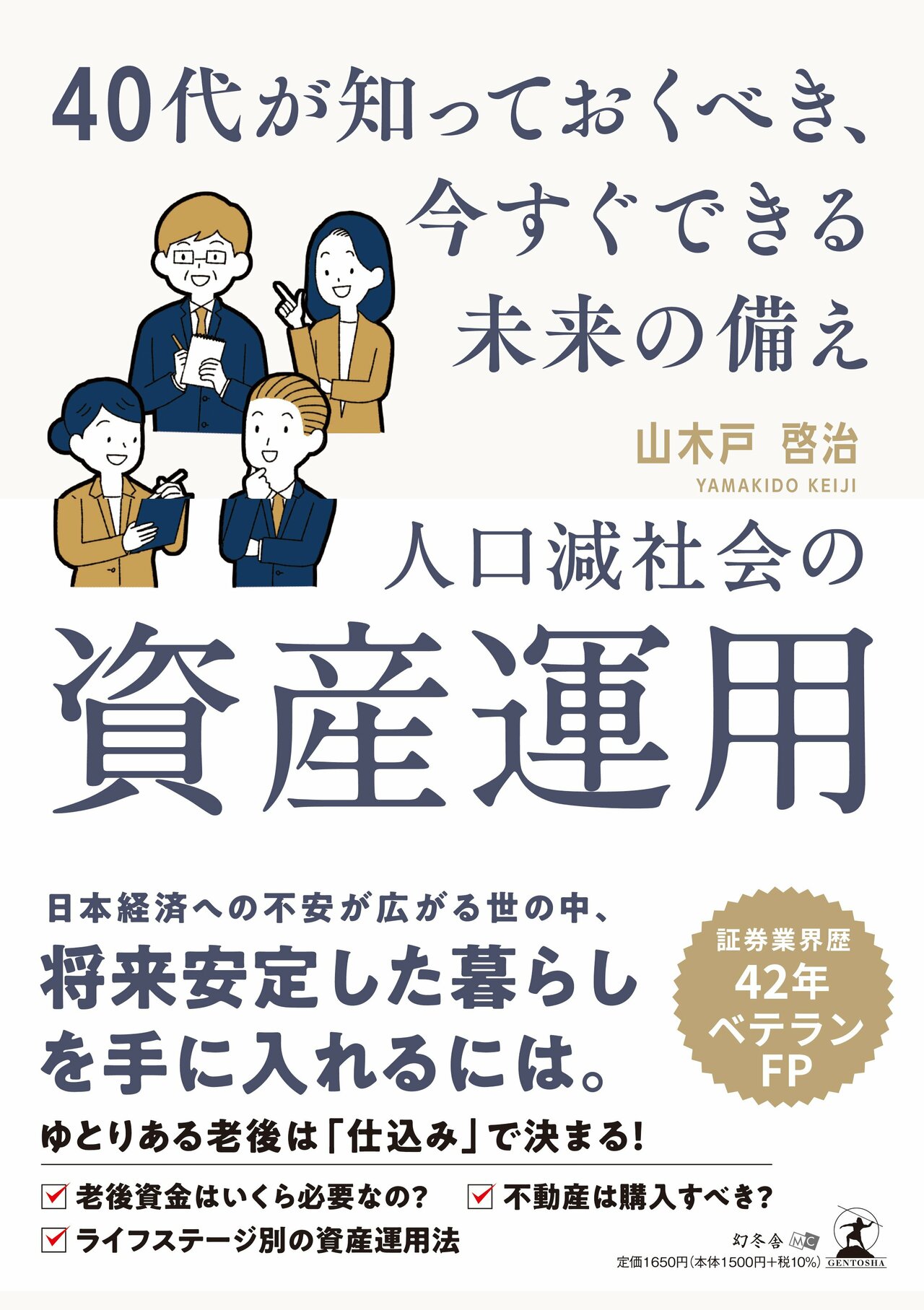高額マンションを購入、あるいは高額な家賃を負担して大都市中心部に住む人は、住むことでリターンが大きいと考える人です。
大都市には、技術・知識集約性の高い産業が集積していることで、個人的にも生産性を高める余地があると考えられるからです。
職場に近く、大都市中心部へのアクセスの良さを持つ駅近タワーマンションの利便性は、他の地域との格差を広げる要素です。
「2021年度首都圏(1都3県)新築マンションの1戸当たりの平均価格は、6,360万円とバブル期を超え、過去最高を更新した。地域別での平均価格は、東京23区が、8,449万円で過去最高になった」(不動産経済研究所 2022年4月18日)
注意しなければならないのは、生産性を高めるエンジンが失われて、コストに見合ったリターンが得られなくなれば、人は去ります。人・モノ・情報を、東京に集めることで、機能してきた、集積の経済という生産性向上策が、働かなくなったら曲がり角を迎えます。
「NTTは本社機能の一部を、東京都心から群馬県高崎市と京都市に移す。戦後長らく続いてきた一極集中。その潮目が変われば、働き手は人口集中による窮屈な暮らしから解放される」(『日経Views』先読み「一極集中、潮目変わるか」2022/10/02)
新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、本社や一部機能を東京圏から移す企業も増えています。
これまで地方圏で、人口減少と高齢化が先行してきました。今後は東京圏においても、人口減少や高齢化が、急速に進行していく可能性があります。例えば、多数の高齢者が、所得や資産はあっても物理的に充分な医療・介護が受けられない事態を招きかねません。
人口が集中する東京圏での高齢化の進行状況によっては、グローバル都市としての活力が、失われることを想定すべきかもしれません。
住宅ローン金利は「黒田バズーカ」から、10年を経ても超低金利状態が続き、銀行の低金利競争は、住宅ローン利用者を巻き込んでいます。
デフレ脱却をもくろんだ日銀の低金利政策は、住宅市場の活況をもたらしていますが、いつまで続くのか見極める必要があります。
住宅の適正購入価格は、購入後に賃貸に出して、一定期間経過の後に売却した場合にも、損をしないことが目安となります。
持ち家取得では、住宅ローンを組んで住宅ローン控除等の税制優遇措置を受けながら、資産運用している意識を持つことが大切です。
人口減社会は、住宅が人生最大の買い物でなくなる時代の到来を意味しています。
東京などの大都市の一等地に、住宅を購入することをあきらめれば、ゆとりある老後生活のための資金を、確保することができます。
次回更新は11月23日(日)、8時の予定です。
👉『人口減社会の資産運用[注目連載ピックアップ]』連載記事一覧はこちら