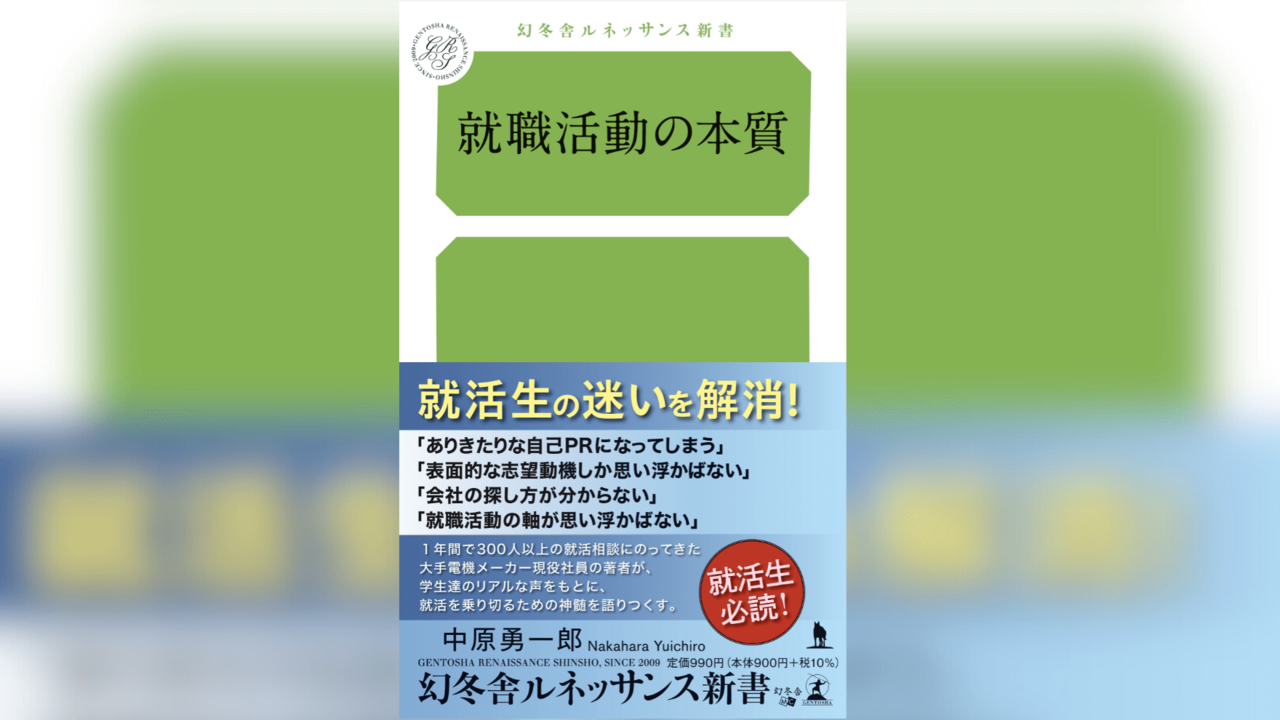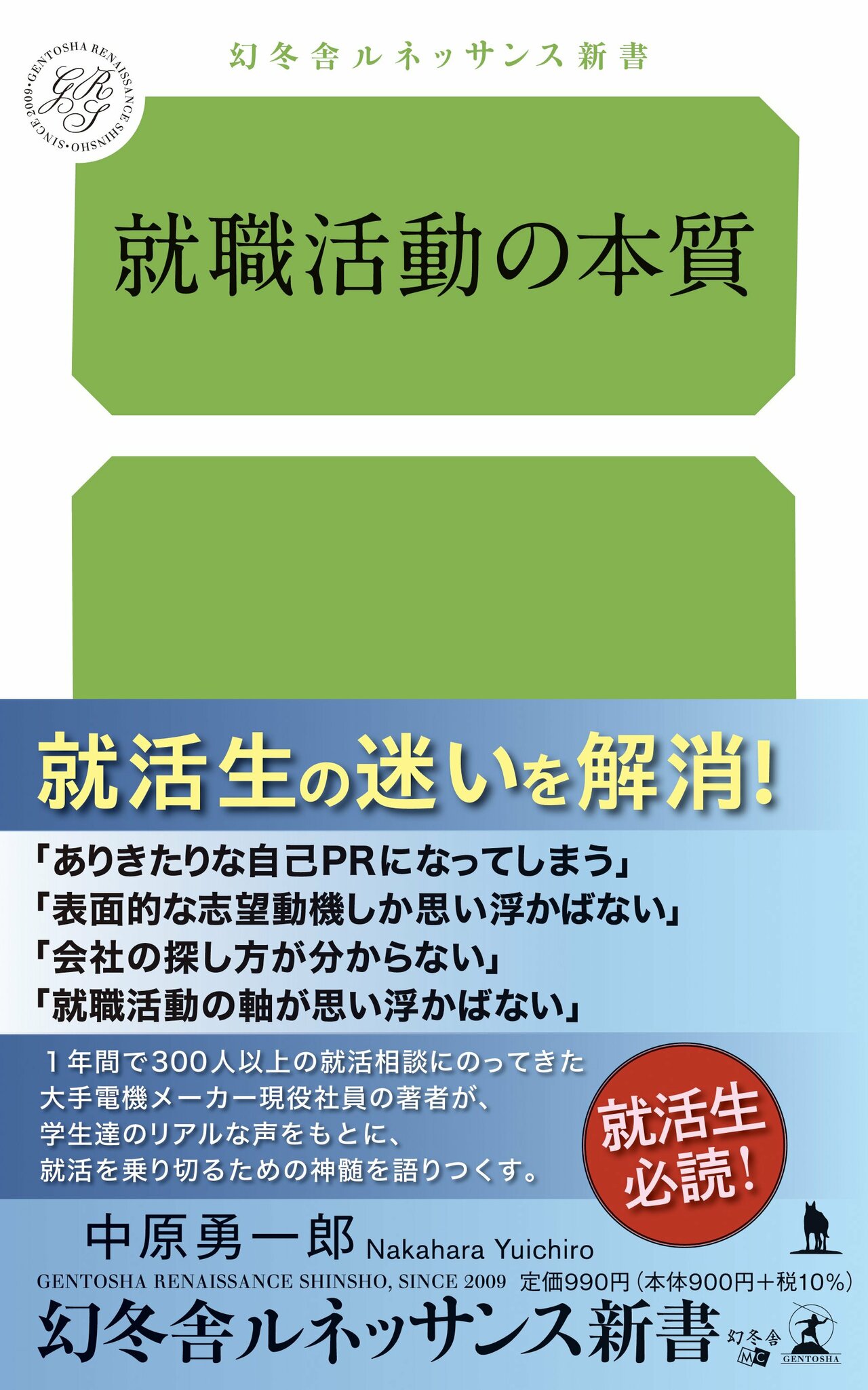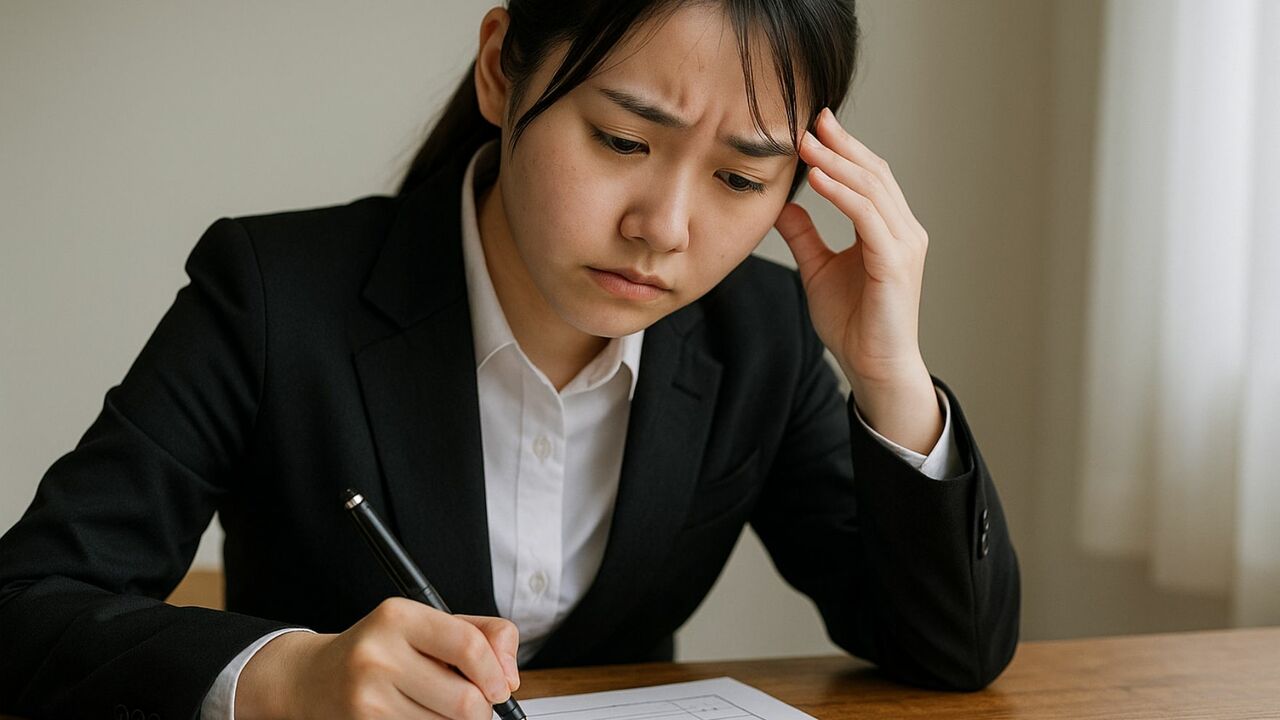【前回記事を読む】12歳の時に父の転勤でアメリカに行き生活が一変。6畳と4畳半二間の団地から30畳程のリビングがあるコンドミニアムへ
第一章 私の学生時代
自由の国アメリカで、楽しいこともあり、辛いこともあり、私にとってはかけがえのない五年間であったが、私がアメリカでの生活で学べたこと、それは英語を喋れるようになったことなんかではなく、日本に対する「愛国心」。
やや右寄りの表現に聞こえるかもしれないが、決してそんな意味合いではなく、日本を離れて日本を初めて知ることができたということ。日本を外からみて初めて日本を意識したということ。そして、自分は日本人なのだな、日本が好きなのだな。日本を馬鹿にされたら怒りがこみ上げてくるんだな。
こんな自覚を覚え、こんな感性を弱冠十二~十三歳くらいで培うことができたこと。それは今の私の中で、私は日本人として誇りをもつ、というひとつのポリシーと化しており、アメリカ生活で得ることができた最も貴重な価値観として心の中に刻まれている。
だから、アメリカでの生活を目一杯謳歌(おうか)して楽しんでいた帰国間際の十七歳の時、父から突然呼ばれて「日本に帰国することになった。お前に一週間やるから、残りたいか、帰りたいか、どちらか自分で選んでよい。どちらでも道をつくってやる」と打ち明けられた際に、やはり日本に帰ろうと、意外にもスムーズに決心がついたのである。
でも、当時の私は十二歳から十七歳までの五年間、一日も日本人学校に通うことなく、当時はまともに漢字も書けず、怪しい日本語を喋る十七歳。
帰国子女枠で面接と論文だけで、受験戦争という過酷な試練を伴うことなく合格することができた同志社国際高校に、本来高校二年生の年齢で、一学年落として高校一年生に編入することになった。
同志社国際高校は自由だった。私服の学校生活。海外生活が長く、日本語のレベルが学年相応に追い付いていない学生に対する特別クラスの設置、大方八割の学生が帰国子女。
そんな長年海外の国々で生活してきた、半分外国人のような学生達が不自由や不安を感じることのない、帰国子女にとっては国外の学校生活と遜色のない雰囲気やカリキュラムの中で、私は日本の高校生活を謳歌することができた。
エスカレーター式で内部進学した同志社大学で、私は文学部・英文科に属していた。大学進学の際に父の希望であり、父との約束でもあった英語教師の教員資格取得。教職課程は大学四回生までしっかり学習し、意外にも私は割と高い成績で四回生の教育実習の年を迎えた。