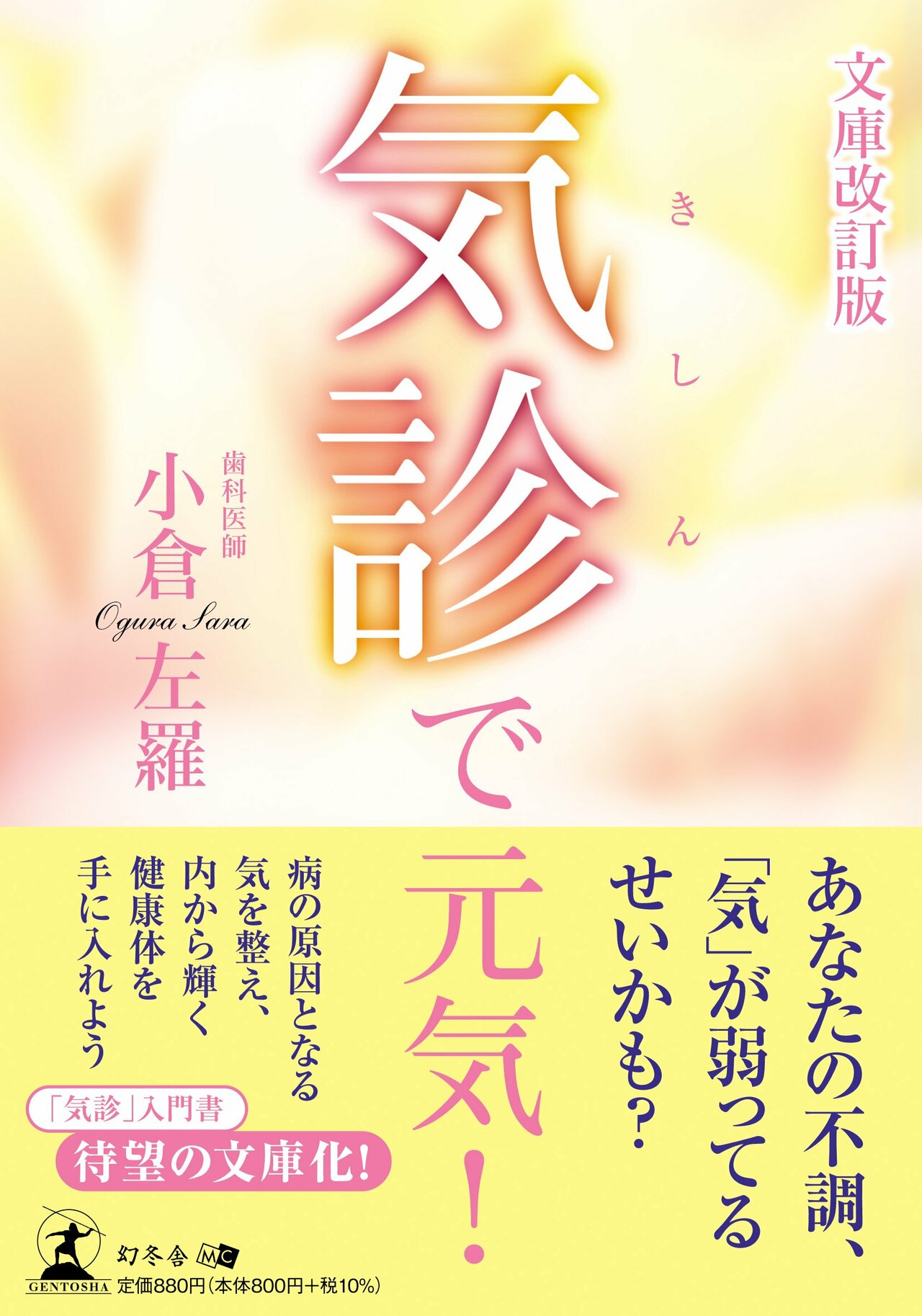七、風邪(ふうじゃ)を取る
第一章で風邪(ふうじゃ)のお話をしました。「気診」ではまず風邪(ふうじゃ)を取ることが大切です。風邪(ふうじゃ)を取ることで、早いうちなら、ちょっと頭が重い、冷える、身体が重い、喉に違和感がある、歯がうくなど身体の異常が改善します。
風邪(ふうじゃ)を「気診」で調べてみますと、どこか具合の悪い人は、周囲の気が雲で覆われ、その人に手をかざすと施術者の胸鎖乳突筋は硬く緊張します。
「気診」を受ける人の風邪(ふうじゃ)を取るには、一般に漢方薬の気を使います。すると身体に合う物であれば筋肉は弛みますので、漢方薬をその人の手の上に載せて合うか合わないかを調べ、合う漢方薬の気を身体を取り巻く気に入れます。
例えば、葛根湯という漢方薬がその人に合えば、手に葛根湯を載せますと雲のように覆っていた気は、さっと晴れるように消えます。施術者が自分の胸鎖乳突筋で調べますと、硬かった筋肉は柔らかくなります。その場合は、葛根湯はその人に合うと判断します。そして、葛根湯の気をその人の気に入れます。ただし季節やその人の状態によって、合う漢方薬は異なります。
入れる場所は、イメージした胃です。軽いカゼならそれだけで改善が見られます。すでに症状が重くなってしまった場合には、何度も繰り返して気を入れます。
身体に合わない漢方薬を手の上に載せますと、身体は緊張し、周囲の気はさらに雲が厚くなり、施術者の胸鎖乳突筋で判定するとカチカチに硬くなっています。実際に受け手の肩などを触ってみますと硬くなりますので、合う・合わないの違いがわかるのです。