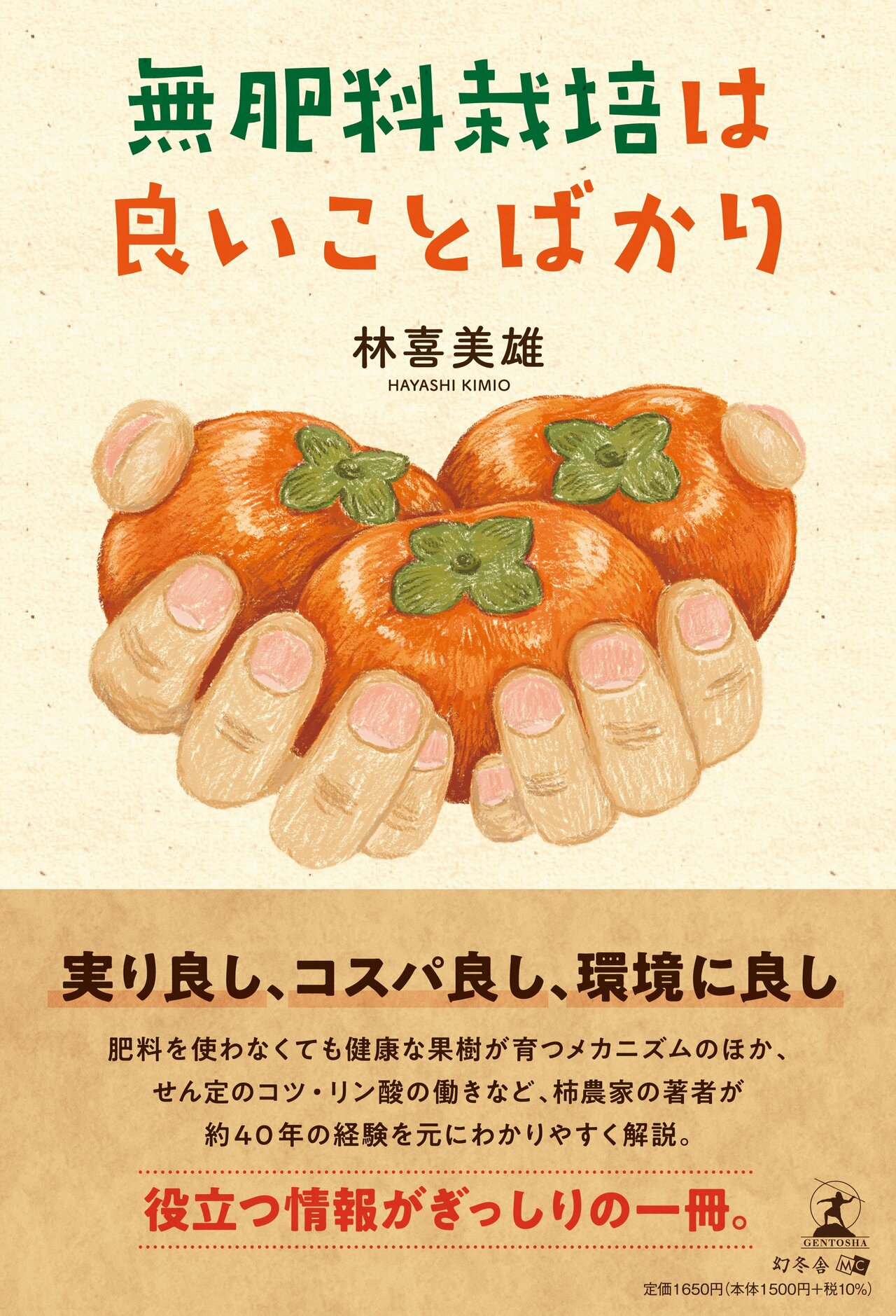2 無肥料栽培への挑戦
無肥料栽培を始める
私がガンの手術をした時、父親は当然のことながら、幼木を全部処分した。病人ばかりでは、面積が広過ぎるからだ。そして、順調にガンから回復した私は、再び柿栽培にもどることにしたのだが、なかなか、気分が乗ってこない。そこで、成木を二反七畝(せ)まで減らした。しかも、無肥料栽培を目標に掲げることにより、仕事量を減らしながらも、収益を減らさないような作戦を立てたのだ。
無肥料で育てると、柿木が痩せがちになり、成らせる実の数は少なくなるが、質は向上するだろうと考えた。結果的に、柿の収益は、ある程度減少するが、農薬の回数が減ることが予想されるし、肥料代が全くかからないことから、減益にはならないだろうという作戦なのだ。
こうして、平成十六年五十五才の時、無肥料栽培を始めてみると、何も変化がないように見えるではないか。数年経って、少しヤワ果が減ったかなという程度であった。
木が痩せがちになったら、実の数を減らそうと思っていたのだが、その必要は全くなさそうだ。木は元気そのものであり、以前と十分同じくらい実をつけることができた。ヤワ果も確実に少なくなり、質も上々であった。消毒の回数は三回程減らすことができ、肥料ゼロと合わせると、大幅に必要経費を削減することができた。したがって、予想に反して、収益は上昇したのである。
無肥料を始めて三年後に、青森県のリンゴ農家の方が無肥料・無農薬栽培に成功したとして本が出版された。同じようなことを考える人がいるものだと、この報により勇気づけられ、無肥料栽培を続けることにした。
ただ、残念なことに、十九年経った現在も、無農薬には至っていないのだ。途中、年二回の散布にまで減らしたことはあったが、特に害虫が、次年度に持ち越し、増加することがわかったので成功しなかったのである。
なぜ、無農薬栽培が成功しなかったのか。それは、柿木が完全には健康な状態にはならなかったものと考えている。ただ、農薬の回数を減らせたのだから、ある程度は健康を取りもどしたことになり、点数をつけると四十点ぐらいであろうか。
健康な植物では、葉で十分な栄養が生産される。そして、生きていくために必要な物質が作られ、必要な場所に送られる。例えば、植物によって異なるが、作られた栄養の二十~七十パーセントが根に送られるとされている。動物のため果実だけに送られるわけではない。
送られた栄養は根から分泌され、微生物を呼び集めるのに使われる。そして、根の周辺に集まってきた微生物は、そのお礼として植物にリン酸等の栄養を補給し、いわゆる共生関係が出来上がっているのだ。人間と腸内細菌の関係と同じであると思えばよく理解できる。
【イチオシ記事】「私、初めてです。こんなに気持ちがいいって…」――彼の顔を見るのが恥ずかしい。顔が赤くなっているのが自分でも分かった
【注目記事】「奥さん、この二年あまりで三千万円近くになりますよ。こんなになるまで気がつかなかったんですか?」と警官に呆れられたが…