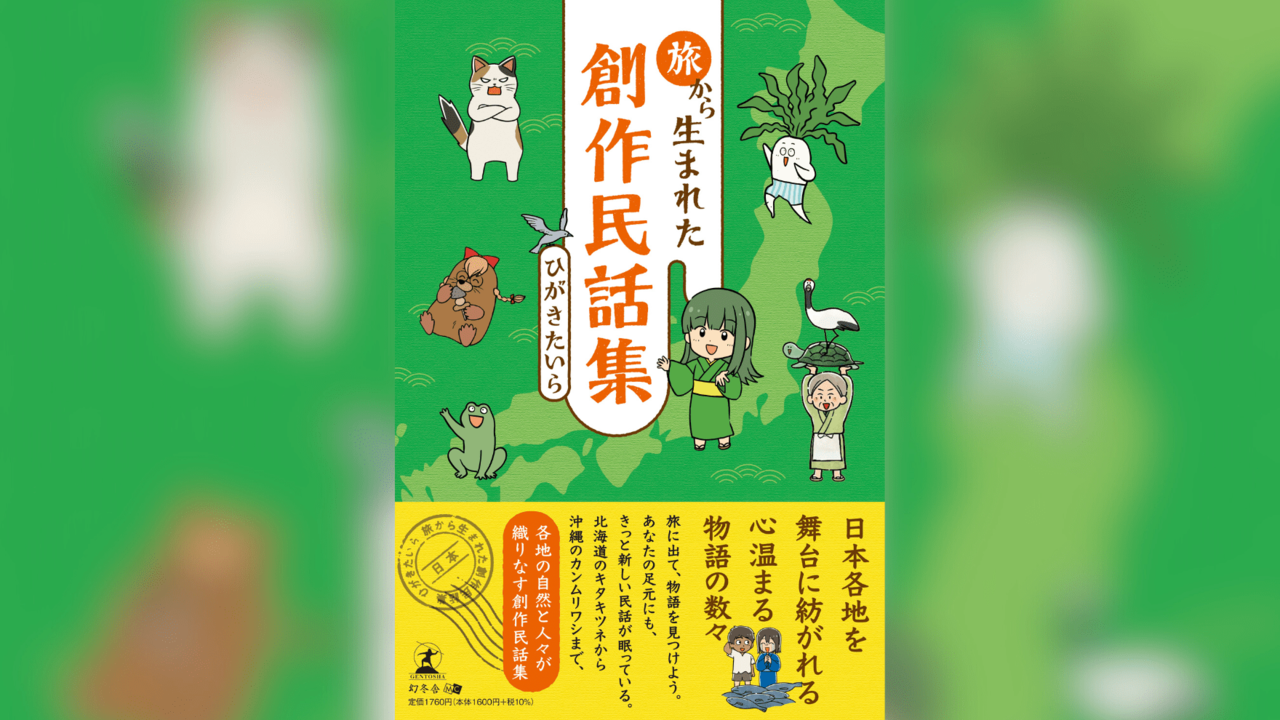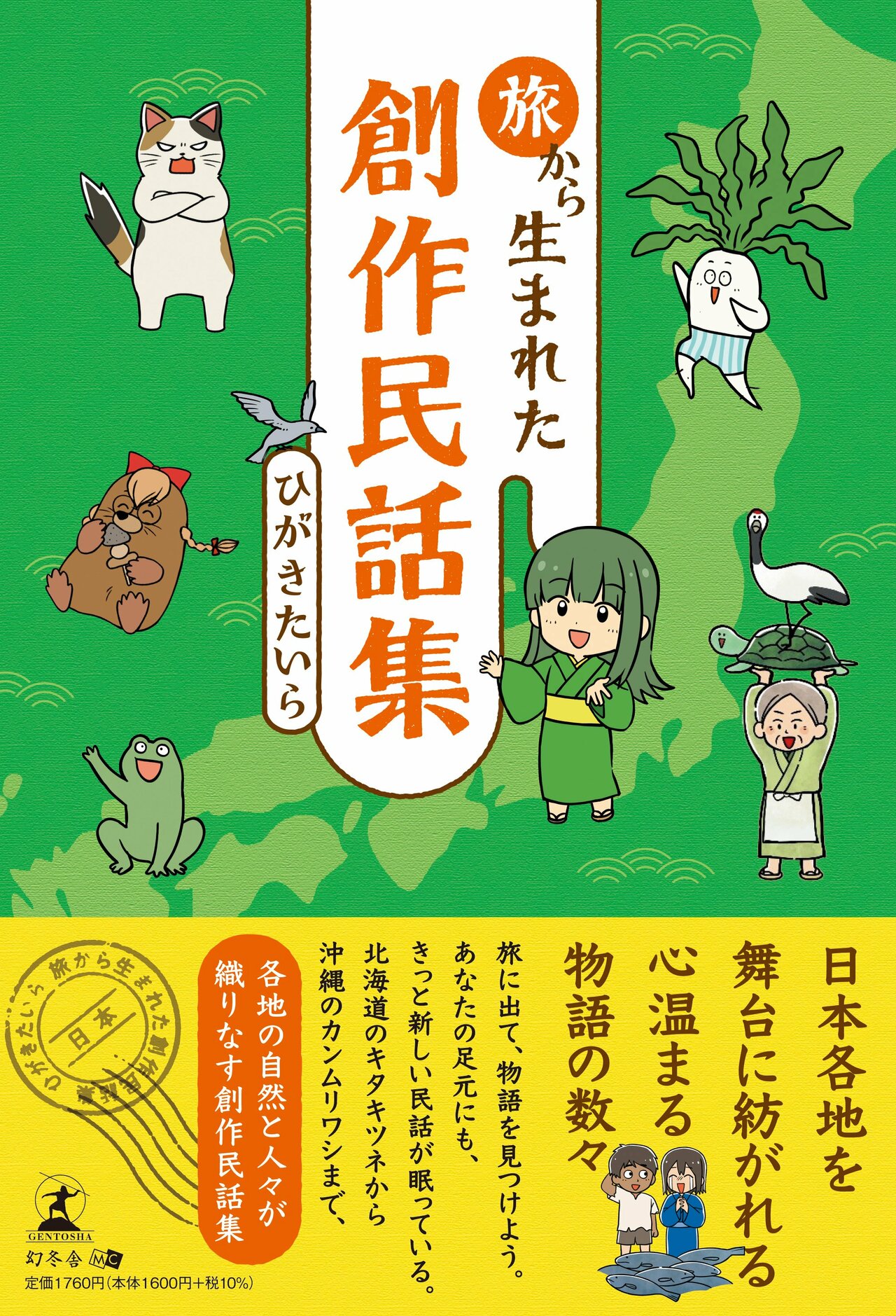はじめに
小学生の頃から、「旅に関わる妄想」が得意でした。最初のきっかけは、西部劇や東宝映画との出会いです。昭和30年代、三流映画館では三本立てで作品が上映され、子供でも手の届く料金で楽しむことができました。
そんな魅力に引き寄せられて、新世界の映画館へ一人バスに乗って出かけたのが、私の「一人旅」の原点です。その頃から、誰かと一緒でなくても行動できるようになり、自転車に乗れるようになると、知らない場所へふらっと出かけることが楽しくて仕方ありませんでした。
27歳で結婚し、子供たちができてからは、即興で思いつきの話を語るのが日課のようになりました。1975年からは精神科病院に看護助手として勤め始め、その間、レクリエーションで紙芝居を作ったり、演芸会の台本を書いたりと、創作活動にも多く関わりました。壁画をスタッフや患者さんと一緒に描いたこともあり、楽しい思い出がたくさんあります。
病院を62歳で退職したあとも、私は新しいことに挑戦しました。71歳でヘルパー資格を取得し、地域の訪問介護の現場に入りました。そこで出会ったのが、29歳の引きこもりの青年でした。言葉を交わすことも難しいほどの壁があり、「赤いポスト」と「郵便屋さん」という情報のみでしたが、彼宛てに「観光案内」や「創作民話」を綴った手紙を出してみることにしたのです。
すると、その手紙が少しずつ彼の心を開いてくれました。やがて行動範囲も広がり、大きな変化が生まれたのです。この体験こそが、私が本格的に「創作民話」を書き始める大きなきっかけとなりました。
当時、私は地域のNPO法人で教育支援のボランティアもしていて、ある日、久しぶりに出会った中学生に「4コマイラストを描いてみてくれない?」とお願いしました。数か月後、「先生、描いてきたよ!」と渡された作品は、想像を遥かに超える素晴らしさ。物語とイラストの相乗効果を、肌で実感した瞬間でした。
私は文章のプロではありません。それでも、2019年から今まで、47都道府県を題材に中編・短編合わせて57本の創作民話を書き上げることができました。旅の記憶や、まだ訪れていない地域への興味から、物語の構想は尽きることがありません。「終わり」はなく、つねに「続き」があるのが、旅であり、創作なのです。
旅先で出会う人々の笑顔、心に残る方言、郷土料理や特産品。そうしたひとつひとつが創作のヒントであり、物語の素材です。
誰かの心にそっと寄り添うような物語を、子供たちにも届けられたら ― そんな想いが、筆を動かす原動力になっています。
「旅に出て、創作民話を書いてみよう」― 皆さんにもそう思ってもらえれば、私にとってはこの上ない喜びです。