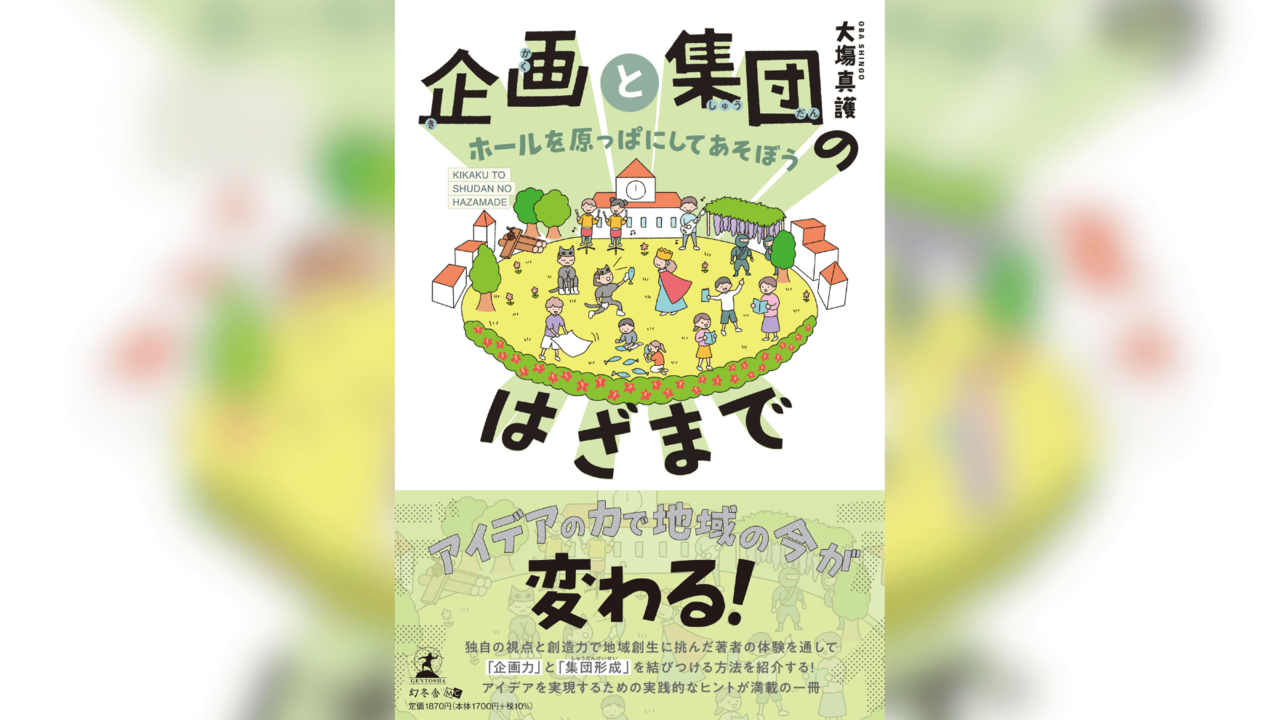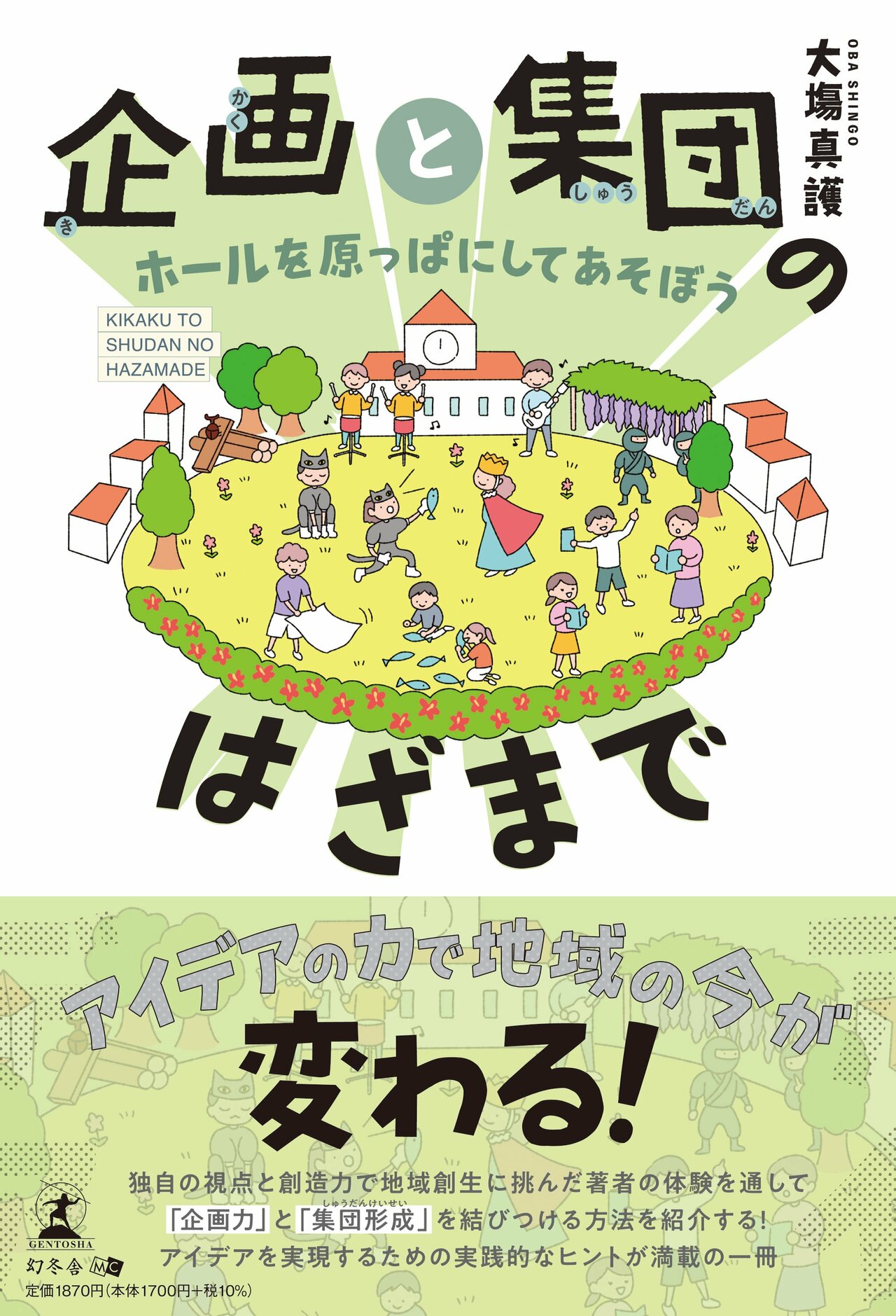【前回記事を読む】「なぜ~するの?」にうまく答えられないのは、そこに2つの「WHY」があるから。一つは、心の中にある動機。もう一つは…
第1部 理論編・企画を解明する
第一章 樹に学ぶ
第一節 動機(種/根)
種
物事を発生させる心/脳については多くの仮説が、心理学者や歴史学者や思想家によって述べられています。「エロスとタナトス」や、「生命力の過剰」といったことばで、とめどなく動く脳のエネルギーの根源 ── 物事を発生させる原因 ── について解析しようと試みてきました。
その一人にロジェ・カイヨワ──フランスの文芸批評家、社会学者、哲学者(1978年死去)──がいます。
1958年の『遊びと人間』で、社会本能として「あそび」の4要素──競い、賭け、真似、目眩──を提示しています。その後の「戦争論」には、「人間がなぜ戦争に惹き付けられてしまうのか」という、綺麗事ではない赤裸々な人間洞察が書かれています。
動機が即目的
表現欲求もこの4つの要素が組み合わさったものと考えられます。遊びですから。
絵を描くのが好き、楽器を奏でるのが好き、舞台に立つのが好きといった人が、表現するために人を集めて会を開いたりします。「みんなで~する」という動機が即目的となる人もいて、これまた実施まで一直線に進めていきます。
読まれるものとしての種
「種」で思い出すのは、詩人長田弘さんの次のような一節です。
──病院に訪ねてきた、詩人になろうと思っていた未知の青年に、パウンド*は言います。
「もし君が詩人になるつもりなら、毎日、詩に取り組まなければならない」
そののちにパウンドからもらった手紙の一行は、マーウィンには忘れられない一行になります。
「小枝ではなく、種を読むこと」
小枝は目に見えるもの、種子は目には見えないもの。若いマーウィンは、目には見えない詩の種を求めて、「文化共同体」の伝説の地を求めて南フランスの片田舎に移り住みます。
(長田弘『幼年の色、人生の色』みすず書房 2016年)
伝説の地でなくても、地域には自然と人間が織りなす「場」、人が集まれば発生する「集団」、あるいは過去からいまという「時間の蓄積」が混在しています。
旅してきた詩人のように、一度よそ人の視点で地域を見渡せば、近くに目に見えない種を発見できるかもしれません。そこから自然にアイデアが生まれてくるかもしれません。