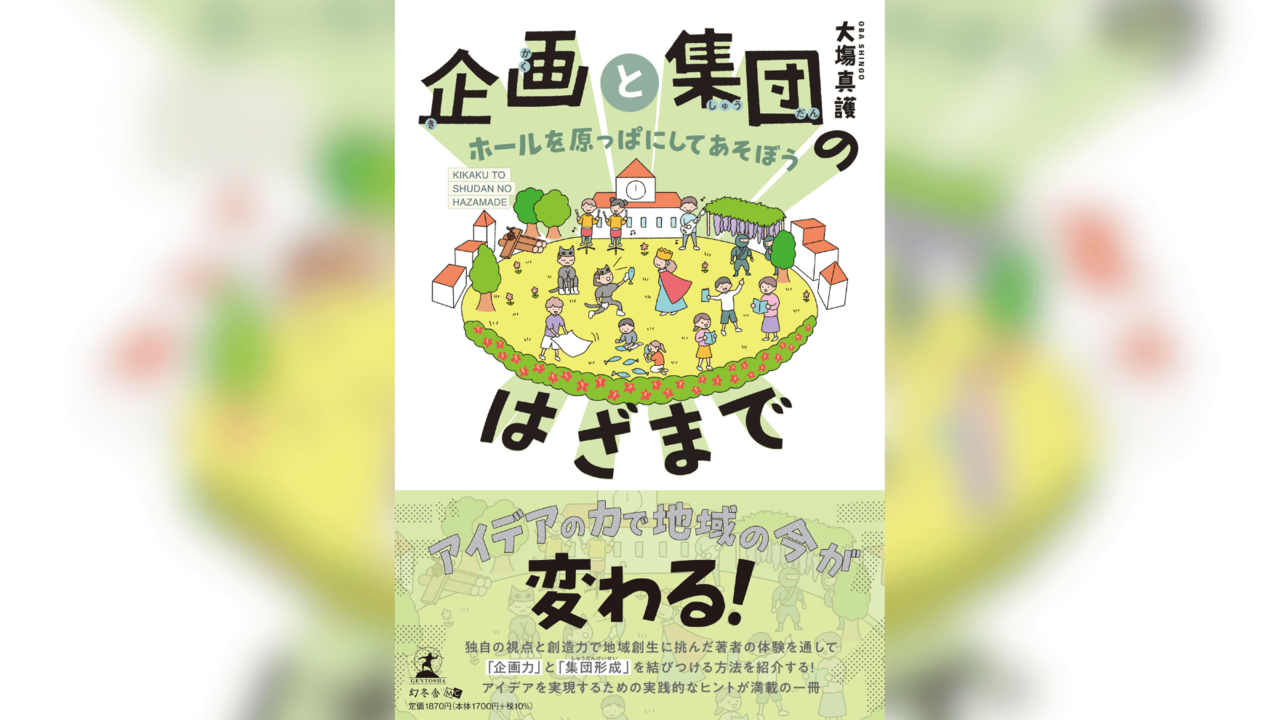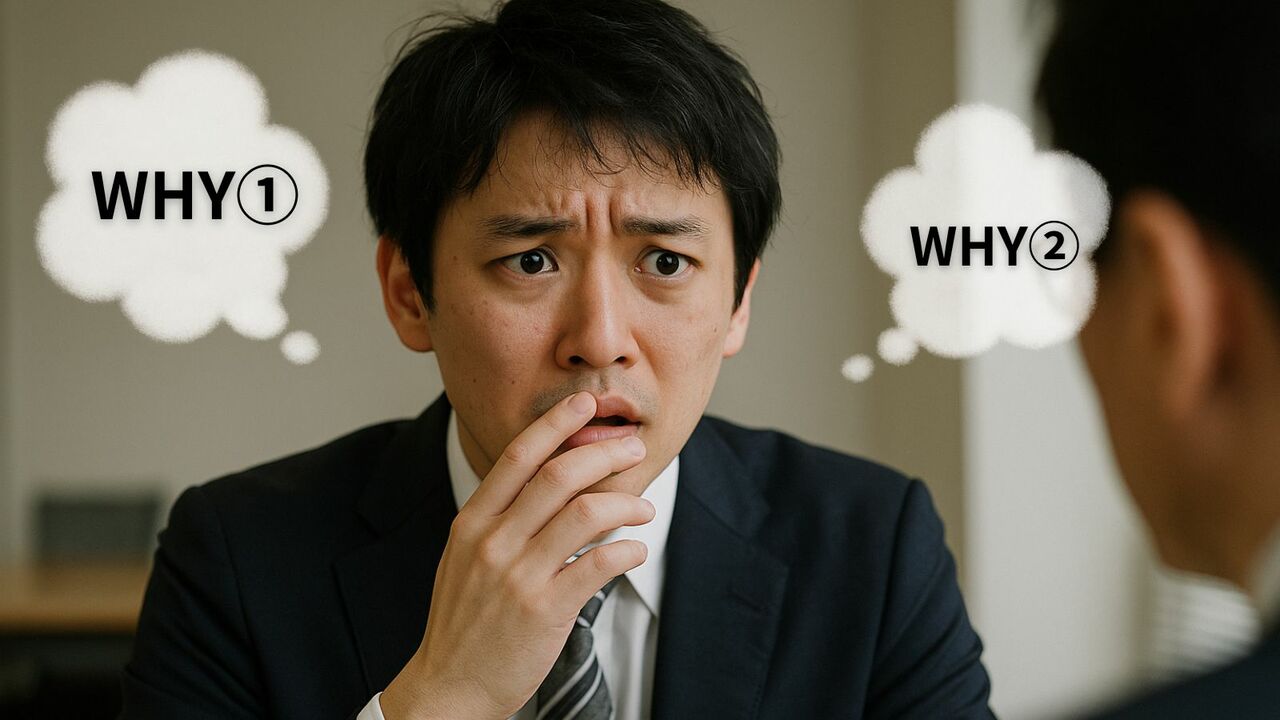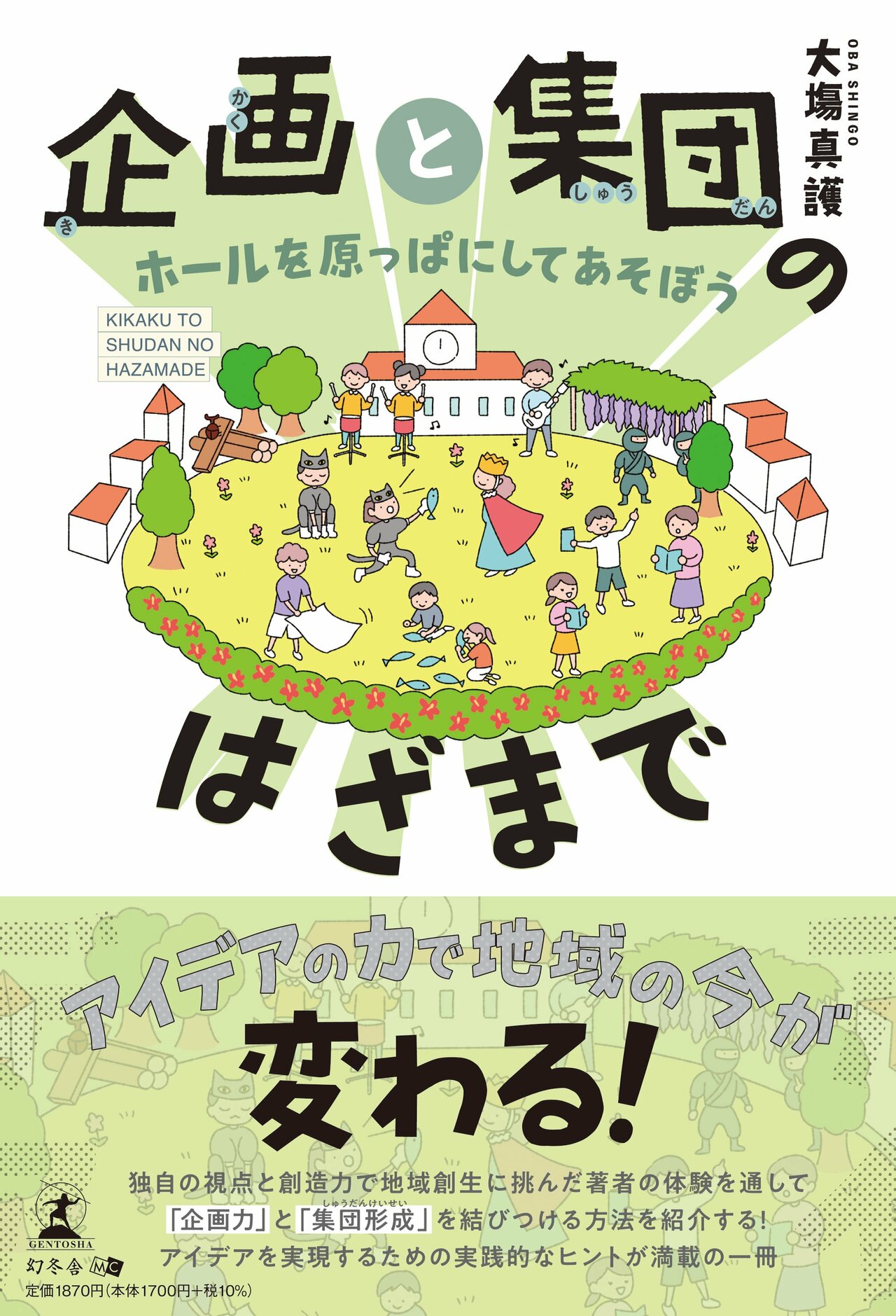【前回記事を読む】「企画」と「企て」は何が違う? 地域で続く文化事業の真の価値とその根を支える見えざる労力とは
まえがき
「集団」の集は「鳥が木の上に集まってくる」という意で、それを打ち固めてまるい形にすれば団となる。企画という樹に市民が集まってきて、ゆるやかな共同体としてNPO法人という実を付ける。成った果実は地に落ちて、そこから地域の多くの老若男女を巻き込んで、木を育て企てを実践し、最後に実を付ける。
「企画」ということばの構築には労力が必要になり、一方で常に揺れ動きながら変容していく「集団づくり」にも異なったエネルギーを要する。
地域で中規模な企てを継続するには、相対立する、秩序立てたものと常に変容するもはざまの ──2つの間で試行錯誤することで、どこまでいってもきりがない。
文化・芸術の領域に留まらず、地域のどこに身を置いていても同じと思う。
さまざまな形の集団が起こす混沌さと凶暴さが毎日流れてくる。熱い仲間たちが引き起こす混乱であったり、冷たい組織が引き起こす凶悪さであったり……。
ともかく歴史は繰り返されている。
こんな時でも、いやこんな時だからこそ、地域という片隅にいても、「企画」という仮説を立て、「集団」が生み出すまっとうなエネルギーと喜びを多くの人と共有していくことは意義深いと感じる。
第1部には「樹に学ぶ」として、樹の構造に則しながら企画のシステムについて述べる。次に実践していく上での要となる「方法」を解剖してみた。そこから辿り着いた「企画費・制作費」が「公益性」の視点からは欠かせないことについて付録として記した。
第2部の前半は、女子中学生の担任として「影絵」を始め、それをきっかけにしてクラスや学年のあり方を見直した記録である。今でも実践している集団の原型図(P158)も載せた。30年たった今でもこの捉え方は変わっていない。
第2部の後半は、退職後の6つの場所での中規模な9つの企てについて、それぞれの「きっかけと動機とひらめき」を中心にして、間には関わった方々のことばも挟んでの記録である。
第3部として、NPO法人「企画 on岡山」について記す。企画開始から10年目の今年辿り着いた集団の容(かたち)について会員募集チラシに書き込んだことばを中心にまとめてみたいと集団図を置いてみた。
できる限り多くの方に手に取っていただきたいのですが、特に、ひらめきはあるがそれをどのようにしたら実現できるのか悩み始めた人、地域で企画し始めたリーダーやビジネスパーソン、あるいは消滅しかかろうとしている集団の舵取りを担ってしまった方々の参考になればと思います。どこにいても企画と集団の狭間(はざま)にいることに違いはないでしょうから。
そこから一歩を踏み出し、試行錯誤しながら進まれることを願っています。もっとも、最後までお読みいただくと、多くのコトが試行錯誤の途上であることがおわかりいただけると思います。