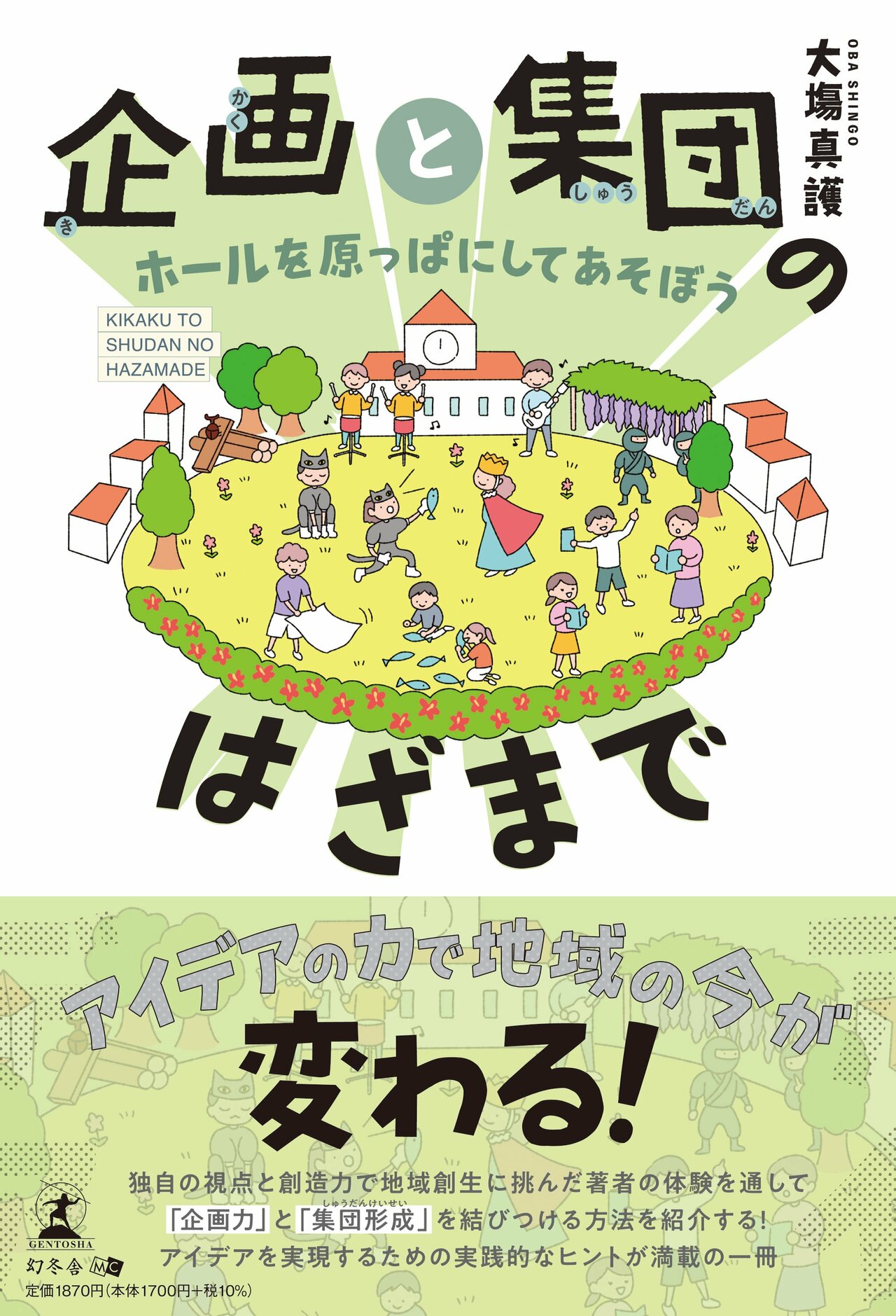第1部 理論編・企画を解明する
第一章 樹に学ぶ
週に一度里帰りをして土を耕す畑の横には2本の柿の木があり、毎年、甘柿と渋柿を美味しく頂いています。気がつけば木は若葉を出し、ちっちゃな実をつけ、徐々に大きくなって赤みを帯びてくる。そして最後は土に葉や実を落とし、冬の間は枯れ木のごとく立っている柿の木……。
その静かな「循環システム」をなぞっていけば、こだわってきた「企画」について説明できるのではないかと10年ほど前に考え始めました。「根幹をなす」や「年輪を重ねる」や「枝葉末節のお話」のようにものごとを樹のシステムになぞらえて表現する先人のことばもあります。「桃栗三年柿八年」ということばもあります。
6年前に県立図書館でたまたま『小学館日本語新辞典』(松井栄一)を手にしました。外国の人のために、所々で類似した主要なことばの比較が記されています。「目的」を引いたところ「目標」などとの違いが詳しく説明されていて、頭がすっきりしました。各項目の最初にその短い説明を置くと、そのことばに触発されて筆も進みました。
第一節 動機(種/根)
種
種:植物が目を出すもとになるもの。物事を発生させる原因・理由となるもの
「なぜ~するの?」と聞かれても、答えに迷ったり、話がかみ合わなかったりする時があります。それは、「なぜ」の中に個人的な心の中である「動機」(WHY①)と、社会との重なりである「目的」(WHY②)があるからです。「目標」も人によっては含まれたりします。
「動機」は柿の木で言えば「種や根」で、「目的」は「幹」、「目標」は「枝」となります。
樹では一粒の「種」の中にさまざまな遺伝子を内包し、環境からの刺激によって根を生やし、土から水と栄養を摂取し芽を出します。
【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…
【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった