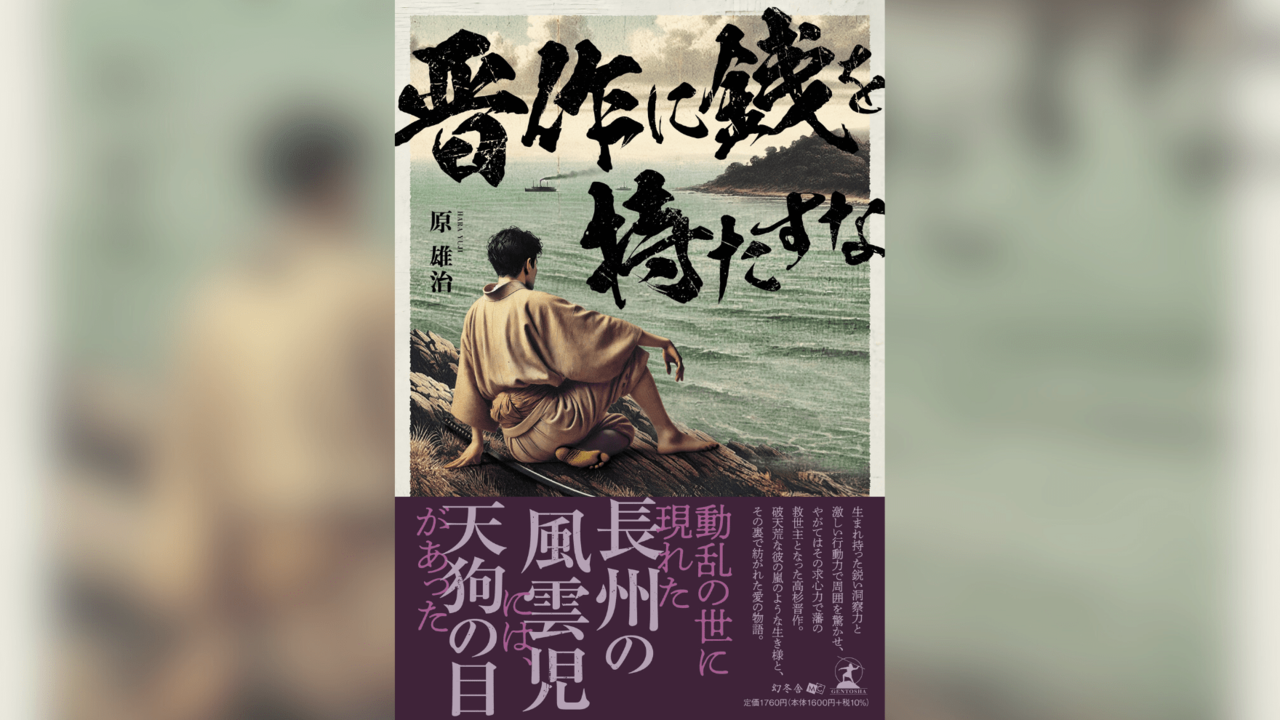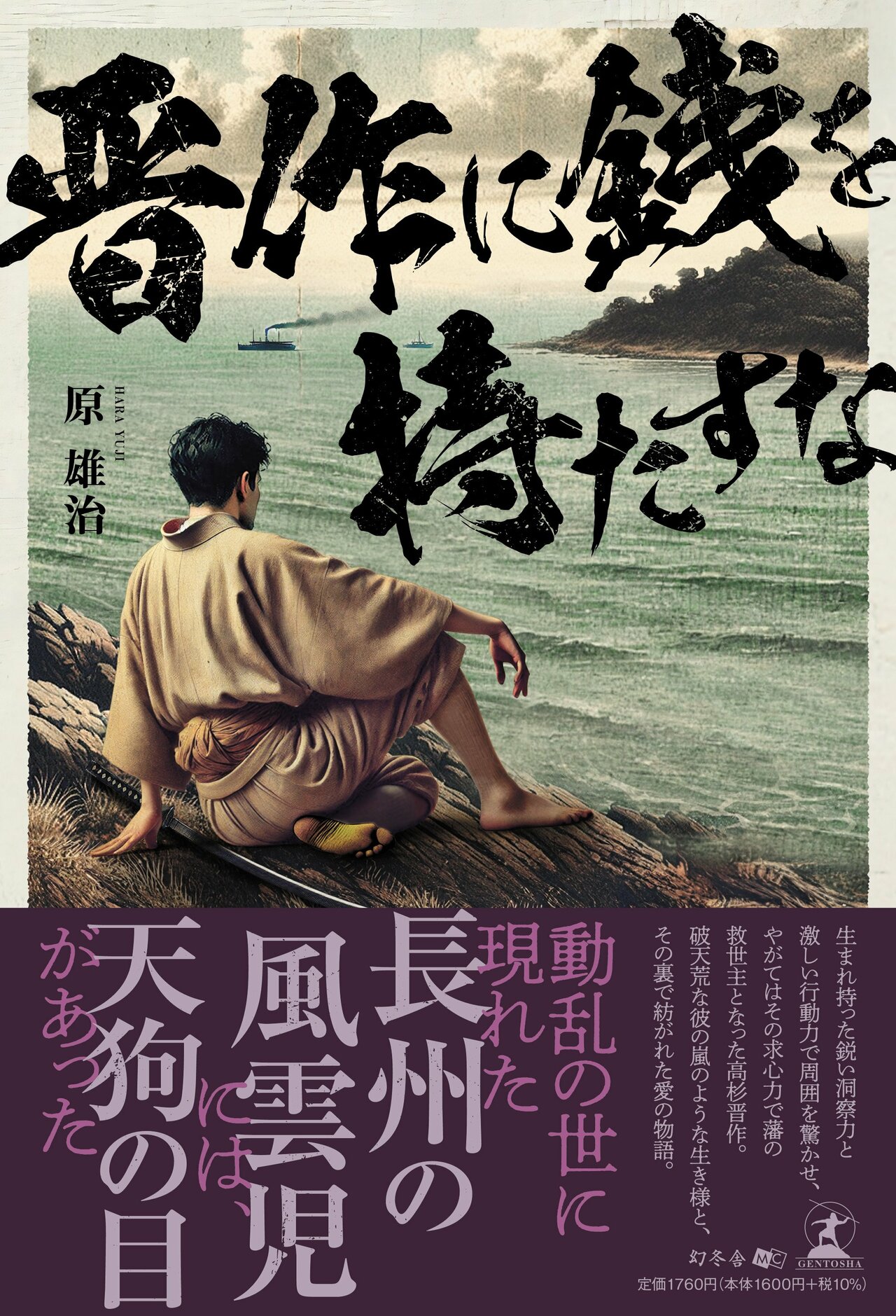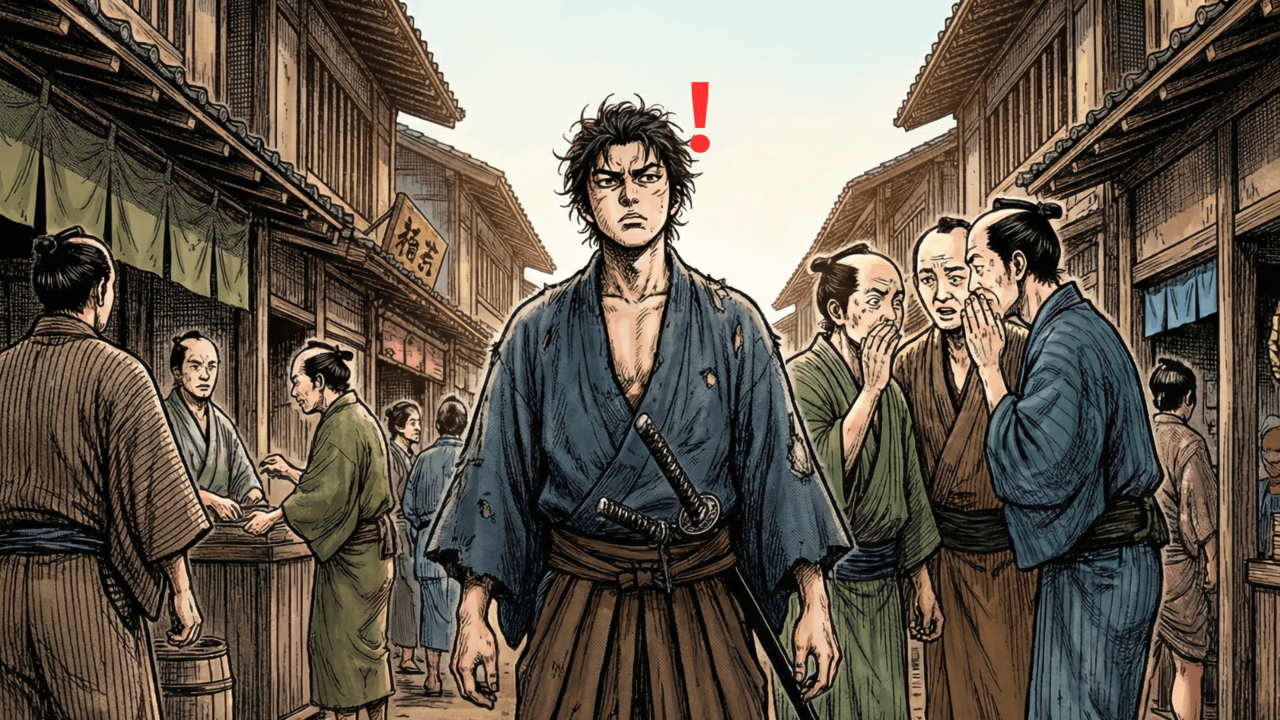【前回記事を読む】「おまえには天狗の眼がある」――悪戯ばかりの晋作に、怒るのではなく真っすぐ語りかけた父。当時の晋作には分からなかったが…
天狗の申し子
小忠太は結論から語り始めた。
「『負ける戦はするな。負ける喧嘩はするな』『戦とは謀略、つまり騙し合い。だから敵に勝つ為には敵の弱点を読み切り、そこに謀略つまり罠を仕掛けよ』それが毛利元就公の戦い方だった。しかし十四代当主の毛利輝元公は全くこの考えを受け継いでいなかった。
むしろ、元就公の考えを受け継いでおられたのは家康公であった。その結果、輝元公は関ヶ原の決戦で惨敗し、滅亡するところを従兄に当たる吉川広家公に救ってもらった。今の岩国吉川藩の祖に当たる人だ」
小忠太の初日の講義はこの話だった。
講義は一日五十分で、この日から続けて五日間に及んだ。
二日目の講義は午前八時から始められ、何故負けてはいけないかについての話だった。
小忠太は関ヶ原惨敗の結果、ここ萩に城が築かれ城下町が開かれた経緯を語った後、高杉家が一五〇石に決まった背景を語った。
惨敗した輝元公は頭を丸めて僧になり家康公からの沙汰を待ったが、家康公がお家取り潰しを一旦は決められた後、広家公が家康公に対して「約束が違う」と言って猛烈に抗議された結果、輝元公は今の長州藩の藩祖に落ち着いた。
実は家康公と広家公との間には関ヶ原決戦開始直前に秘密の約束があった。今では関ヶ原決戦は東軍の徳川家康公対西軍の毛利輝元公の二人の大将の天下分け目の戦いと言われているが、実のところは騙し合いの戦であった。
秀吉死後家康公は、長い時間をかけて秀吉子飼いの武将福島正則や加藤清正などを手練手管(てれんてくだ)で味方に引き込み、自らの意に従わない東北の大大名上杉景勝を切り従える為と称して、幼い秀頼を遺したまま福島正則や加藤清正らの総勢数千人の軍を率いて大坂城を出た。
家康公は大坂城を出る時、輝元公に「秀頼公の守りは輝元殿にお願いする」と言って輝元を大坂城に足止めにした。
輝元公は豊臣秀吉から可愛がられ、秀吉亡き後の豊臣政権を継承する五大老の第二位になっていたので、家康公の申し出を反対されることなく受け入れられた。
勿論五大老の第一位は徳川家康公で、家康公は秀吉亡き後は秀頼守護を名目に、自分の勢力拡大の方策を遠慮することなく矢継ぎ早に打ち出されていた。つまり家康公は豊臣政権とは名ばかりで、実は徳川政権の足固めを着々と進めておられた。この流れの中での上杉征伐だった。