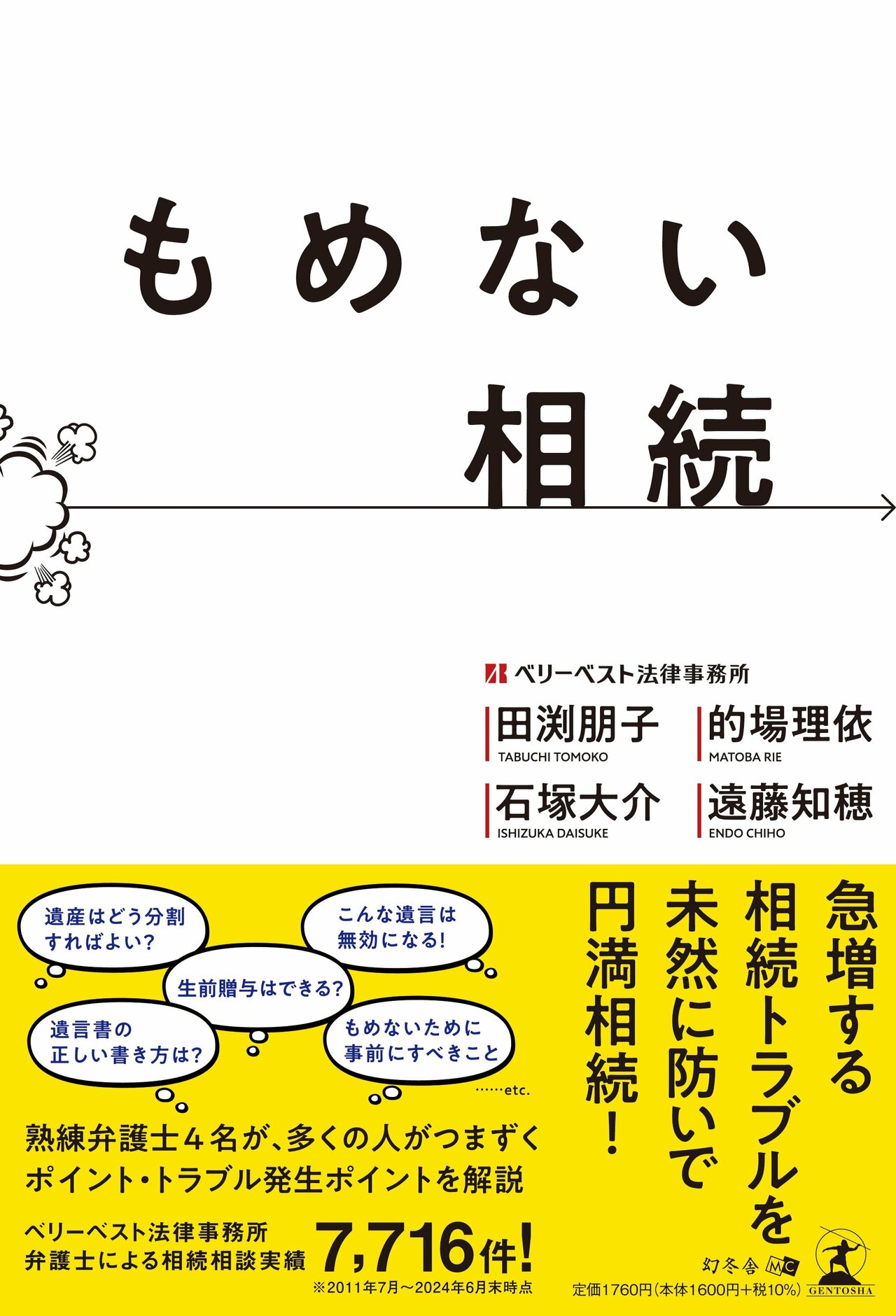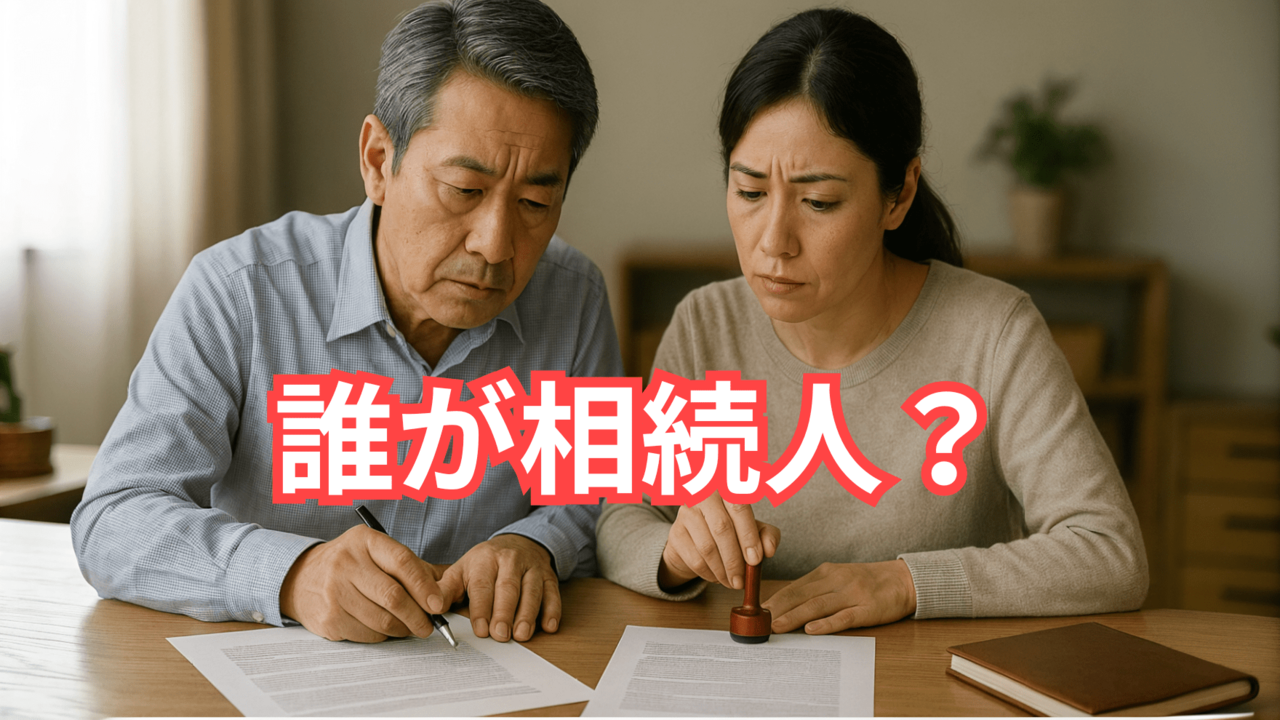2 相続人の範囲
(1) 相続人は誰なのか
遺産分割は相続人全員で行う必要があるため、誰が相続人であるかを確認しなければなりません。遺産分割協議に相続人でない人が参加した場合や、参加すべき相続人が参加していない場合には、遺産分割の有効性に問題が生じてしまいます。
遺産分割協議をする上で協議する相続人の範囲については、民法にそのルールが定められています。
(2) 相続人の範囲
民法に定められた相続人のことを法定相続人といいますが、その法定相続人について、その範囲と相続の順位のルールを説明します。
①配偶者
被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
被相続人が亡くなったときに法律上の婚姻関係にあれば、配偶者として相続権が認められます。他方で、内縁関係など実質的に夫婦同様の関係にある場合でも、法律上の婚姻関係がなければ相続権はありません。
②血族相続人
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
ア 被相続人の子(第1順位)
被相続人に子がいる場合は第1順位の相続人となります。
被相続人よりも先に子が亡くなっている場合や、相続権を失った場合(廃除、相続欠格)でも、その子の直系卑属(子や孫)が相続人となります。
このような被相続人の子が亡くなったり相続権を失ったりした場合に、その子に代わって直近の卑属が相続人となることを「代襲相続」といいます。なお、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないというルールがあります。
そのため、養子縁組をした後に養子の子が誕生した場合、その子は養親の孫(直系卑属)となりますが、他方で、養子縁組の前に出生していた養子の子は養親の卑属ではなく代襲相続とはなりませんので、注意が必要です。
イ 被相続人の直系尊属(第2順位)
相続人となる直系尊属は、近い世代の順に相続人となります。第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。
ウ 被相続人の兄弟姉妹(第3順位)
被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子の世代まで代襲相続が認められます。