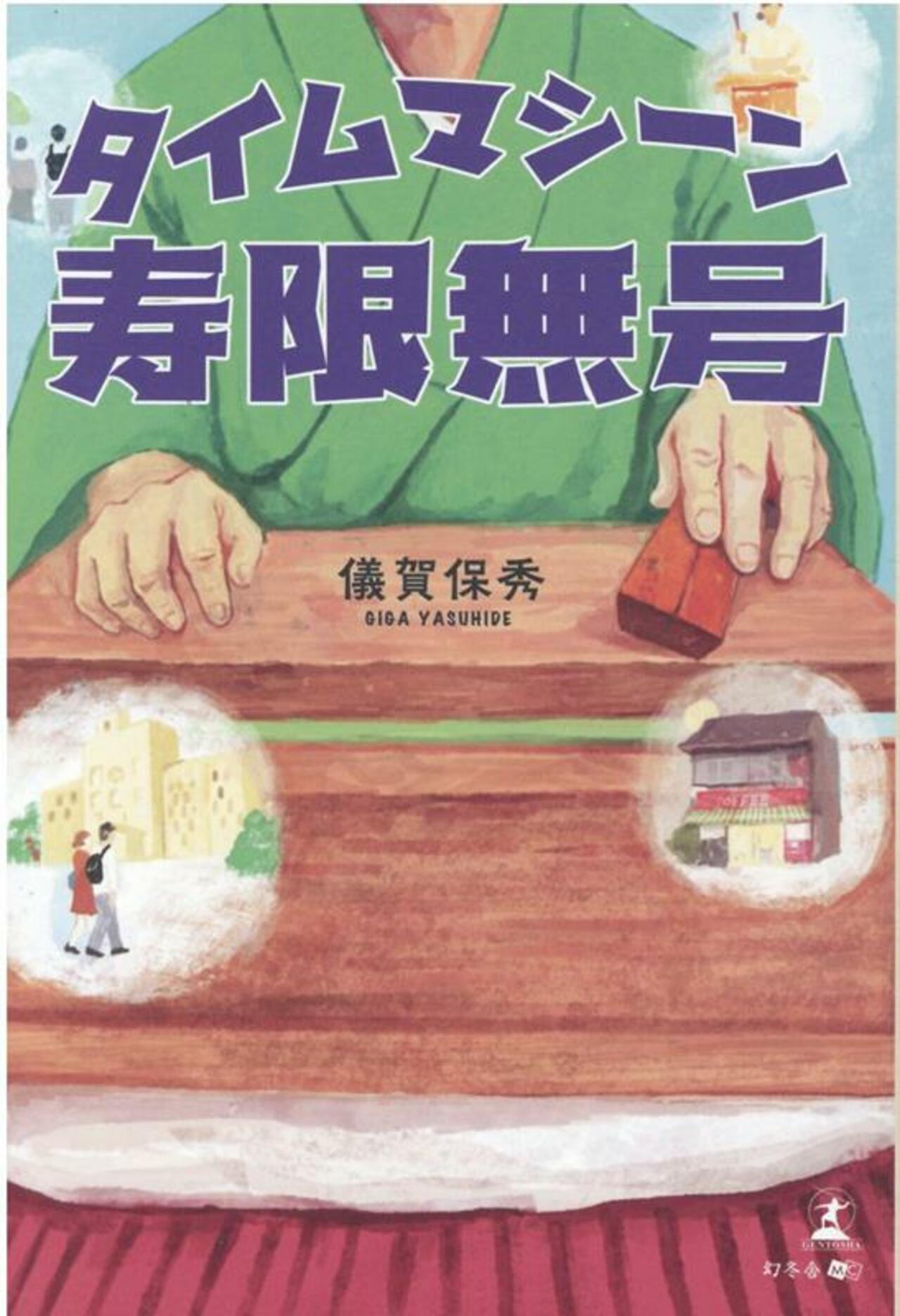そんな源太郎が三十周年の話題に触れた。
「これも三十周年の前祝いちゃうか? 何かの縁やないか」「何かの縁?」喜之介は考える。
こんな俺でも弟子になりたいという人間が現れたのだ。
しかも三人も! これも何かの縁か……。
まあ、そうやわな。
三人それぞれに自分を師匠として選んだ理由を聞いたが、それなりに嬉しい言葉が聞かれた。正直、すごく良い気分だった。
そんな人たちの思いをはねのけて「弟子は取りません!」そう言い切る自信はなかった。
「相談と言いつつ、克ちゃんの気持ちはもう決まってるんやろ?」
自らの思考に没入していた喜之介を呼び戻すように源太郎が言う。
「な? そうやろ?」
「うーん」唸っては見たものの確かに源太郎の言う通りだ。
弟子を取ってみても良いかも? その思いに感情のベクトルは向いていた。
「けど……」喜之介の中には一気に突き進む勇気もない。
「けど……何やねん?」
「弟子を取るっていうことは、その人間の人生の面倒を見るっていうことやろ? 一人の人間の人生を背負うってことは責任重大やと思うねんけどなあ」
「ハハハ」源太郎の高笑い。
「何がおかしいねん」
「確かに突き詰めて考えたら、そういうことやねんけど、そこを考えすぎると大変やで。もっと気楽に考えたらええねん」
「ほな、ケンちゃんはどういう気持ちで弟子を取ってんねん?」 既に五人もの弟子がいる源太郎に聞いた。
「そうやなあ。まあ、それなりに真剣に接してるけど、人間というのは合う合わんがあるしなあ。最初は俺の弟子になりたいって来ても、実際に弟子に取ってみたら、うまくいかんことも多々あるわ。
今は弟子が五人いるけど、辞めていった人間も同じぐらいの人数いてるし……早い奴なんか一週間ほどでリタイアや」
そうなのか。その辺の詳しい話はあまり聞いたことがなかった。
「そやから、そいつの人生を背負うとか、あんまり深く考えんと、気軽に弟子にしてやったらええんちゃうかな。他の師匠方は知らんけど、俺はそう思ってるし、実際、そういうふうにやってる」
確かに必要以上に深く考える必要はないのかもしれない。
「自分が弟子入りした時のことを考えてみたらどうや?」源太郎が言う。
「もちろん、真剣に弟子入りを頼みに行ったけど、師匠に自分の人生を委ねるって、そこまで重いことを考えてた? もっと気軽やなかったか? 俺はもっとドライに考えてたけどなあ」
源太郎の師匠は、今は亡き桂源兵衛だった。