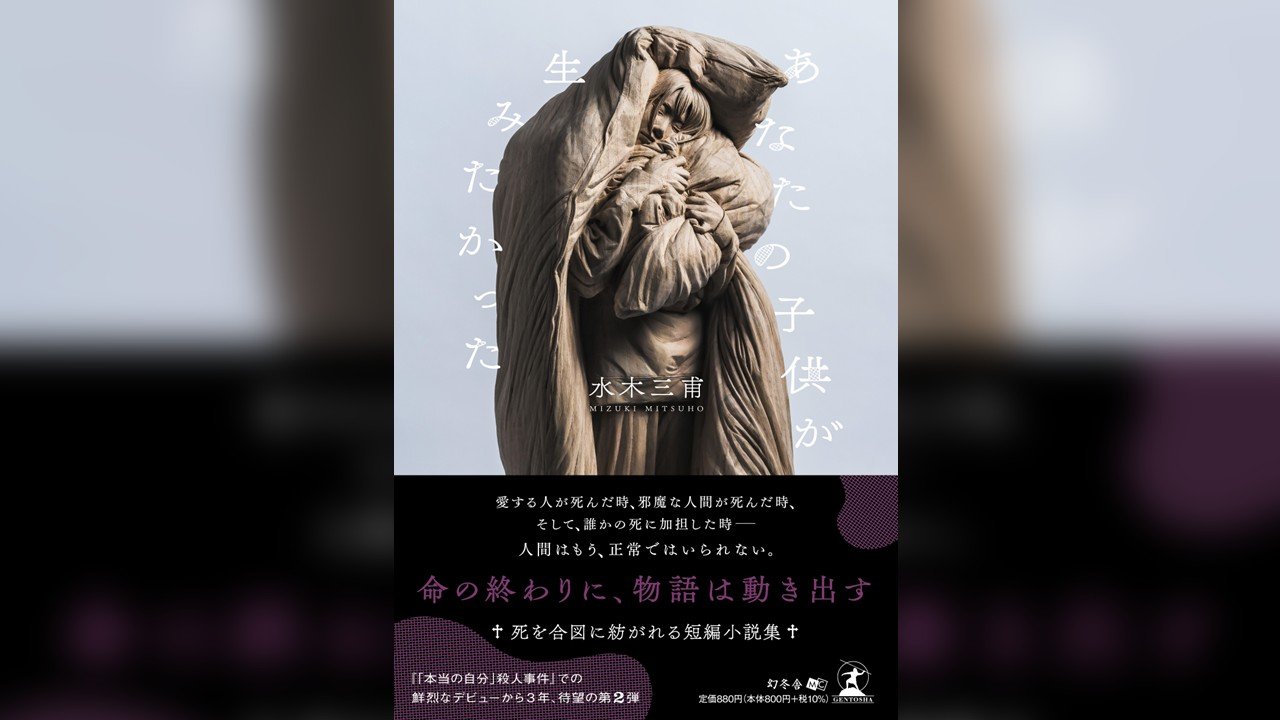【前回の記事を読む】墓に埋まっているのは、自分の一部かもしれない…スコップを骨壺にカチンと当てる。大きな骨の塊を拾い上げ、靴跡を丁寧に隠し…
湖の記憶
4
河西琴音とは写真スクールで出会った。クラスは十二名で、女性は三名しかいなかった。その中の一人が河西琴音だった。大きな瞳、鼻梁はまっすぐ通っていて、鼻頭だけちょこんと尖っていた。口も大きく笑顔には華があった。
講師はプロのカメラマンで、佐々木夏彦と名乗った。
「初心者コースへのご参加ありがとうございます。今のカメラは性能もよく、携帯電話の写真でもプロ並みの写真を撮ることができます。
しかし、ここに参加した皆さんはさらに上のレベルを目指したからこそ、お金まで払ってこのスクールに参加しました。プロのカメラマンを目指している人もいれば、みんなとはちょっと違う格好いい写真を撮りたいという人もいるでしょう。
プロとまではいかなくても、皆さんが払ったお金以上の成果を上げられるよう、私も頑張りますので、皆さんも頑張ってください」生徒たちは真剣な眼差しで講師を見つめていた。
「まずは皆さんに自己紹介してもらいます。その際、持ってきたカメラの機種も発表してもらいます」
自己紹介がひととおり終わった。年齢層は幅広く、最年長は七十二歳の白髪頭のじいさんで、サトルが一番若かった。
カメラの構造や撮影、現像、プリントなど写真作りのプロセスについての講義が終わり、五分間の休憩があった。
休憩が終わり、生徒が全員席に着いたのを確認後、佐々木講師が言った。
「今日は皆さんに、今まで撮った中でお気に入りの写真を二十枚持ってきてもらいました。まずはそれを机の上に出してください」生徒たちがバッグから写真を取り出した。
「皆さんの写真には、皆さんそれぞれの癖が表れています。人物を写すか、風景を写すかといった被写体の選び方、被写体との距離感や構図、どんな色がよく写っているか。それぞれが皆さんの見る目の個性と言えます。まずは自分の個性を探してみましょう。そして、それをメモしてください」
サトルにとっての被写体は湖と決めている。しかし、わざわざ湖まで行って、写真を撮ってくるわけにはいかず、サトルは近所の公園の噴水や木々の緑、道路沿いに並べられた花壇の花々、お寺の境内など風景を撮影していた。
写真のほぼすべてに空が写っていたので、青色が多く含まれている。被写体との距離は様々で、特に癖があるようには思えなかった。
「終わりましたか? 終わっていない人は手をあげてください」手をあげる生徒は一人もいなかった。
「それでは二人一組になってください」
初めて出会った者同士が牽制する中、サトルは真っ先に河西琴音に声をかけた。
「よろしくお願いします」
琴音はちょこんと頭を下げた。