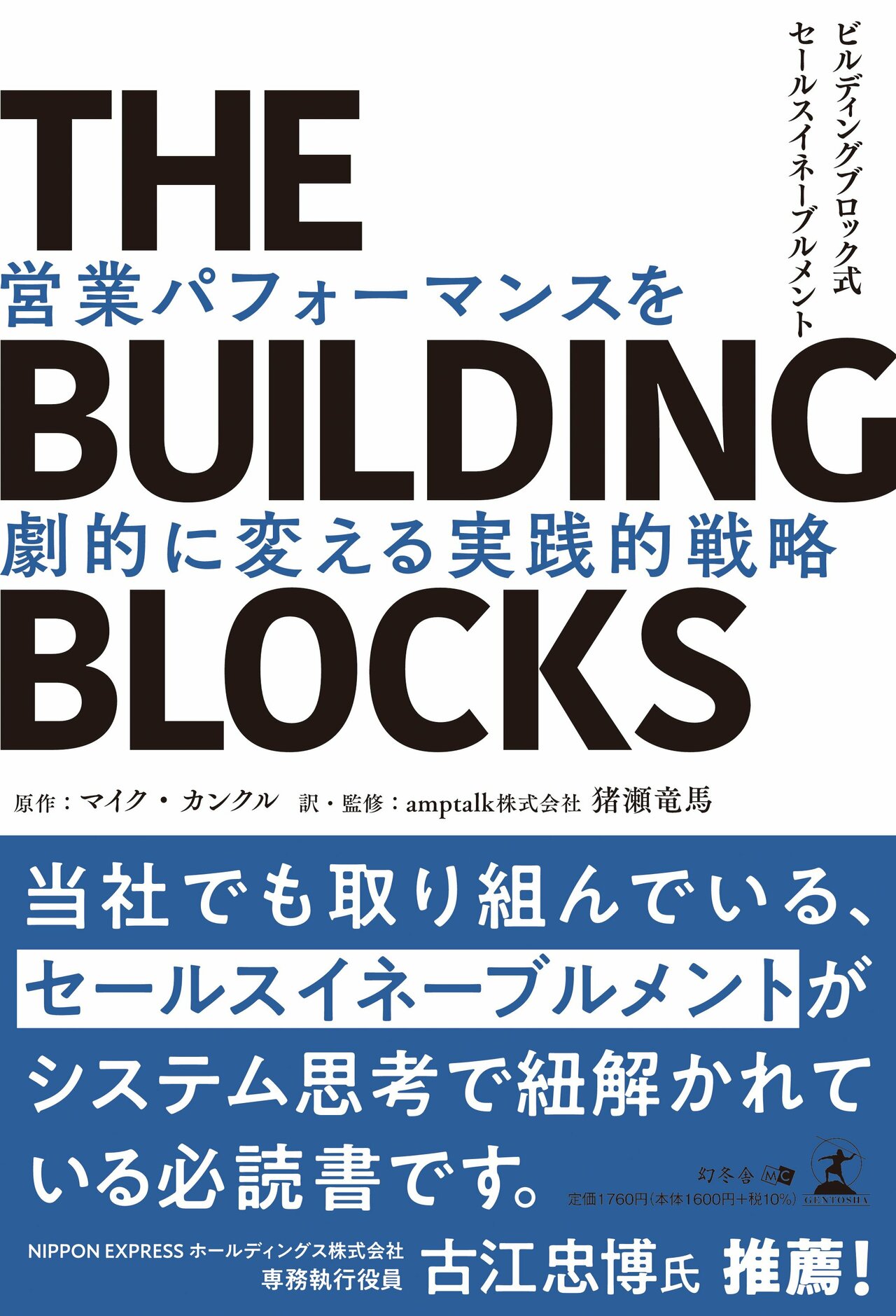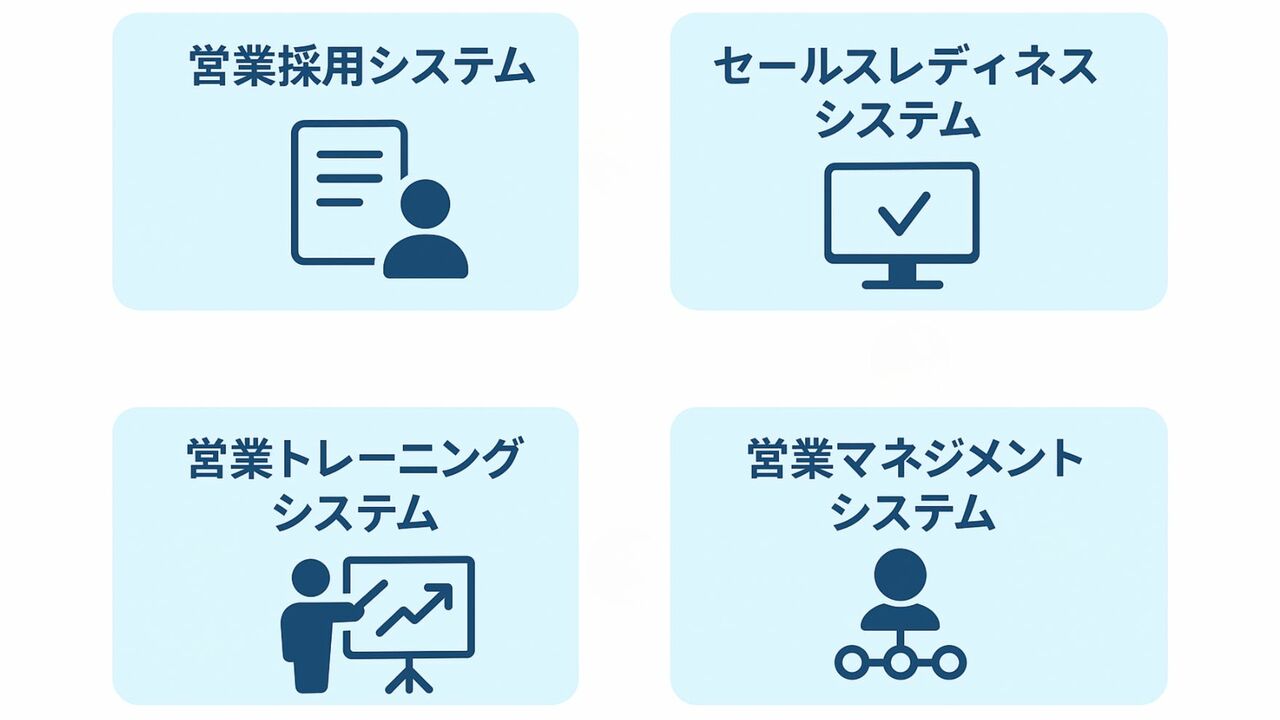システム思考とは
システム思考に関する多くの書籍の著者であり、ペガサス・コミュニケーションズとMIT組織学習センターの共同設立者でもあるダニエル・H・キムは、システム思考についてこのように定義している。
「システムとは、特定の目的を有する複雑かつ統合された全体を形成する、相互作用性、相互関連性、または相互依存性を持つ部分からなる集団である【訳注:『Introduction to Systems Thinking(システム思考の紹介)(未邦訳)』】」
キムはこう語ってもいる。「覚えておくべきなのは、あらゆる部分になんらかの相互関連性と相互依存性があるということだ。こうした相互依存性がないのであれば、私たちはシステムではなく一部分の集合でしかない【訳注:前掲書に同じ】」
別の方法で考えてみよう。たとえば自動車には相互連携するさまざまなシステムが搭載されているから、なめらかに走行できる。主要なシステムとしてはエンジン、燃料システム、排気システム、冷却システム、潤滑システム、電気システム、トランスミッション、シャーシが挙げられる。さらに、シャーシにはホイールとタイヤ、ブレーキ、懸架装置、車体が含まれている。
駆動系や電気システム(スターター、バッテリー、オルタネーターなど)に問題があったり、複数のエンジンが回転しなかったり(燃料システムの問題)すると、車はうまく走れない。
人間の身体もシステムである。呼吸器系、心臓血管系、肺系統、骨格系、消化器系などの各システムがそれぞれ役目を果たし、問題なく機能する健康な身体を形作っている。
組織も同じだ。
政治環境、社会経済的な状況、マイクロ経済またはマクロ経済的な要素など組織外に存在するシステムもあれば、組織内に存在するシステムもある。本書では内部のシステムに焦点を当てて作動部分を解明し、それぞれが健全であるだけでなく、うまく連携していることを確認する。