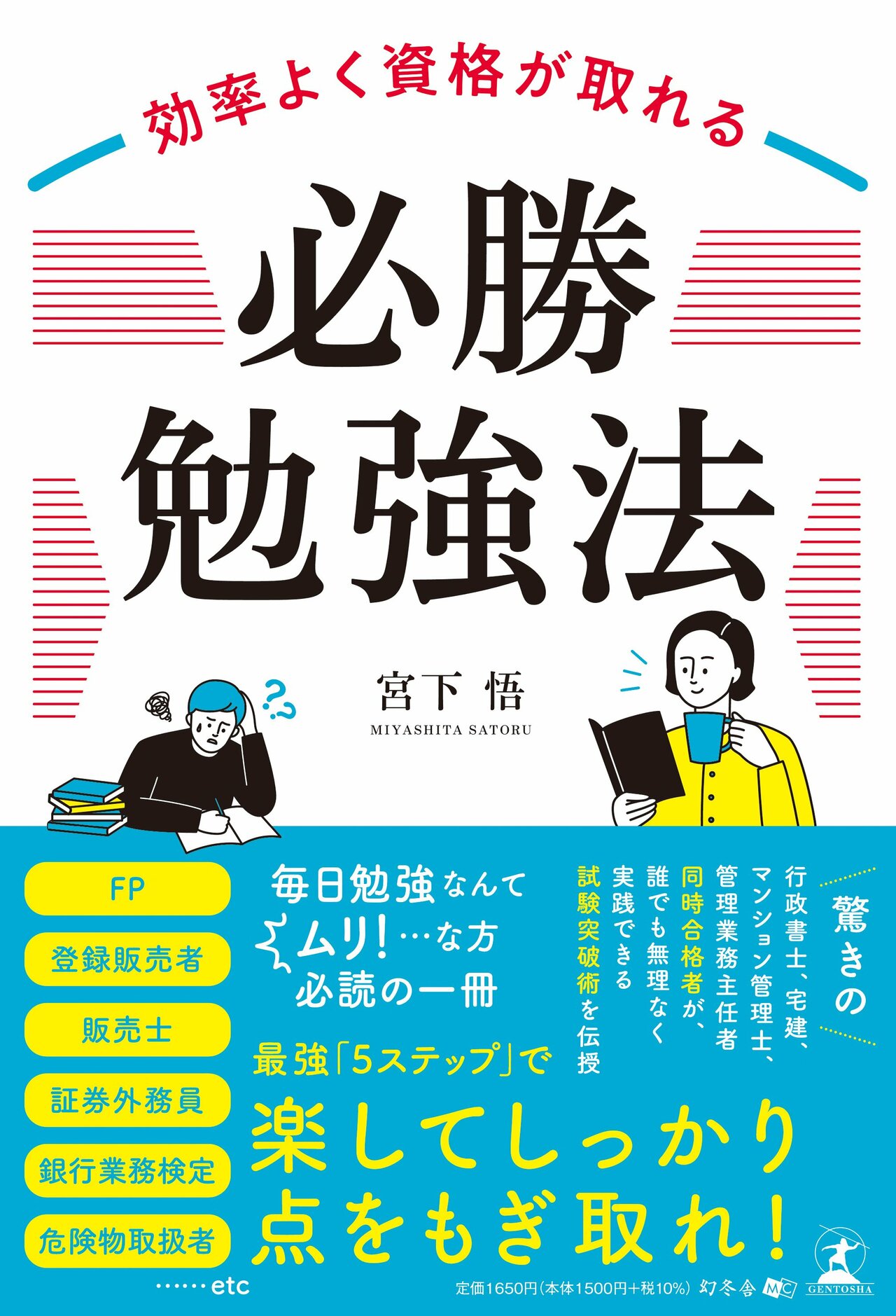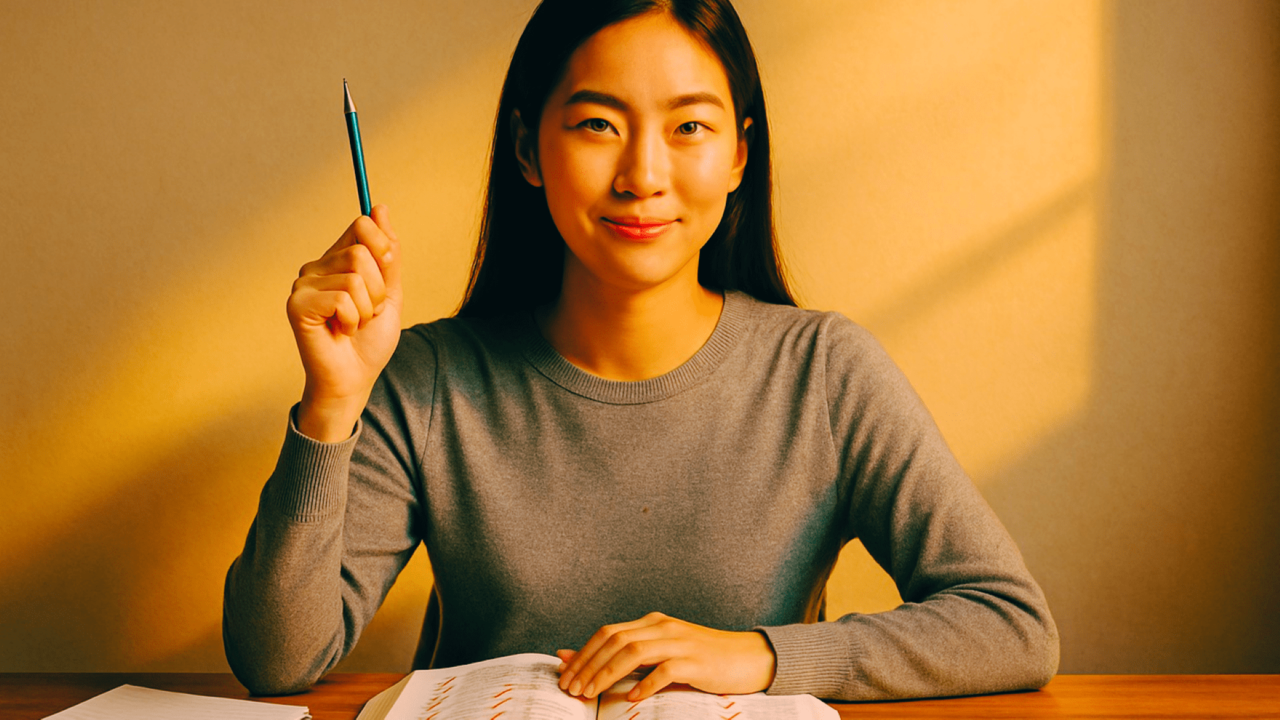確かにテキストの内容が問題のベースにあるだろう。しかし、残念ながらテキストのみを繰り返し読んだところで「合格力」は身につかない。基本的には「過去問を解く」ことを通じて知識を定着させていくほうが、より問題意識を持って取り組める。
また、過去問を通じて「問題に慣れる」という面も見逃せない。本番の試験にいちばん近い形式の問題は、なんといっても過去問である。
また、③については、過去問の問題数を把握することにより、「勉強量の『見える化』」ができる。「勉強量が見えてしまうと、かえってげんなりする」という声もありそうだが、効率的に勉強するには、問題数や勉強量を事前に把握しておくことが大切である。
例えば、宅地建物取引士試験は一回の試験で五〇問、五年分は二五〇問になる。また四肢択一式のため、問題の選択肢の数としては、一〇〇〇ということになる。
そして「『合格力』をつけるには、まずは、一〇〇〇の選択肢を勉強すればよい」という見立てができ、漠然と勉強するよりも目標が具体的になる。「一〇〇〇」となると数としては膨大であり、これを五回も解くなんて、と思われるだろう。だが、後述する解き方をしていけば、想像以上に負担は軽くなると断言する。
そして④については、「結論として、勉強は過去問を拠りどころにせざるを得ない」という消極的な(?)理由である。予想問題集や模擬試験で経験を重ねる、というのも勉強法の一つであろう。だが、これらに取り組むのみで過去問には手をつけない、というのでは勉強の効率上、かなり問題がある。
予想問題は、あくまでも「予想」の範疇を超えない、というのも理由の一つである。だが、それ以上に大きな理由として、過去問を繰り返し解くことで、「合格力」を身につけるという方法が、効率よく学習するためのいちばんの方法、ということである。
高校・大学受験においても、大学共通テストや各高校・大学ごとに「傾向と対策」というものがある。資格試験においても、やはり「傾向と対策」はあり、その「傾向」が過去問に反映されている、と言っても過言ではない。
ただし、試験内容に大幅に変更があった場合(例えば、行政書士試験はかつて、労働法、税法、戸籍法、住民基本台帳法等、幅広い試験範囲であったが、現在は憲法、行政法、民法、会社法(商法)の比重が極めて高い)は、最新の試験要項に沿って増える科目に重点を置いて勉強する、というような工夫が必要であろう。
では、「効率的な過去問の解き方」をお伝えする前に、実際にどのような過去問やテキストを選べばよいかを、次章で書いていきたい。
次回更新は8月23日(土)、8時の予定です。
👉『効率よく資格が取れる「必勝勉強法」』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...