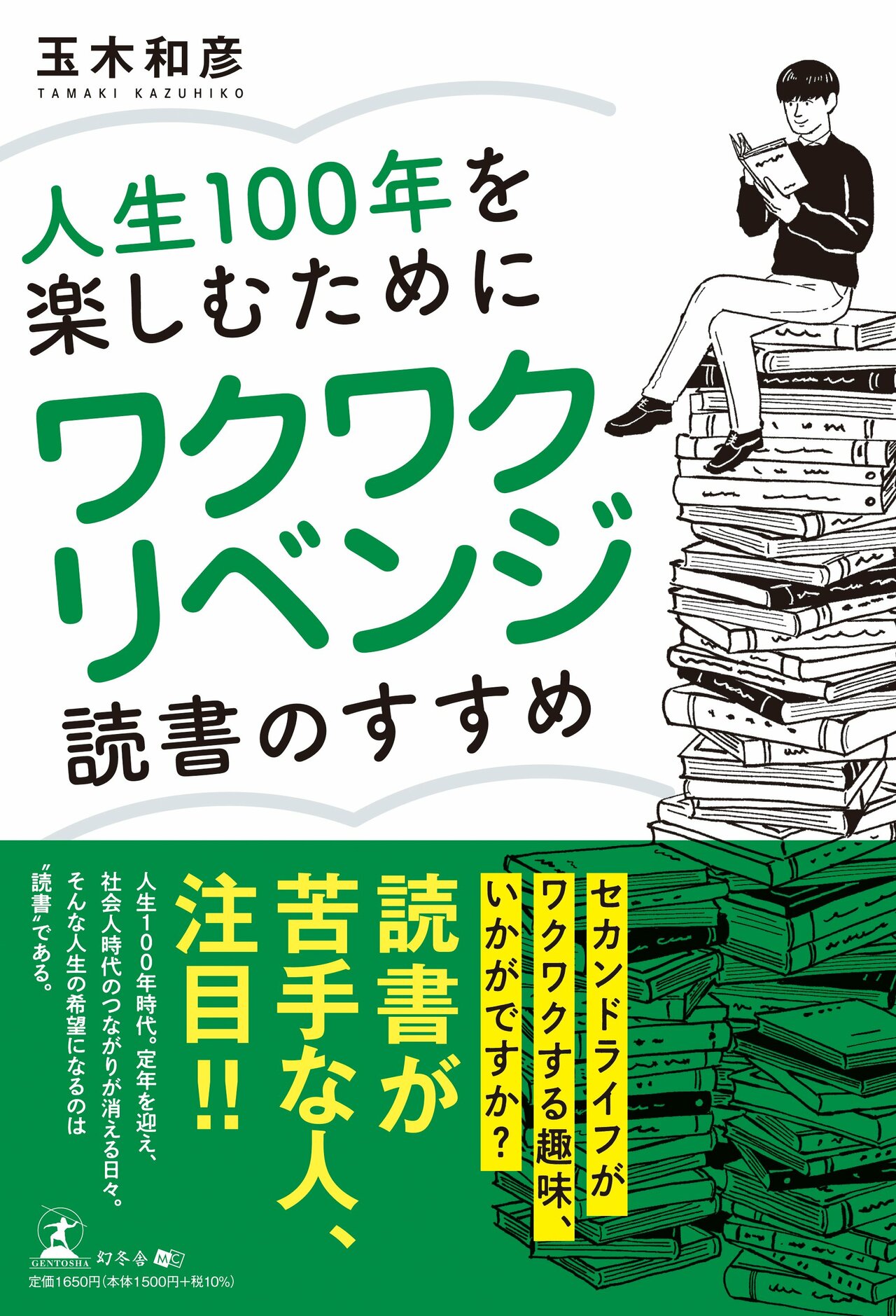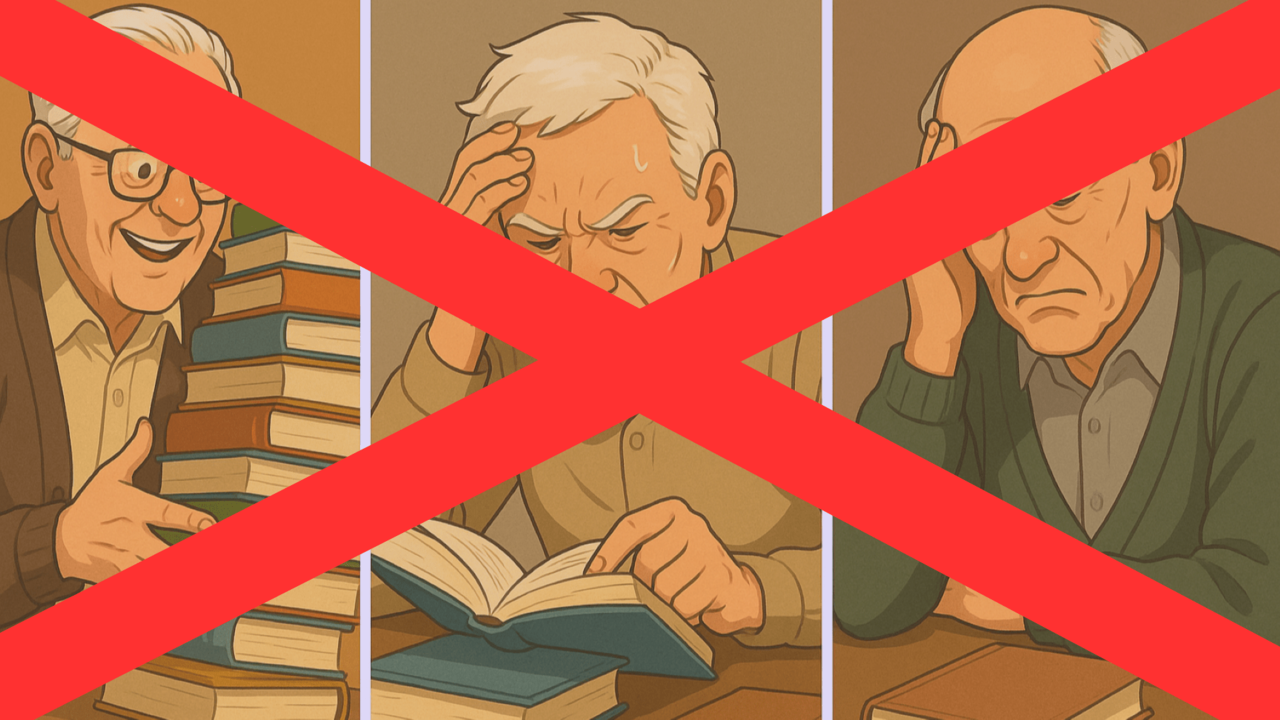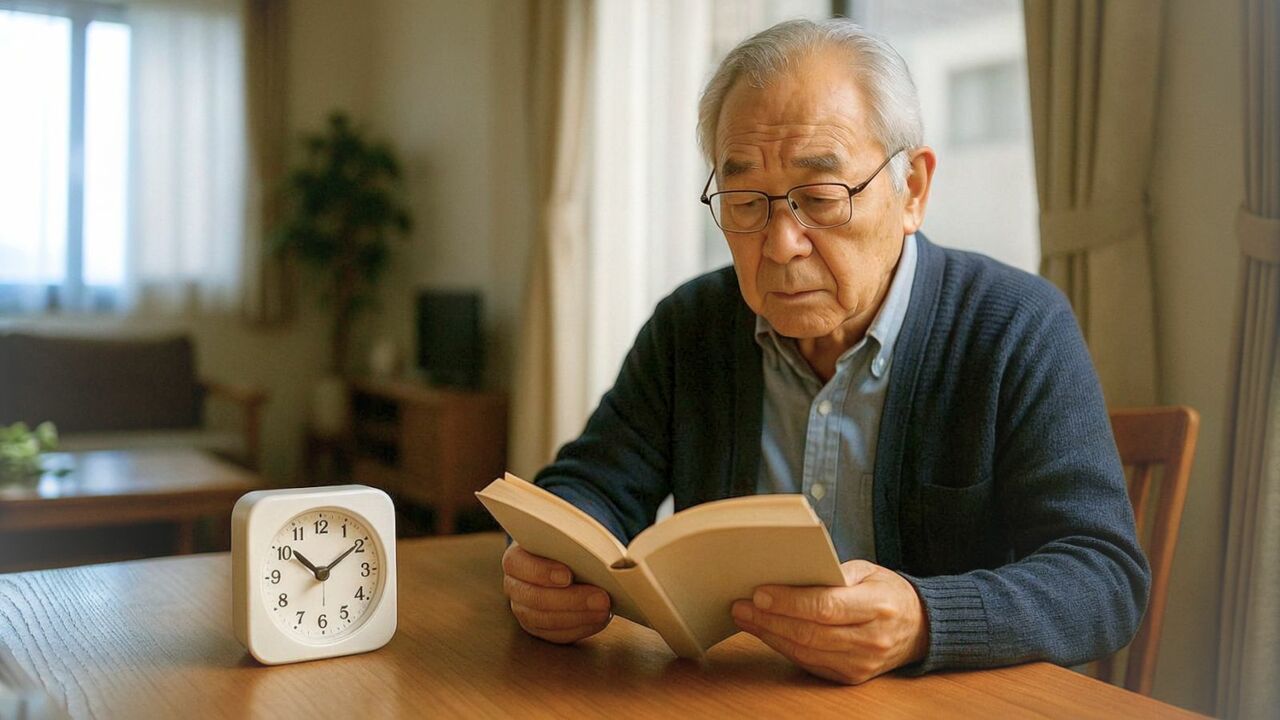簡単なのはネットやSNS、解説本を活用することである。いわゆる名作といわれる作品はだいたいの背景や内容はオンライン百科事典などに記されている。あるいは、書籍紹介サイトや書評案内の専門誌、解説本などで、識者や作品を読んだことのある人の感想や評価を確認することができる。
そこでは、作品を読むにあたってのいろいろなポイントを理解することができ、とても参考になる。
その他にも見落とされがちなのは、書籍(文庫本の場合)の裏表紙にあるいわゆる「裏コメント」や「帯POP」。それぞれ正式名称はわからないが、これらには、出版社・編集部としてその本のアピールしたいポイントが書かれている。
特に裏コメントはわずか200字ほどだが、その本のエッセンスが凝縮している。見どころが書かれていると言っても間違いない。私も「本ぶら(本のウインドーショッピング)」をする時には必ず目次と裏コメントを見るようにしている。極端に言えば、それだけでその本を読んだ気にもなるし、場合によってはもっと深く読んでみたいと感じることもある。
聞いた話では、裏コメントは出版社の中でも「この道○十年」というベテランの方が、担当されていたり後進育成として実地指導をされていることが多いらしい。そう考えると、裏コメントはその本の顔であると同時に、その会社(出版社)の姿勢を見ることができるとも言える。
同様に「帯POP」。書籍の下部にかけられている案内POPである。その本のキャッチフレーズや、セールスポイントが書かれている。ここを見るだけでも楽しい。編集者の方のセンスを確認することができる。
以上、「何を読んだらいいかわからない」という方向けのポイントを記載したが、具体的な作品を例にとって確認してみよう。
例えば、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』(新潮社 1978年)。
この作品を例に、読み出し前のネタバレのコンテンツについて具体的に記載する。
本連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。
👉『人生100年を楽しむために ワクワクリベンジ読書のすすめ』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...