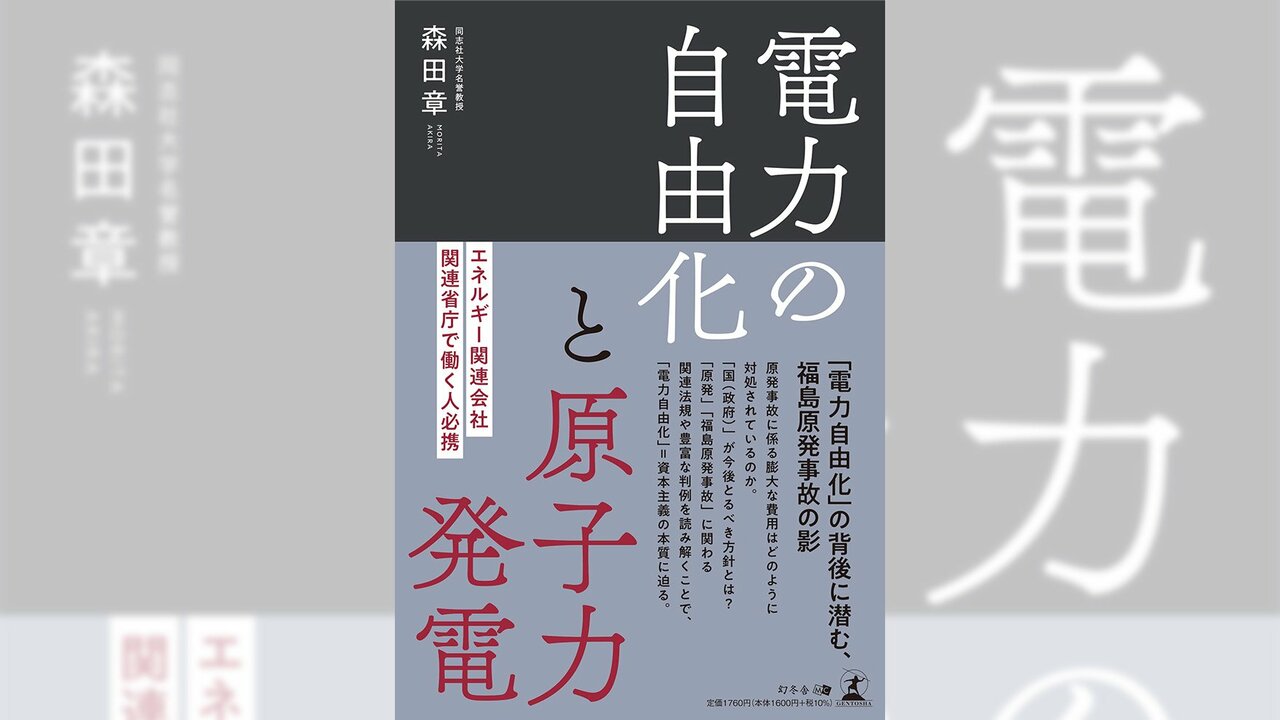②福島原発事故に対する政府の「援助」の実際
「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」(平成23年5月13日原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合決定)によると、
「政府として、第一に、迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置、第二に、東京電力福島原子力発電所の状態の安定化及び事故処理に関係する事業者等への悪影響の回避、そして第三に、国民生活に不可欠な電力の安定供給、という三つを確保しなければならない。
このため、政府は、これまで政府と原子力事業者が共同して原子力政策を推進してきた社会的責務を認識しつつ、原賠法の枠組みの下で、国民負担の極小化を図ることを基本として東京電力に対する支援を行うものとする。
政府は、今回の事態を踏まえ、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる枠組みを設けることとし、東京電力以外の原子力事業者にも参加を求めることとする」という。
具体的には、機構を設置し、機構が原子力事業者に対し援助(資金の交付、資本充実等)を行い、原子力事業者を債務超過にさせない、とする。政府も、交付国債の交付、政府保証の付与等を行うというものであった。
このスキームによれば、実際には東京電力の負うべき無限責任に対して政府が援助し続けることになるが、実質上は原子力事業者の無限責任の解放は明言しないことから、東京電力の経営基盤は危ういままである。
このことに関しては、前述の竹内教授が指摘されたことであるが、原子力事業者が負うべき「万一の事故の場合の予測しえない責任を予測可能なものに転換すること」が放置されている。
さらにいえば、破綻再生のスキームではないはずであるのに、上記対応チームの「具体的な支援の枠組み」においては、「原子力事業者を債務超過にさせない」とか、「政府は、援助を行うに先立って原子力事業者からの申請を受け、必要な援助の内容、経営合理化等を判断し、一定期間、原子力事業者の経営合理化等について監督(認可等)をする」などが明らかにされ、あたかも金融機関が破綻した際に行われた管理型の再生スキームのようなトーンとなっている。