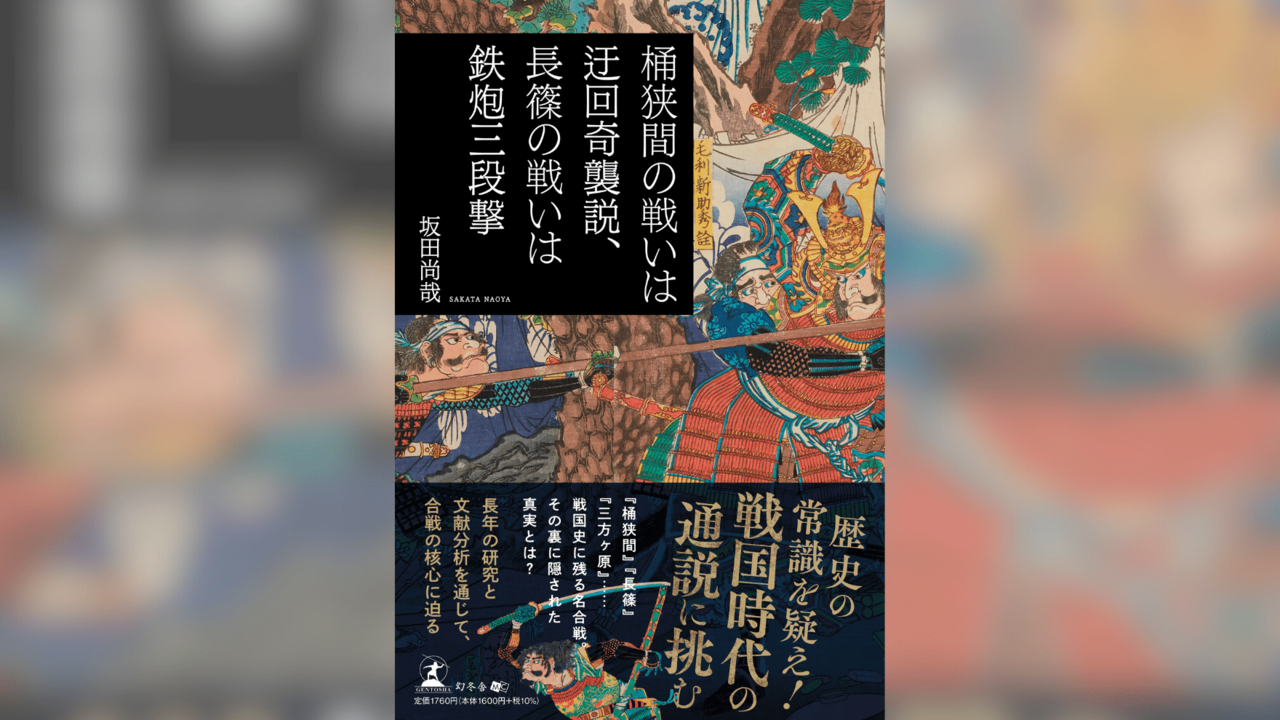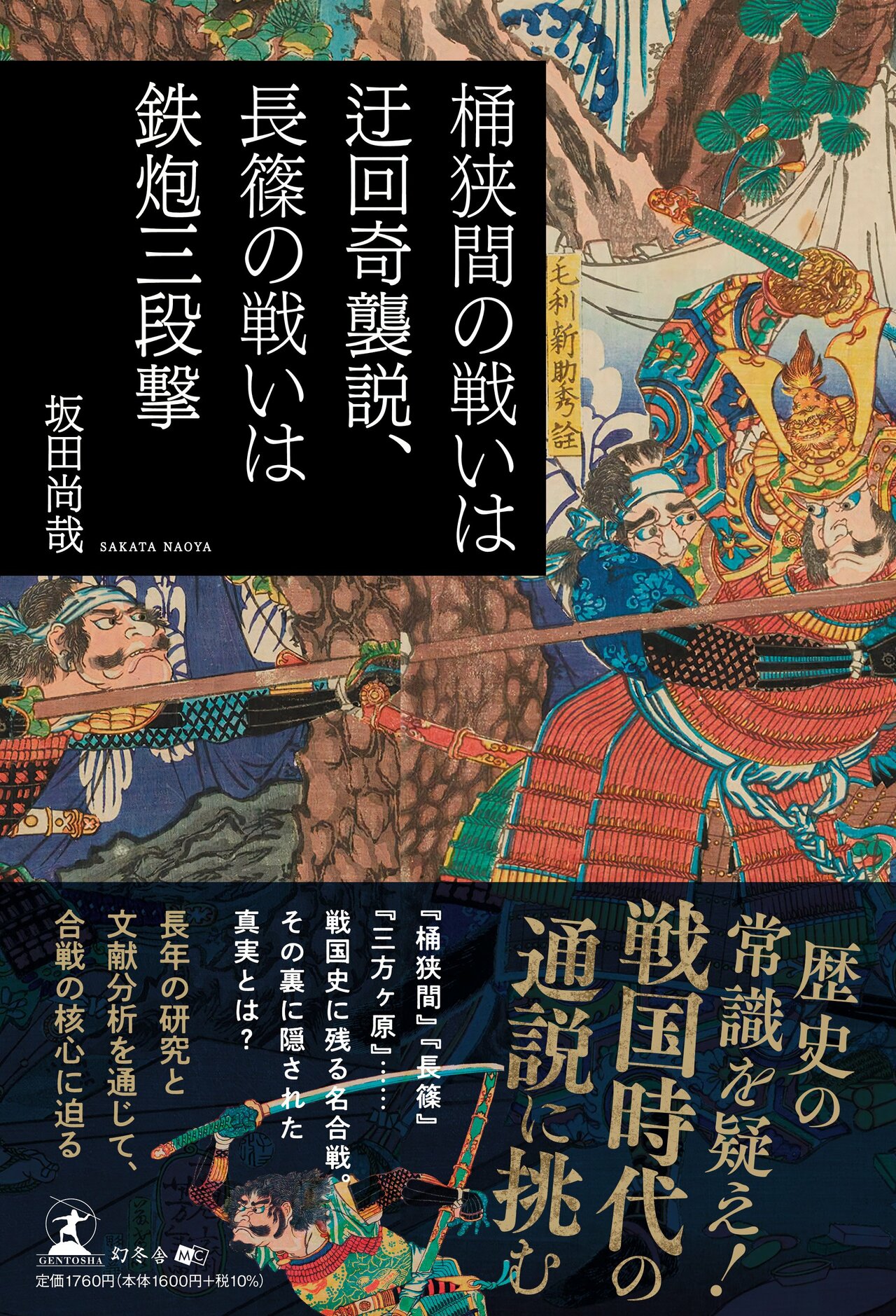【前回記事を読む】その歴史、本当に正しい? 信長はなぜ勝てたのか…織田信長の桶狭間の戦いを「信長公記」から徹底再考!
第一部 桶狭間の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い
一 桶狭間の戦い ~「正面攻撃説」から「迂回奇襲説」へ回帰する~
今川軍の進軍経路の考察
織田軍の進軍経路を考察する前に、少しだけ今川軍の進軍経路について考察してみたい。近年の大河ドラマでの今川軍の進軍経路の解釈であるが、「麒麟がくる」では義元が「大高城に向かう」と宣言して沓掛城を出発する姿が描かれ、「どうする家康」では大高城に入城した松平元康が後着するはずの義元を待つ姿が描かれていた。
いずれも当日の朝に沓掛城を出た今川本陣の向かった先は大高方面だったという解釈であった。どうして大高方面に向かったと解釈したのかNHKに問い合わせをしたところ、以下のような回答をいただいた。
〈『信長公記』だけでは、今川本軍が具体的にどこに向かったか記されていませんが、ほぼ同時期に作成された『三河物語』では明確に今川本軍は大高城にむかったことが記されています。ドラマでは、『三河物語』の記述を重視し、「大高城にむかった」としました〉
まず、『信長公記』には記されていないというのは誤りというべきで、「午剋戌亥に向て人数を備」とあるのは鳴海方面に向かったと解釈できなくもない記述である。記されていないという見解は見落とししたということであろう。
『三河物語』に明確に記されているというのは「義元ハ、地リウ寄段々に押て大高え行」という一文のことであろう。『信長公記』のいう義元は沓掛城を出て昼頃北西に向けて陣を構えていたのに対して、『三河物語』のいう義元は池鯉鮒から大高に向かっているので出発場所も行先場所も異なる。これを同一人物とするのはいくらなんでも無理があるので、検証を要するところである。
当日の今川本陣が沓掛城を出発したか池鯉鮒を出発したかは解らない部分がある。『信長公記』には、前夜に「今川義元沓懸へ参陣」とあるので、常識的には義元が沓掛城に入城したと解釈すべきではあるが、今川軍先鋒部隊の一部が着陣したという意味である可能性を無視できないからである。
従って、今川本陣の当日の出発地と向かった先の組み合わせは以下のとおりとなる。
池鯉鮒を出発→鳴海方面に向かった……有り得る。
沓掛城を出発→大高方面に向かった……有り得ない。
沓掛城を出発→鳴海方面に向かった……有り得る。『信長公記』のとおり
池鯉鮒を出発→大高方面に向かった……有り得る。『三河物語』のとおり