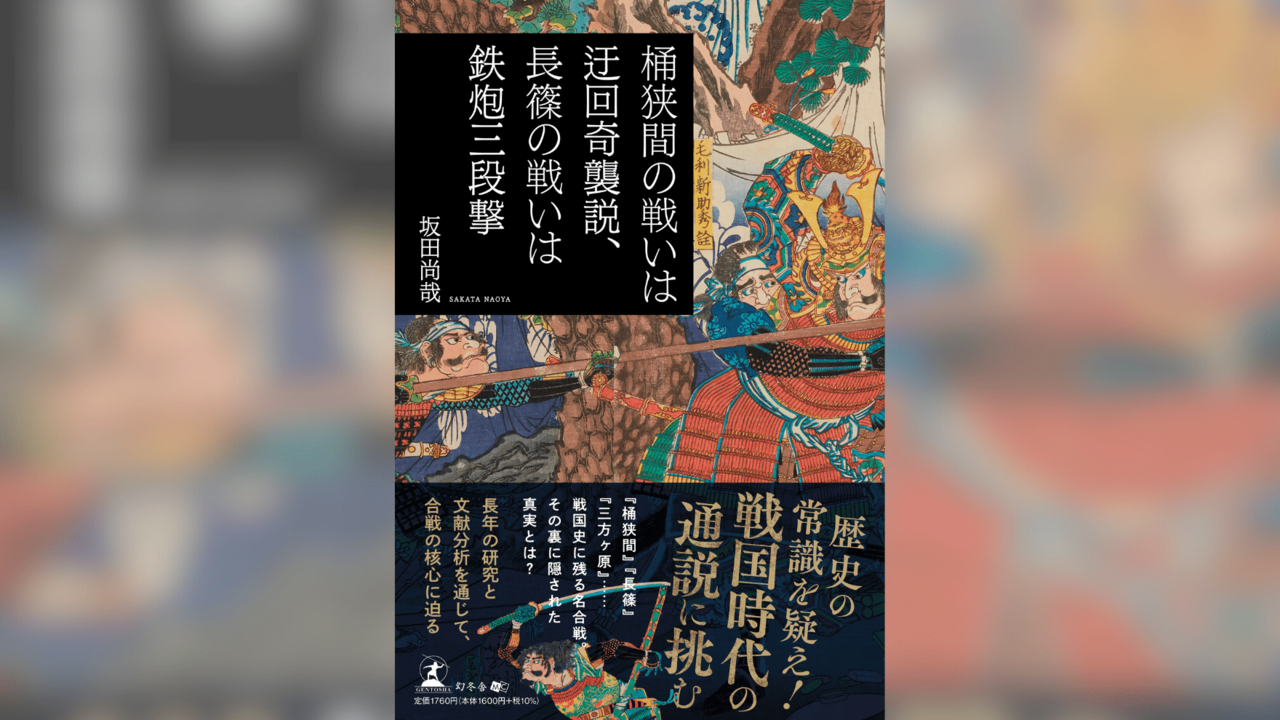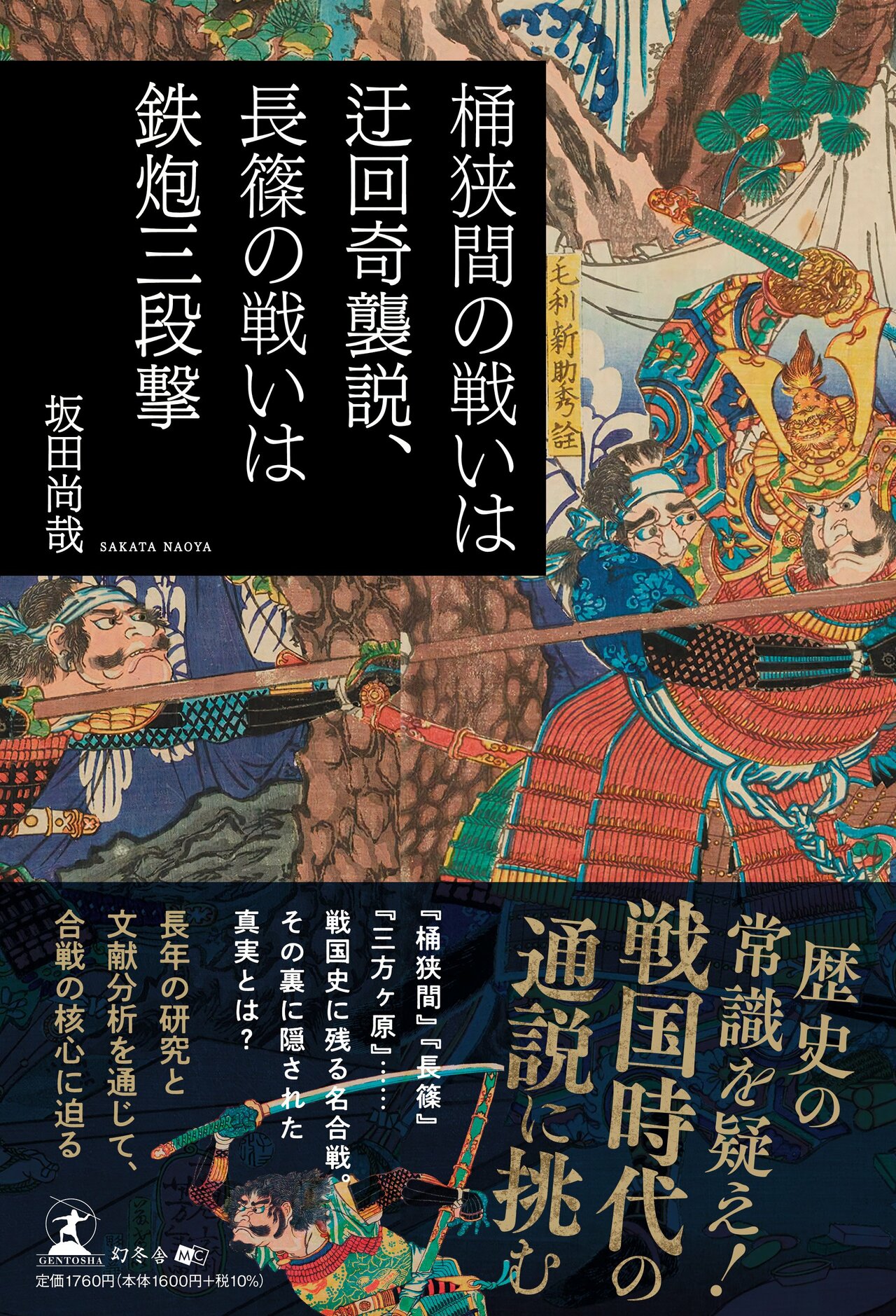第一部 桶狭間の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い
一 桶狭間の戦い ~「正面攻撃説」から「迂回奇襲説」へ回帰する~
桶狭間の戦いは、河越夜戦・厳島海戦とともに日本三大奇襲戦のひとつに数えられる戦国時代を代表する合戦であるにも拘わらず、勝利した織田軍と敗北した今川軍のどちらの進軍経路についても様々な説が論議されていながら、これまでに定説といえるものがないという不思議な合戦である。
最近の研究が『信長公記』を最も良質な史料と位置付けて論考するという姿勢であることに、私は異論がない。
『信長公記』を引用し注釈を加える形で提唱された「正面攻撃説」が現在それなりに評価を得て新しい通説になりつつあることは承知している。
しかし、どうしても「正面攻撃説」の微細な部分について私は納得できずにいて、どうせなら愚直なまでに徹底的に史料の細部の表現にまでこだわって、拭い切れないでいる疑問は晴らすべきではないかと思う。
『信長公記』の記述を私なりに考察し、さらに『甫庵信長記』『三河物語』『松平記』の記述を傍証に用いることで、織田軍と今川軍の進軍経路をできる限りで納得できる形で表してみたいと思う。
私が最も重視する『信長公記』の中の情報
桶狭間の戦いにおける織田軍と今川軍の進軍経路を解明するために、『信長公記』の記述の中で最も重視すべきと私が思うのは、
今川軍……午剋戌亥に向て人数を備
織田軍……未剋東へ向てかゝり給ふ
であると思う。
結論からいうと、今川軍が北西方向に陣を敷いているところへ、その進行方向よりも左斜めから織田軍が攻め込んだという図になる訳である。
今川軍が戌亥に向かっていたのは午剋(午後0時頃)で織田軍の突撃が行われる二時間前であるから、その間に向きをかえた可能性は否定できないが、織田軍が東へ向かって攻め込んだのは未剋(午後2時頃)のその瞬間のことである。
織田軍による今川本陣への攻撃の最初の場面は、『信長公記』に「黒煙立て懸るを見て、水をまくるが如く後へくはつと崩れたり、弓・鑓・鉄炮・のほり・さし物、算を乱すに異ならす、今川義元の塗輿も捨てくつれ逃けり」と記述されているから、今川勢にとっては突然の出来事であったに違いない。