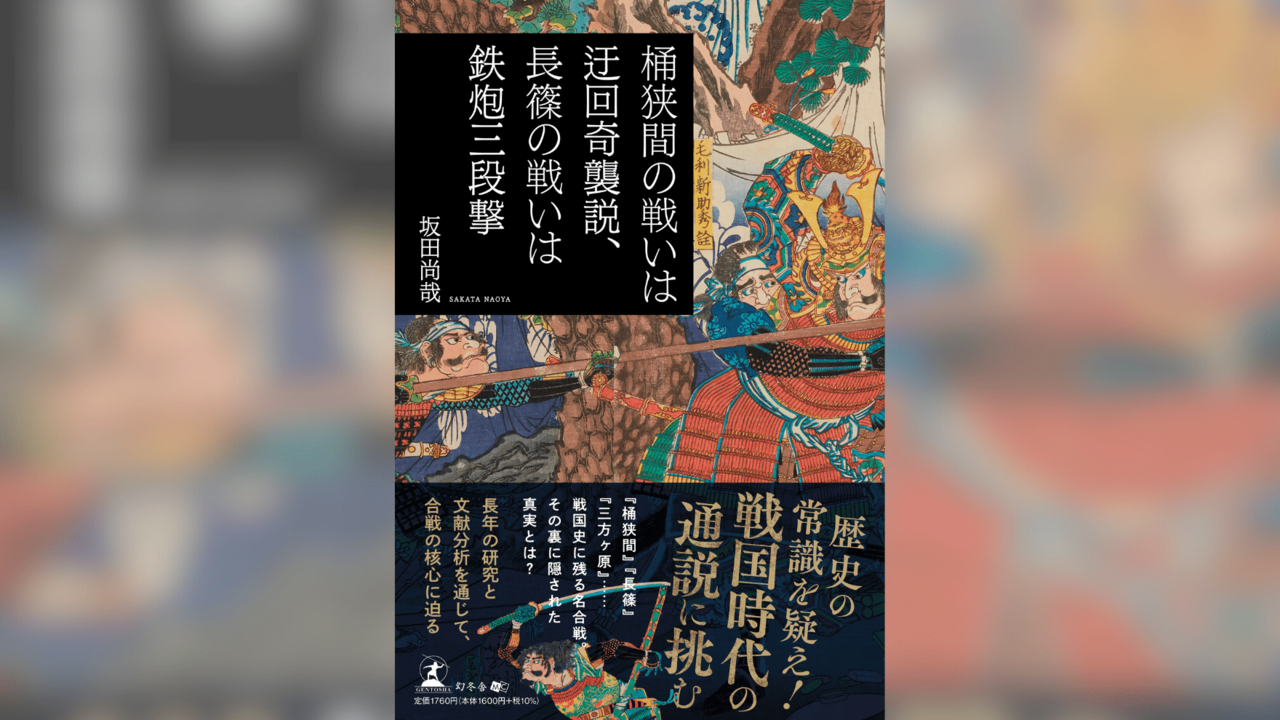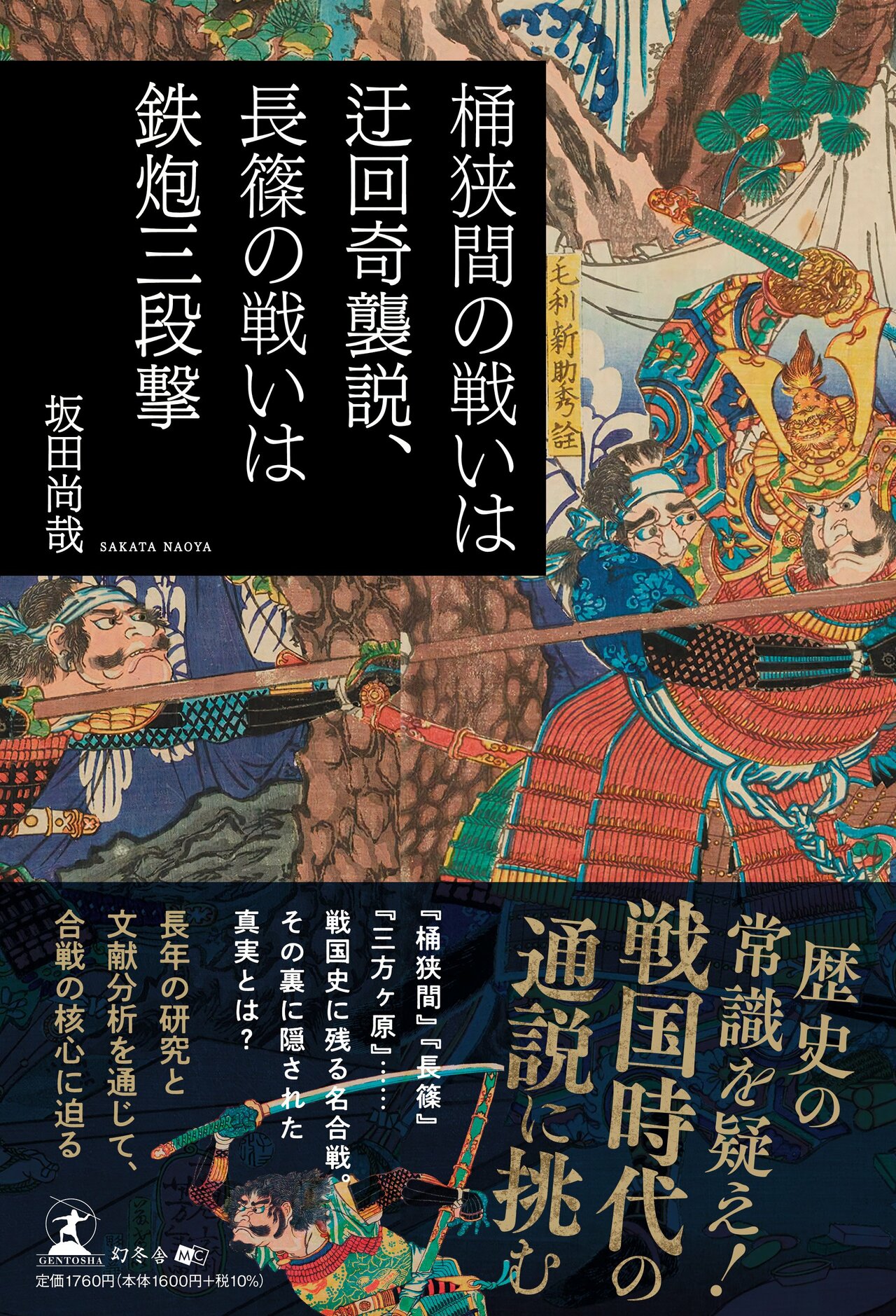【前回記事を読む】「桶狭間の戦いで、今川本陣はどこからどこに向かったのか?」――NHKドラマでは『三河物語』を参考にしたようだが、それは…
第一部 桶狭間の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い
一 桶狭間の戦い ~「正面攻撃説」から「迂回奇襲説」へ回帰する~
善照寺砦から中島砦へ、さらに出撃!
桶狭間の戦いにおける織田軍の進軍は信長が清洲城を出発するところから始まるのだが、その進軍経路の議論の焦点は、信長が善照寺砦に到着して敵勢を目の当たりにした午剋から織田軍が今川軍に攻撃をした未剋まで、午後0時から午後2時までの2時間であるといってよい。
信長の善照寺砦到着の様子は、『信長公記』に「夫より善照寺佐久間居陣の取出へ御出有て、御人数立られ、勢衆揃へされられ、様躰御覧し、御敵今川義元ハ四万五千引率し、おけはざま山に人馬の休息之在」と記述されている。
『信長公記』を著した太田牛一の癖なのであろうか、眺望によりその場で得た情報、戦後の首実検時の証言などにより得た情報、後日談やらさらに後から得た情報など、雑多な情報源のものを時系列に並べて記述しているので解りにくいが、「おけはざま山に人馬の休息之在」は善照寺砦から眺望して得た情報、これに対し「謡を三番うたハせられたる由候」などは後から得た情報と考えられる。義元が信長から姿を認められる至近距離にいたのだというような解釈はしないほうがよいらしい。
信長は善照寺砦から中島砦に移る。この時の様子を『信長公記』には「中島へ御移り候ハんと候つるを、脇ハ深田の足入、一騎打の道也、無勢之様躰敵方よりさたかに相見候、無御勿躰之由、家老之衆御馬之轡之引手に取付候て、声々に申され候へとも、ふり切て中島へ御移り候、此時二千に不足御人数之由申候」とある。
中島砦に移ろうとする信長を家老衆が「敵に丸見えだから」と制止しようとしたこと、その時の軍勢が二千人に足らなかったということである。
そこから『信長公記』の記述は「中島より又御人数被出候、今度者無理にすかり付、止申され候へとも、爰にての御諚には……」に続いている。信長は中島砦からさらに出撃したところ、家老衆は無理にすがりついて制止しようとしたというのである。
ところで、近年では「正面攻撃説」が有力とされている。この説を最初に提唱したのは藤本正行氏で、『信長公記』を主たる論拠にして、「信長に隠密に行動して義元に奇襲をかけるという意図などなかった」とし、「織田軍は中嶋砦を出て東に進み、東向きに戦ったわけで、堂々たる正面攻撃ということになる」と論じている。
敵前軍に正面攻撃をかけると、
「この前軍が簡単に崩れたので、義元の旗本も退却を始め、追撃中に敵の旗本を捕捉した信長は、ここではじめて義元に狙いをつけ、ついに倒した」という、奇襲の意図をもたない堂々たる正面攻撃だったとする説は、多くの賛同と同時に多くの反論を呼んだ。