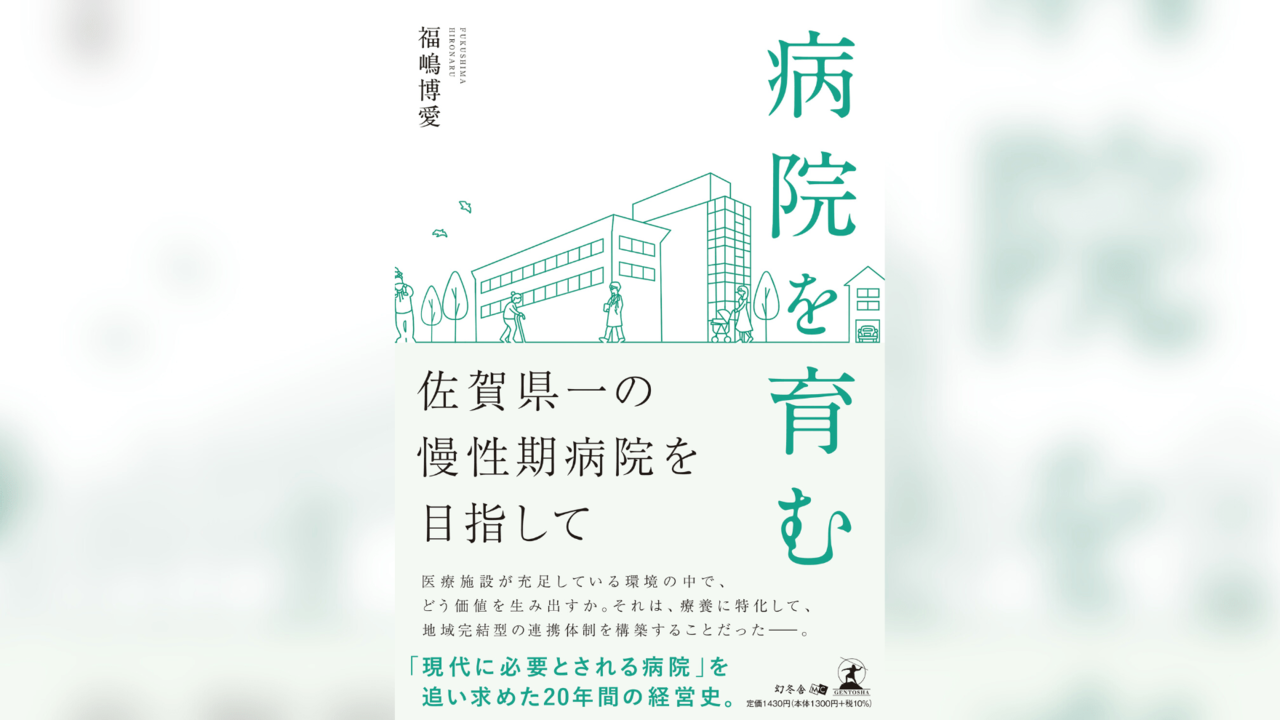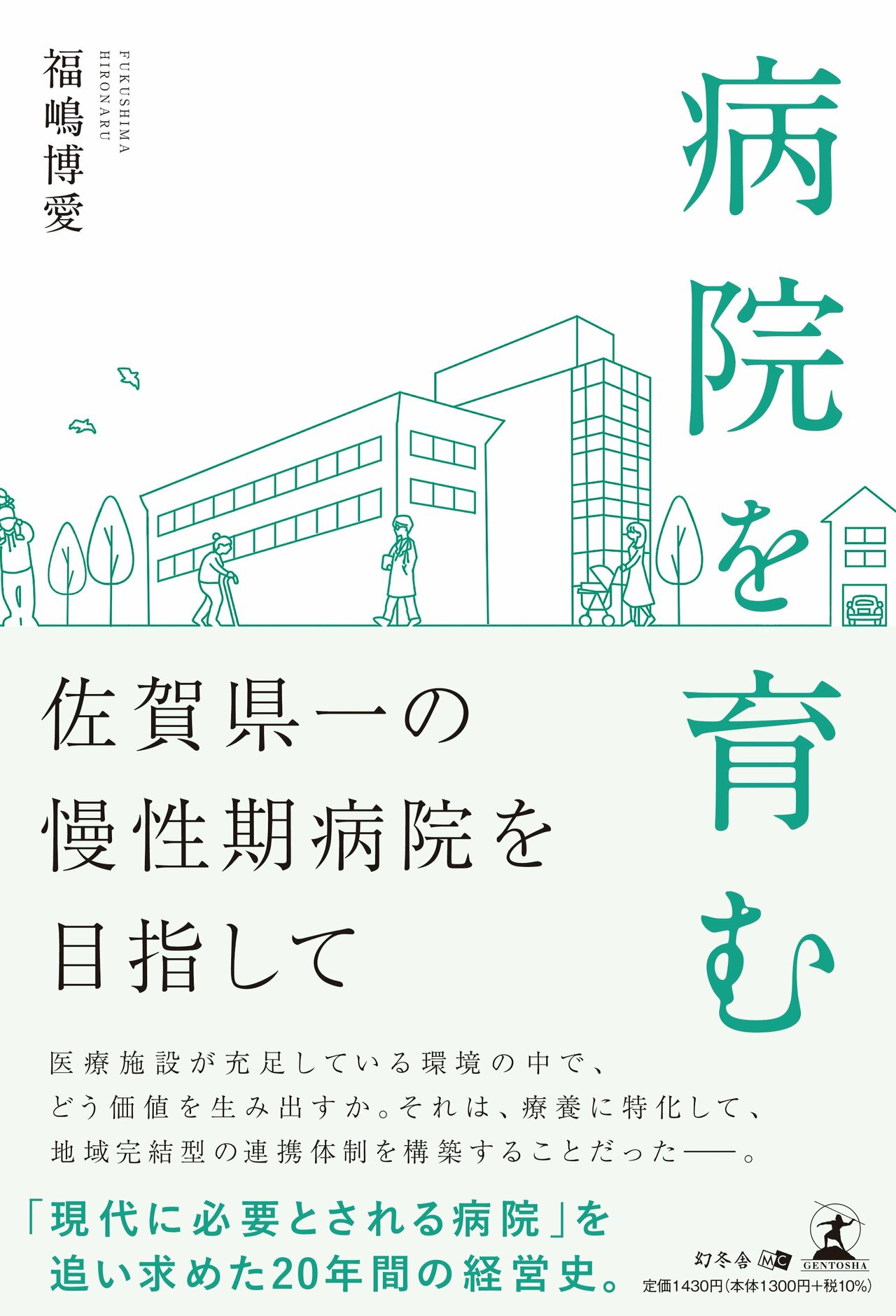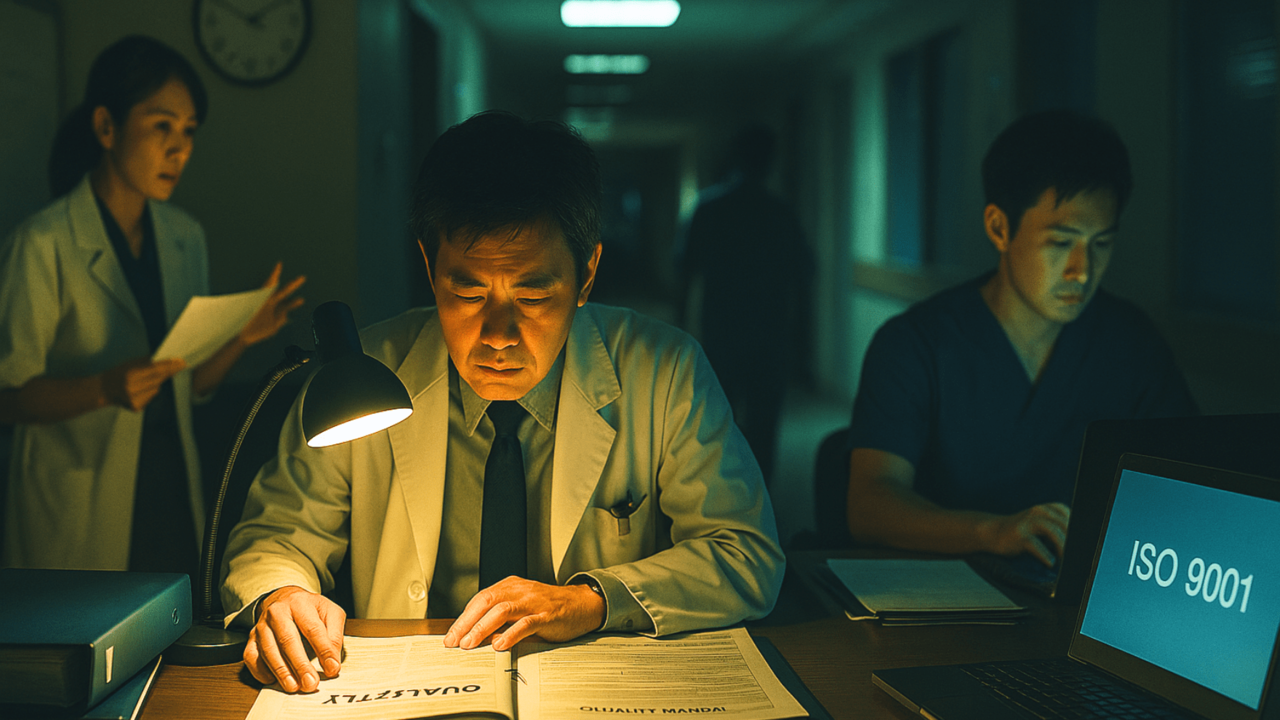【前回記事を読む】服も体も、真っ黒こげで病院に運ばれた私。「あれが奥さんです」と告げられた夫は、私が誰なのか判断がつかなかった
第一章 佐賀県一の病院を目指して
第一節 病院の移転まで
当時は現在と比べると、検査機器の貧弱な時代で進行したがんが多く、効果的な抗がん剤も少なく拡大切除がおこなわれ、術者の技量に委ねられていた「神の手」の時代だった。
恩師もそのお一人だった。何人もの術者の手術中のトラブル対応を見て、予期せぬ事態には、助手は術者を見ている。術者があわてたら皆動揺する。「全ての責任を負い、冷静になり、急がないで着実に対応する。終わらない手術はない」ことを学んだ。
一九八四年、父の入院治療が必要となり、教授のお許しをいただき退局し、妻の実家の病院に入職した。病院は一九三三年に先々代が開業し、一九五九年に医療法人順天堂を設立していた。「順天」の出典は「天の道に従って背かない(易経)」からである。
開業医としての生活が始まった。
当時の社会は一九五五年から一九七三年の高度経済成長期が終わりを迎えていた。
医療界では、一九六一年に国民皆保険制度が実現していた。一九七〇年に、人口の7%が六十五歳の高齢化社会になり、一九七三年には七十歳以上の医療費が無料化され、医療施設の受診率が増加した。シルバーシートが初めて中央線に設置された。
高度成長期に地方から働き盛りの人が都会に吸収され、高齢者が取り残された。高齢者の受け皿である特別養護老人ホーム(特老)、老人保健施設(老健)、訪問看護などが整備されていなかったため、一般病院が「老人施設」の代用となり長期入院者が多く、「社会的入院」と呼ばれていた。有床診療所も増加し、精神病院は二万床から数倍に増えた。
医者が潤った時代だったが長くは続かなかった。
当病院も一九八〇年に新館が完成していたが、一床当たりの面積は狭く、社会的入院に該当する患者さんがかなりのベッドを占めていた。「社会的入院」は止むを得ないことと理解はしていたが外科で育ったため「病院は重症者を診るところになるべき」との思いが強かった。
入職後は理事長(義父)と放射線専門医である妻、常勤医一名と大学病院からの非常勤医師で診療をおこなった。新設医科大学の卒業生がようやく世に出る頃で、慢性的な医師不足の時代であったためほとんど毎日当直し、一、二次救急の初期医療も断らなかった(断れなかったと言った方が適切)。外来、入院診療、往診、手術、学校医、産業医、医師会など多忙な日々を過ごした。