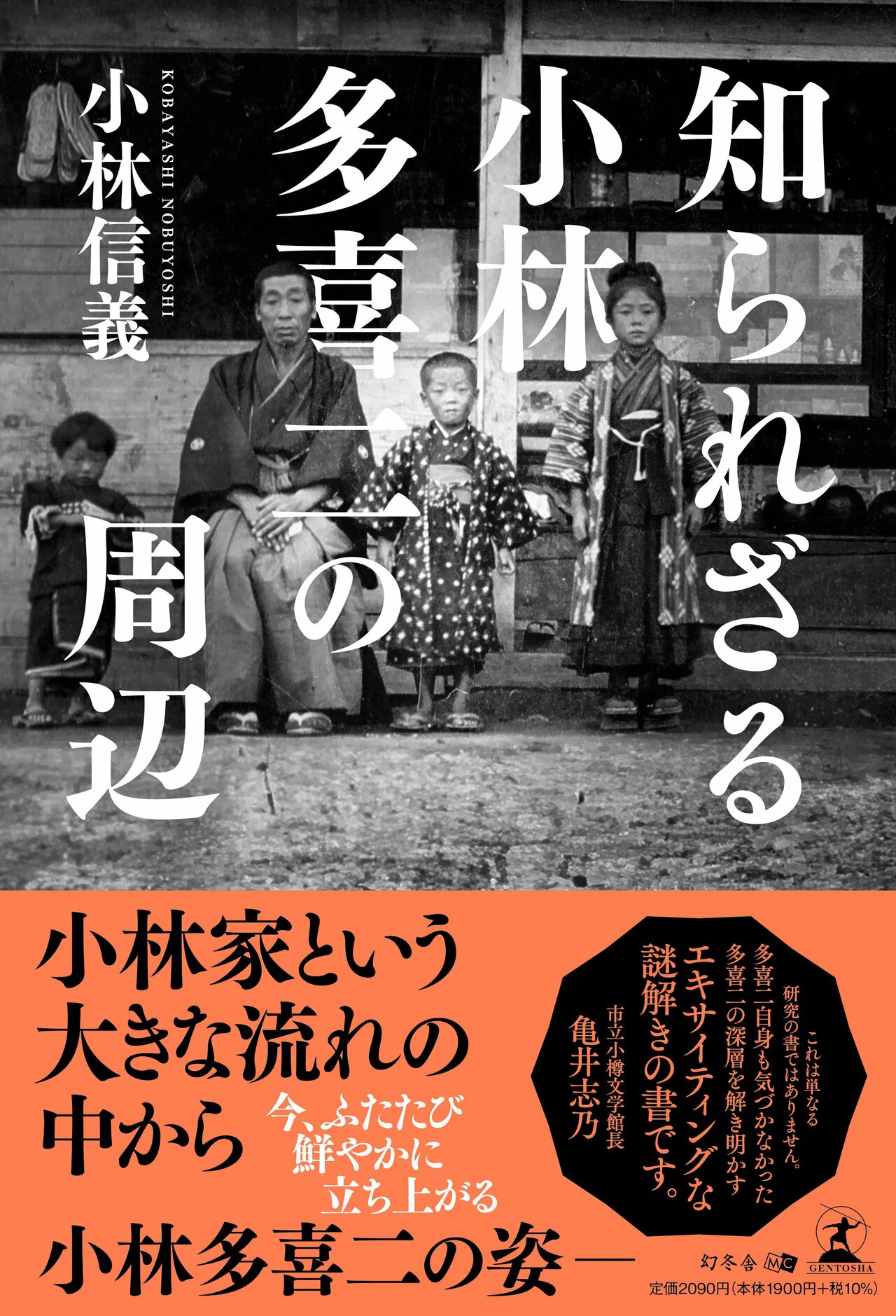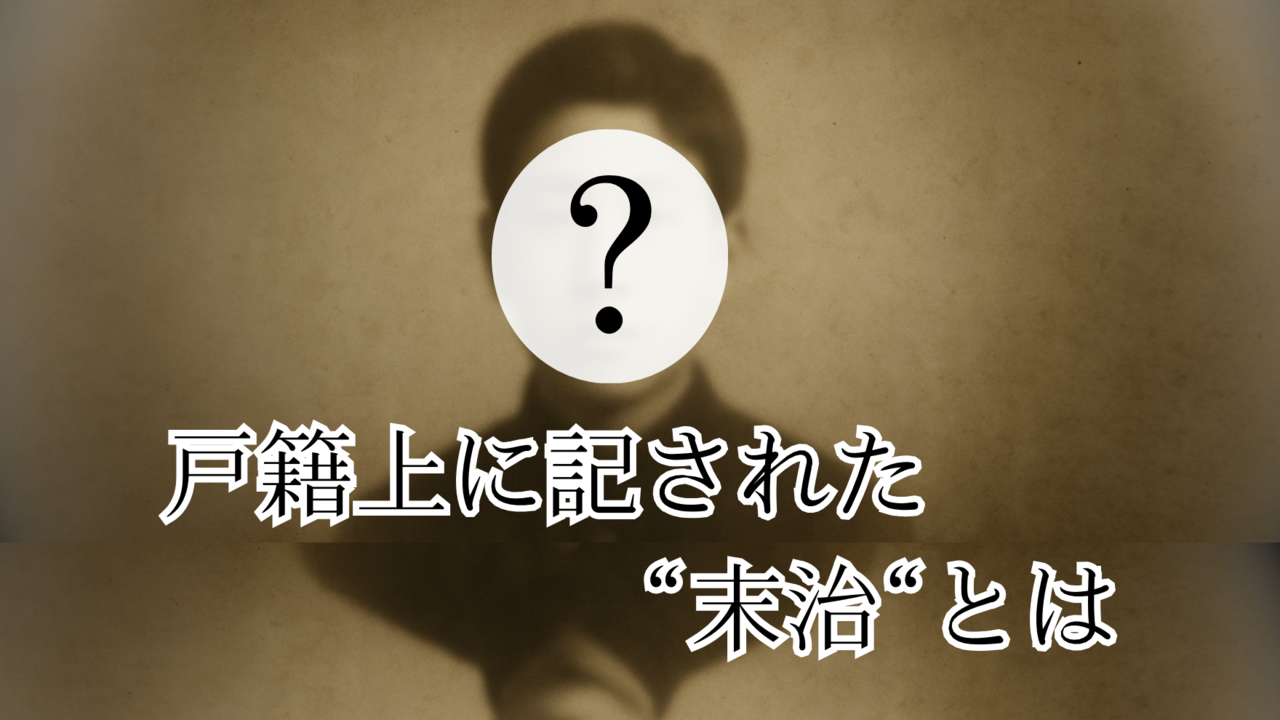慶義の長男幸蔵と2男俊二はクリスチャンになりました。3男吉郎は生後まもなく死亡しています。このことで4男の太郎(私の祖父)が仏事継承者になり、慶義が作らせた仏壇や小林家過去簿が私の実家にありました。
セキの長男多喜郎は11歳で死亡、長女ヤヘは生後1ヶ月半で死亡、5男多志喜は生後4ヶ月半で死亡しています。セキが言う夭死に相当するのは、普通に考えるとこの3人でしょう。しかしながら、これまで知られていなかった謎がふたつあります。
2・A 慈幻善孩兒
「母の語る小林多喜二1」の原稿を見い出して出版した荻野富士夫氏は注記の中で、多喜二の姉チマが書いた「小林家親族の氏名・戒名・没年等」という資料を指摘しています。そこには明治23年(1890)4月30日に亡くなった男児が書かれているそうです。
チマは新暦世代なので新暦の日付と考えていいでしょう。私は平成23年(2011)2月に小樽で開催された多喜二祭の時にノーマ・フィールド氏に会ったことがあります。
その時に「多喜二には多喜郎以外に兄がいたらしい」という話を聞きました。その時は何のことか分かりませんでした。
しかし5ヶ月後に出版された「母の語る小林多喜二1」の注記を読んで理解できました。ノーマ・フィールド氏は荻野氏からすでに、チマが書いた資料のことを聞いていたようです。
明治23年(1890)4月30日に亡くなった男児が存在したということは、満13歳3ヶ月で嫁入りしたセキが満16歳8ヶ月の時に最初の出産をしたことになります。
そうであればその後に生まれた多喜郎は2男、多喜二は3男ということになります。しかしながらこの児は戸籍に載っていません。
チマが書き残した児の存在により、以前からあった私の疑問が解けました。小林家過去簿3の中に1人だけ、誰だか分からない戒名があったのです。
それは慈幻善孩兒(がいじ)という明治年(1890)3月12日に亡くなった児でした(図2左)。戒名からして男児と思われます。旧暦から新暦に切り替わったのは明治 6(1873)でした。
しかしながら小林家過去簿は明治40年頃まで没年月日が旧暦に変換して書かれていることが分かっていました。