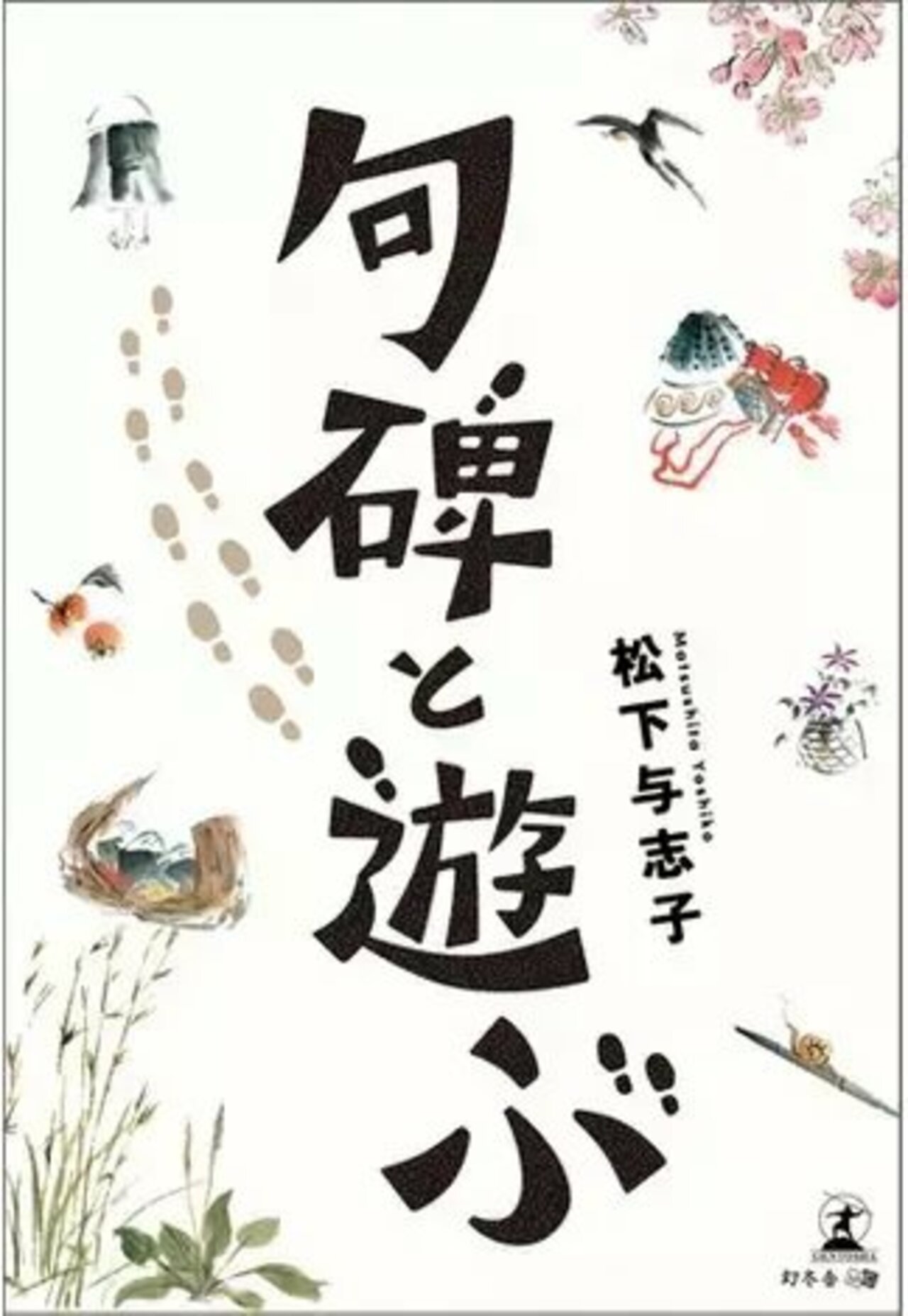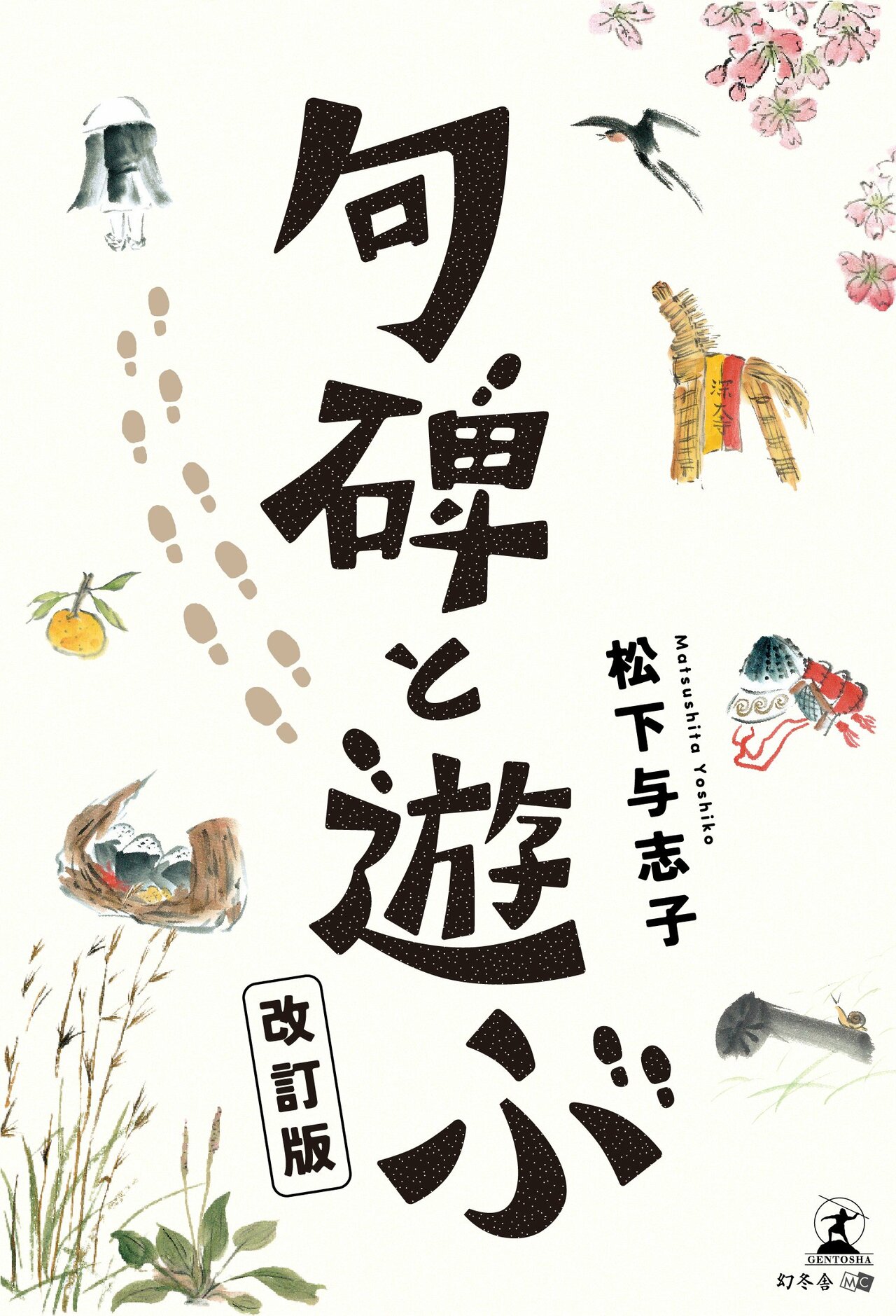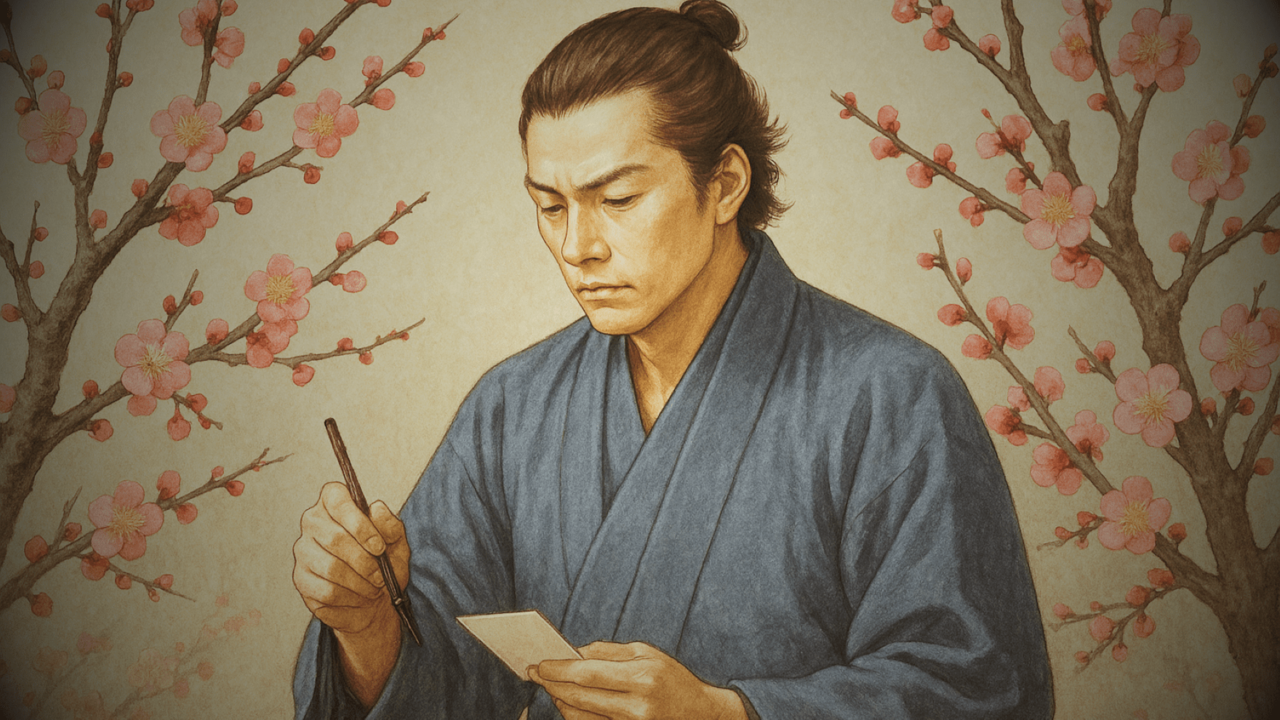子規庵のガラス窓

日本でガラス窓やガラスの引き戸が作られ始めたのは明治に入ってからだという。
当時は吹きガラスの方法で円筒形のガラスを作り、それを縦に切り開き板ガラスにしていたと聞く。
ようやく板ガラスが量産されるようになったのは明治40年代のことで、それでも当時かなり高価なので財力のある家でないと購入はなかなか出来なかったらしい。一般家庭にガラス窓が使われ出したのは昭和に入ってからということだ。
正岡子規が明治27年、終焉の地台東区根岸に移り住んだ頃、その住居には当初ガラスは使用されていなかったのだ。
子規庵を訪ねた折のことは以前「潮音」に書かせてもらったが、庭に面して作られた大きな引き戸は格子状に全てガラスが入れられていたことをはっきり覚えている。最近、あるきっかけで興味深い事実を知った。
寝たきりになった子規の部屋の全ての障子の引き戸が、明治32年12月、全てガラス障子に代えられたのだ。
障子の代わりに煖炉と共にガラス障子の引き戸を贈ったのは高浜虚子であった。病床の子規がガラス越しに庭をいつでも眺められるように、寒がりの子規が少しでも暖かいようにという虚子の配慮であった。
その事実を高浜虚子は自身の伝記的小説『柿二つ』に書き残している。
子規と同じく愛媛県松山出身の虚子は、子規に俳句の指導を受け、虚子の号を子規より受けた。そして生涯子規の高弟子として又友として子規の生涯に付添った。
子規は新しいガラス障子を大変喜んだ。明治33年1月の『ホトトギス』に掲載した「新年雑記」にはガラス越しに眺められるようになった景色の数々が、ウキウキした心情そのままに綴られている。
【イチオシ記事】「浮気とかしないの?」「試してみますか?」冗談で言ったつもりだったがその後オトコとオンナになった
【注目記事】そっと乱れた毛布を直し、「午後4時38分に亡くなられました」と家族に低い声で告げ、一歩下がって手を合わせ頭を垂たれた