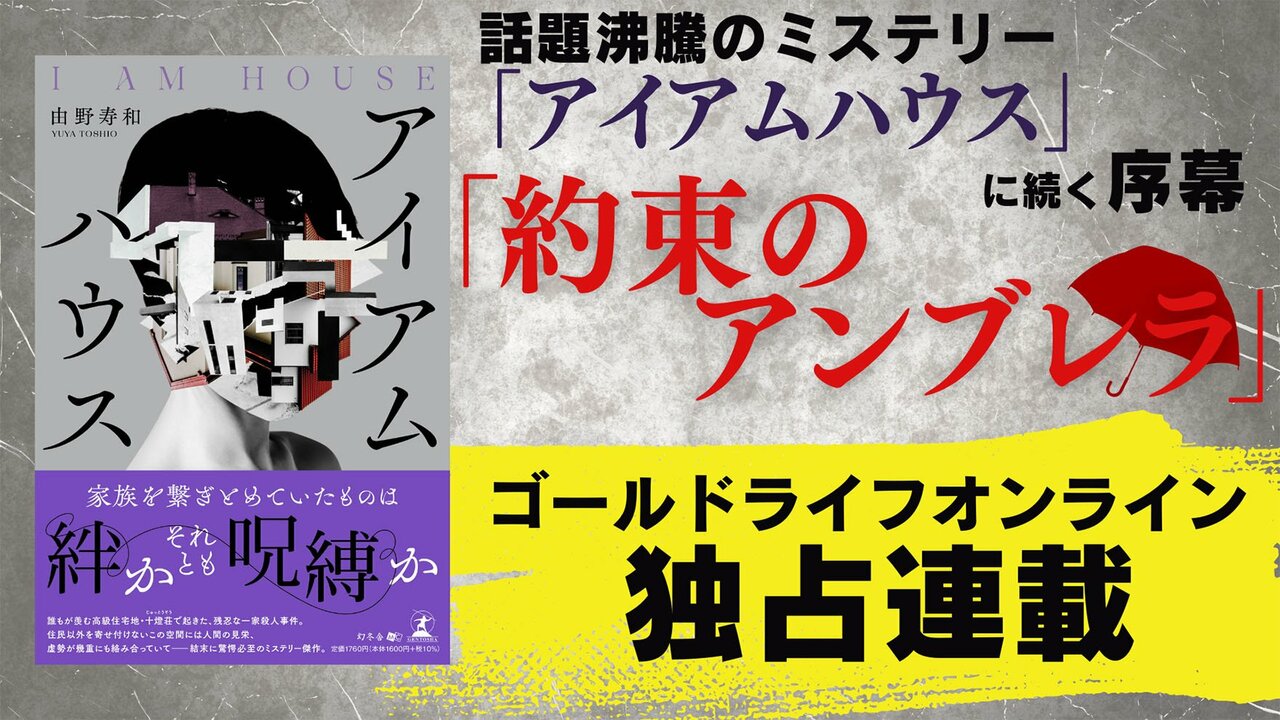『それはそうだろう、当然のことを言うな』
この高圧的な声を仲山はよく知っていた。お前か、と息を吐く。
『金森。俺が代わろう』
そう言いながら受話器を取り上げたのは貝崎だった。仲山は眉を少し釣り上げた。
『観覧車ジャックだのと妙なことを言い張る輩がいると聞いてな。仲山、五年ぶりだ。随分とご無沙汰じゃないか』
この挨拶に、仲山は当然、友好的な言葉を返すことはできなかった。貝崎と仲山の仲は、既に五年前に破綻している。
「今や捜査責任者か、出世したものだな、貝崎。随分と甘い蜜を吸えているんじゃないか?」
『おい仲山、また問題を起こすつもりなのか?』
貝崎も仲山の言葉に揺れることはない。同期同士の二人は、互いに相手を厄介だと感じていた。昔は好敵手といえる関係だったが、今はもうそうは呼べない。
『五年ぶりで、またクリスマスだ。五年前のあの事件のように、お前が見捨てたあの子の無念を思うと今も苦しい。俺はあの悲惨(ひさん)な光景を忘れられない』
「それで、今でも俺を嗅ぎ回ってるのか?」
『……お前なんぞに構っている暇があると思うか? 俺は捜査一課にいるんだぞ』
「そうか。それならいいんだが」
『ふん、愛想のない奴だ。久しぶりに酒でも酌(く)み交(か)わしたいが、そう時間もないらしい』
話を聞かせろ、と貝崎が言う。
「いいか貝崎、これは事故ではなく予告型殺人事件だ」