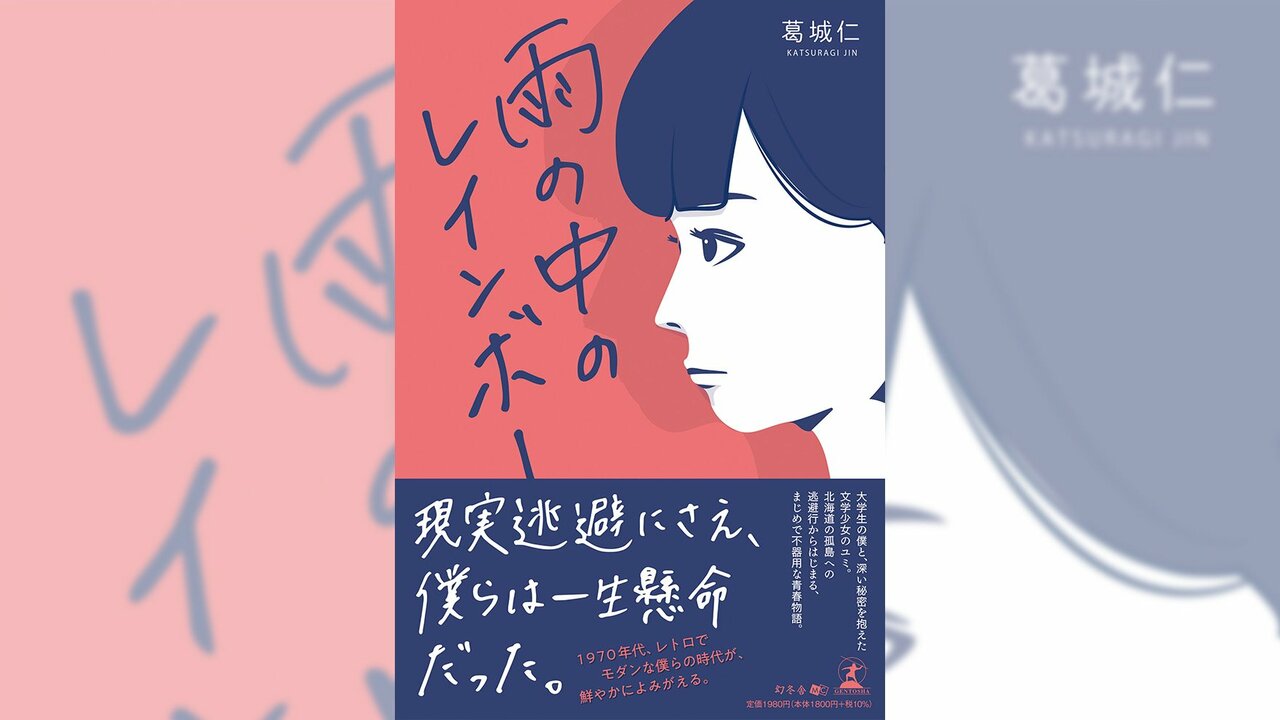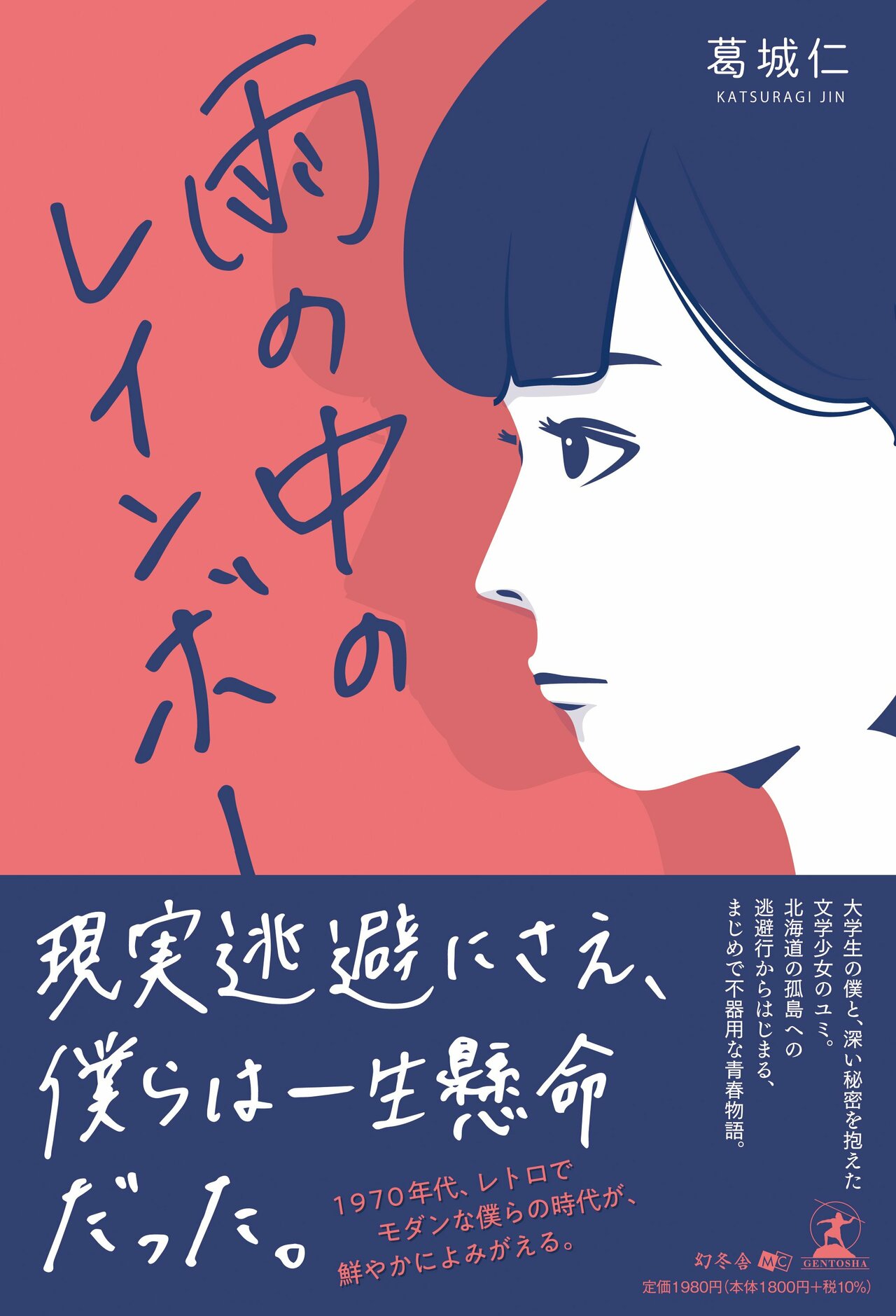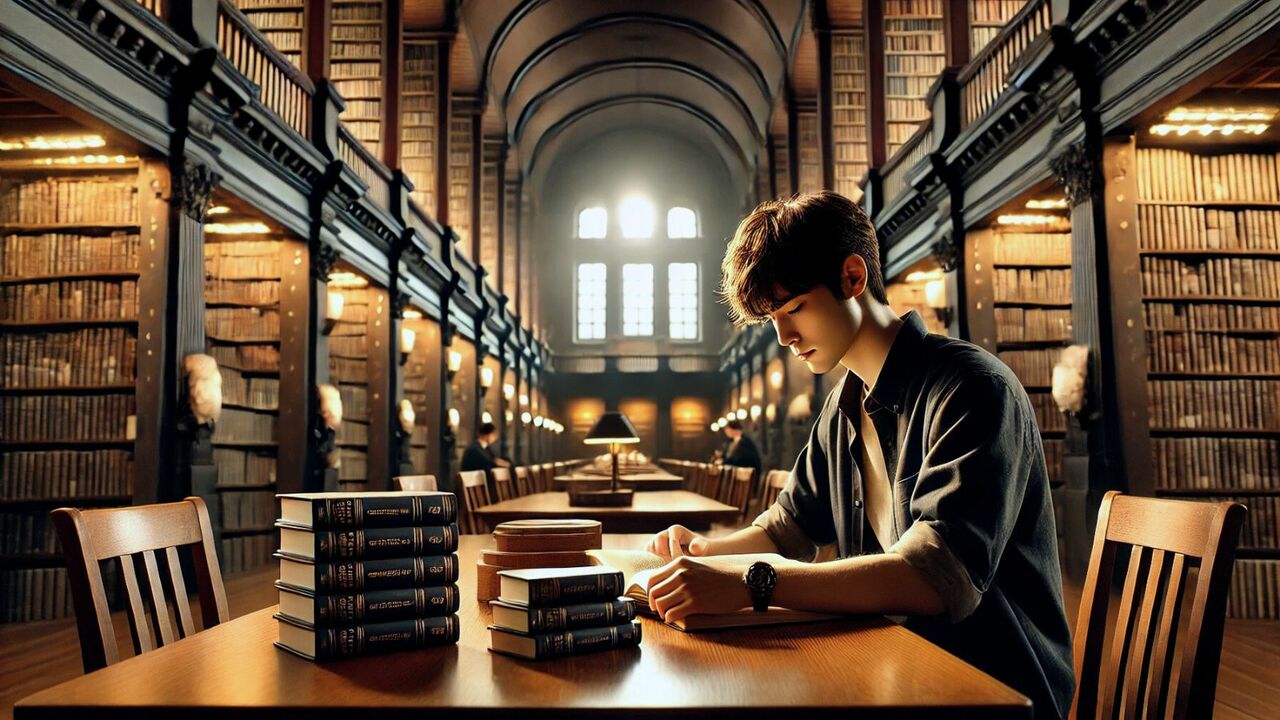【前回の記事を読む】彼女はロックを聴くんだ、「ロック+文学」派か。彼女の短歌?が、クラシックではなくロックを聴く人から出てくる仕組みを知りたい
第一章 東京 赤い車の女
4
「例えばね」と僕は語り始める。
「ベートーヴェンは十一歳から四十年間、ほぼ全生涯をかけて三十二曲のピアノソナタを書いたんだけど、特別に有名な五曲、たぶん誰でも聴いたことのある『悲愴』『月光』『テンペスト』『ワルトシュタイン』『熱情』は今の僕には全然響かない。
それらは皆、他の曲に比べて際立って個性的な旋律と特徴を持っていて、ちょっと前までは僕の心の琴線と容易に共鳴し合っていた。
ベートーヴェンはこの五曲を書くごとに画期的なステップアップを遂げていった。前に書いた曲より数段高い所にヒョイッと登っていったんだ。いわば、進化のランドマーク、記念碑だね。
八番の『悲愴』で圧倒的にロマンチックなメロディーを獲得し、十四番の『月光』で極端に緩徐で無類に美しい第一楽章を創設し、曲全体に意図的な緩急のコントラストを付けた。十七番の『テンペスト』で激しさと速さとセンチメンタルな響きの融合に成功し、二十一番の『ワルトシュタイン』で圧倒的なスピードを手に入れた。
そして二十三番の『熱情』で怒涛の激しさと劇的な構成・起伏を手に入れた、という具合にね。だからこの五曲は他の曲とは違って聴こえる、とてもわかりやすくて覚えやすいんだ」
と、ここで言葉を切って二人の顔を見る。二人は食事を止めて黙って僕を見ている。
「でも、今の僕にはロマンチックもセンチメンタルも激しさも、意図的な緩徐も速さも劇的な構成も、一切が響いてこなかった。それこそ、さっき話題になったけど〝うるさい〟んだ。
僕が最近ずっと聴いているのは、最晩年に作った二十九番『ハンマークラヴィーア』と最後に作った名前の付かない三十二番なんだ。
あらゆる意図的な企てから完全に解放されているように聞える、思うままに弾きたいように弾いているように聞える、それが特徴といえば特徴の曲たちだ。ベートーヴェンの究極の到達点、いわば完成した作品群だと言えるかもしれない。
ここでピアニストの聴き分けがおこるんだよ。今、僕が最も感動できるのは、二十九番の第三楽章と三十二番の第二楽章の後半なんだけど、二十九番はケンプ、三十二番はバックハウスじゃないとダメなんだ。
どっちの曲も、ただそれだけの真実、他に意味を持たない、ただの純粋な真実というようなもの、それらが小さな小さな氷の粒子もしくは凍った霧の粒子となって天空からキラキラ光りながら舞い降りてくるような音の連なりなんだけど、ケンプの一音一音を丹念に重ねていく演奏とバックハウスの一連の流れを弾き切る演奏の、それぞれの良さの違いが、それぞれの曲で際立つんだ」
と僕は語り切った、そして二人の顔を順番に見た。
小百合さんは焦点の定まらないような目をして軽くうなずいてくれた。ユミは、「そうなんだ」と言って、右手に持っていたサンドイッチを一口、パクっと食べた。
「ケンプの真実の氷はキラキラと舞い下りてくる。バックハウスの氷は霧のように細かくて絶え間なく降り注ぐんだ」
と、僕は追い打ちをかけた。