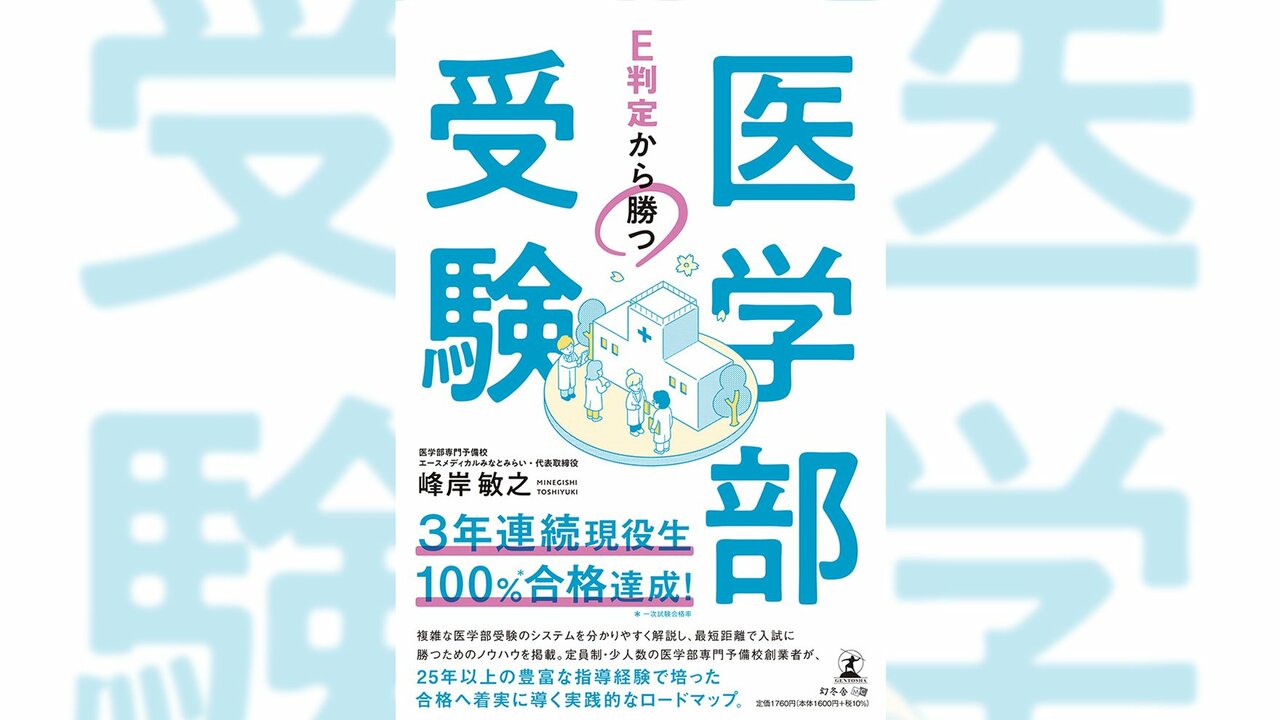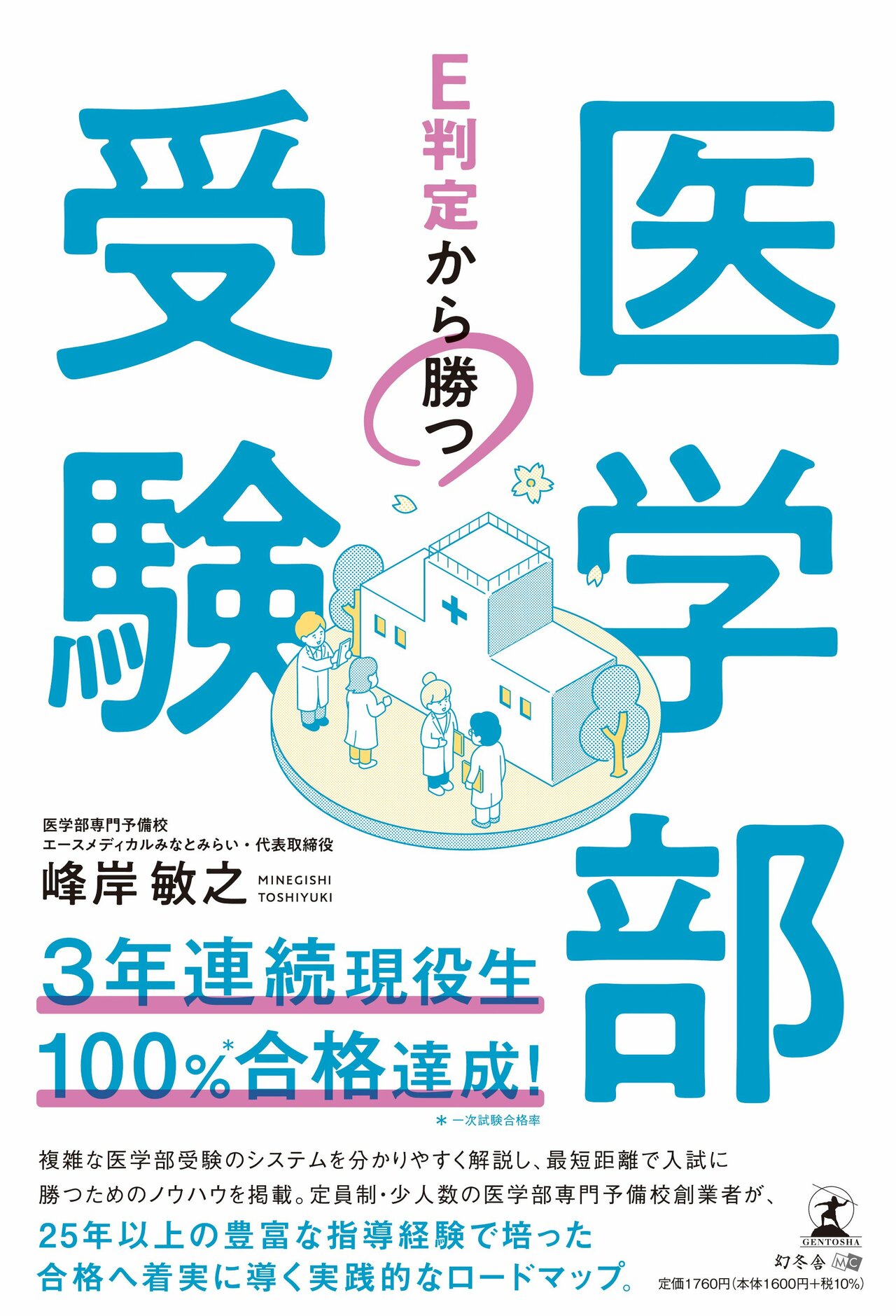【前回の記事を読む】受験校の選定にはテストのプロの力が有利! 加えて一般入試以外の方法にも注目してみよう。
医学部入試システム編
PART 4 総合型入試(旧AO入試)
1 東海大学の総合型入試の場合
東海大学・希望の星育成の例
東海大学では「希望の星育成」と称して現役生を対象に総合型選抜を実施しています。募集人数は10名です。2次選考まであります。
第1次選考の中身は ①本学所定の書類による書類審査、②小論文(60分、800字以内)、③オブザベーション評価(120分程度)、④面接試験(20~30分程度)です。
第2次選考は『大学入学共通テスト』において、「本学医学科が指定する教科・科目を受験すること」になります。
指定科目は ①外国語(リーディング・リスニング)、②数学(数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ・数学B)、③理科(2科目選択)です。
出願要件は ①東海大学医学部医学科を第一志望とする現役生、②全体の評定平均値が3.8以上かつ2023年度大学入学共通テストにおいて、指定された教科・科目を受験する者、③出身高校教員やクラブ顧問等の2名以上(少なくとも1名は出身高校教員)よりの「人物評価書」を提出できる者です。
第1次選考を細かく見ていきましょう。
オブザベーション評価
第1次選考で問題になるのはオブザベーション評価です。これは大学の募集要項によると「当日発表される課題に対し、個人やグループでの取り組み態度や思考、発信力などを拝見します。皆さんの意欲や情熱を確認すると共に、『良医』となるために必要と考える基本的な能力を評価します。」とあります。
具体的にはどのような感じなのでしょうか? 当校の合格者が再現してくれたものをもとにシミュレーションしてみましょう。
東海大学でのオブザベーション評価とは、簡単に言うと7人一組で行う対話形式の評価法です。受験生は自己紹介の後、係員からKJ法についての説明を受けます。要約すると、KJ法は、ブレインストーミングとディスカッションを組み合わせた思考法です。
具体的には、まず、各自5分間一つのテーマから 8 個の枠を埋める時間が与えられます。次に、書いた内容を発表し、7人×8個=56個のアイデアから、皆で話し合って、重要である8個を選びます。
そこから、話し合いを重ね、さらに8個のアイデアのうち、より重要であると考えられる3個を選び、その3個を達成、または獲得するために必要なものをそれぞれ8個ずつ書き出します。
最後に、5分の時間が与えられるので、各自プレゼンの準備を行い、呼ばれたら3人の試験担当者の前で完成したワークシートをもとに3分間プレゼンを行います。といった一連の流れの作業工程が丸ごとオブザベーション評価として試験官に評価されます。
約2時間の動き、発言をずっと見られているわけです。
この評価では、スムーズな話し合いを進行するために、各自の発想力、コミュニケーション能力、協調性などが必要でしょう。
また、自ら積極的に話し合いに参加して意見を述べるとともに、誠実に人のアイデアに耳を傾け、意見を尊重する姿勢も求められます。受験生は与えられた時間内に結論を出せるように、時間管理能力も見られます。
2021年のテーマは「今までの人生で一番うれしかったこと」や「良医になるとは」でした。2020年のテーマは「夢をかなえるには」でした。
こうした試験の中身を知らずに1次選考に向かった受験生と、この選考に対して十分な準備と対策をしてきた受験生ではどちらが受かるか容易に想像できます。当校では本番さながらの練習を繰り返します。その成果が3年連続合格者を生み出している理由の一つでしょう。