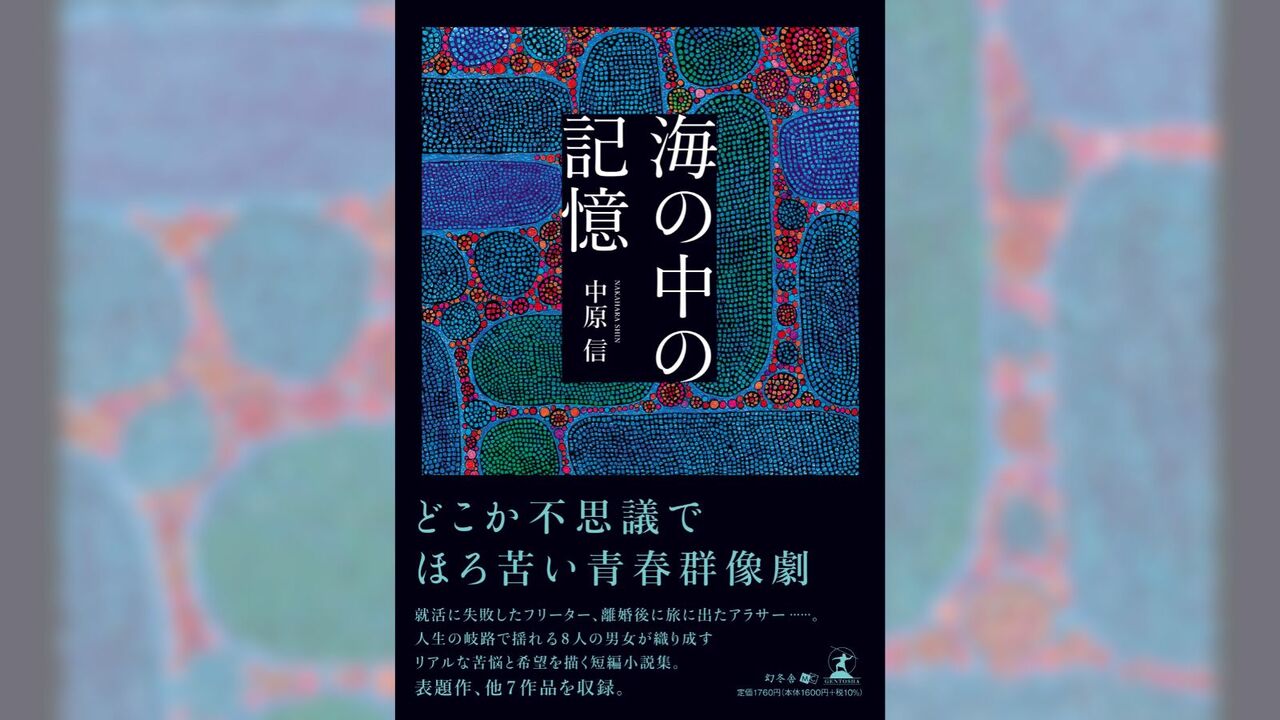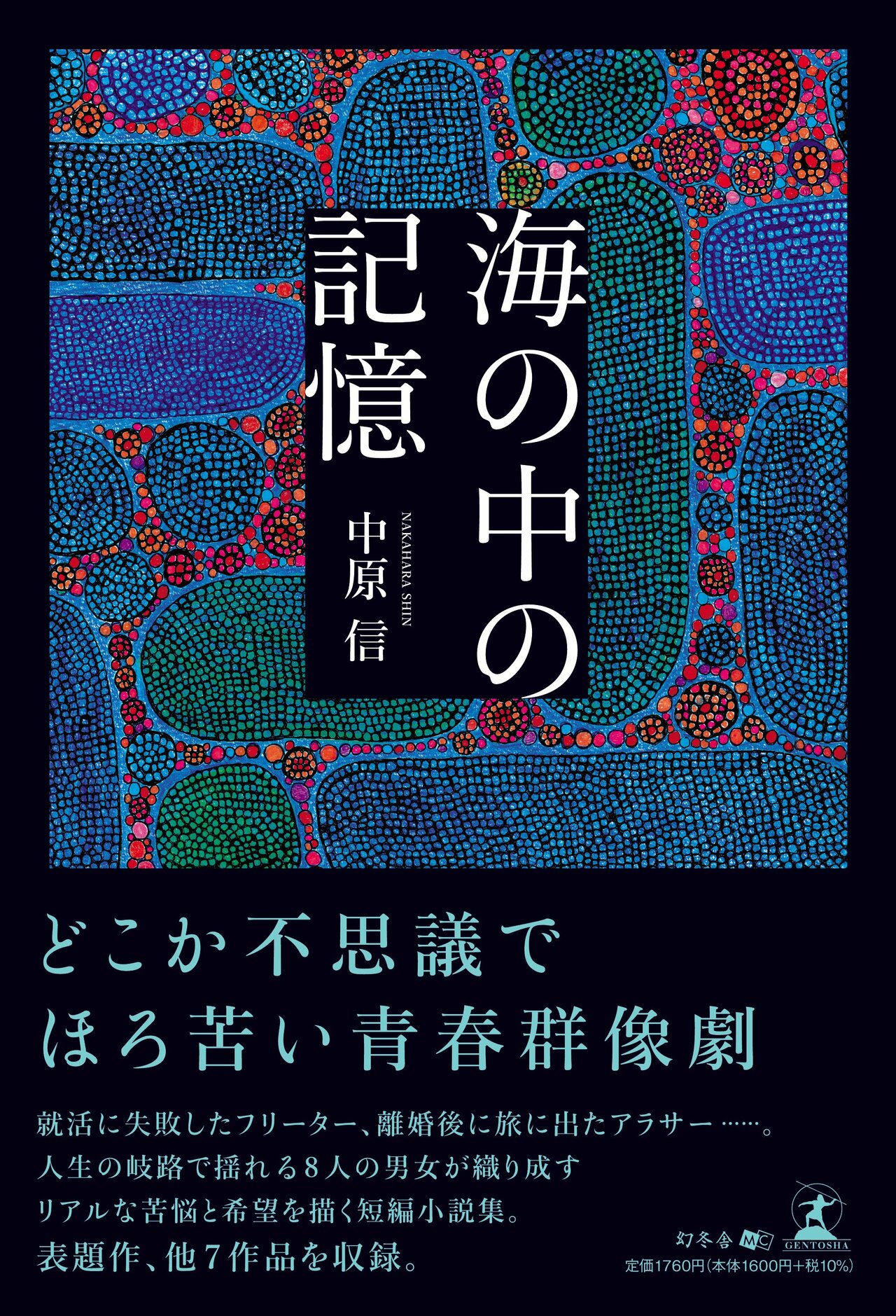【前回記事を読む】大学を卒業したものの、志望通りに就職先が決まらなかった私は、レストランでアルバイトをしながら就職活動に取り組んでいた。
アメリカ文学ゼミ
酎ハイをお代わりしたリカコさんが、酔った勢いで後輩の私に対し、〝指導〟と〝激励〟の言葉を大袈裟に語っていると思ったが、それは違っていた。
「知ったかぶりの知識で、サリンジャー班の卒論は書かないでほしい」
リカコさんの強い〝要請〟には、テキストを深く読み込んだ者だけがわかる、理解の正確さとその確からしさへの自信が裏打ちされていた。
「謎多き作家だからって、テキストをちゃんと読まないでいいって理由にはならないわ」
私は巷に溢れている噂程度の根拠に基づき、推測や憶測で論文を書くつもりは毛頭なかったが、自分の英語力がリカコさんのレベルに及ばないこともよく自覚していた。
サリンジャーがただ好きなだけ、ほかの作家より私の性分に合っていると感じただけ、というのが、サリンジャーを選んだ理由だったが、そういう私のミーハー的な態度がリカコさんに見抜かれていたのも事実だった。
リカコさんに託された重荷に戸惑いつつも、担当を引き継ぐことの責任と、その洞窟の中にある文学の深淵のようなものは、私なりに感じていた。それはサリンジャー班の先輩たちが書いてきた論文の、分厚いファイルを手渡されたからだった。
私は二年間主要なサリンジャー作品とみっちり向き合った。四年生になった今、リカコさんがあの時訴えたかったことが少しわかった。
実は私以外にもう一人、サリンジャー担当を志望する男子学生がいた。彼は高校生の時、『ライ麦』を読んで愛読者になった。しかし、私より成績が振るわず希望は叶わなかった。教授と相談し、彼はオー・ヘンリー担当になり、短編集を読んでいくうちにヤル気になったそうだ。
ホーソーン班、ポー班、ホイットマン班、メルヴィル班、トウェイン班、ドライサー班、ヘミングウェイ班、そして黒人文学班などなど、アメリカ文学史上偉大な作家たちの作品を一通り学べるように各担当が構成されていた。
いずれも先輩から後輩へ引き継がれ、それぞれの班の卒論ファイルは年ごとに厚さを増していった。