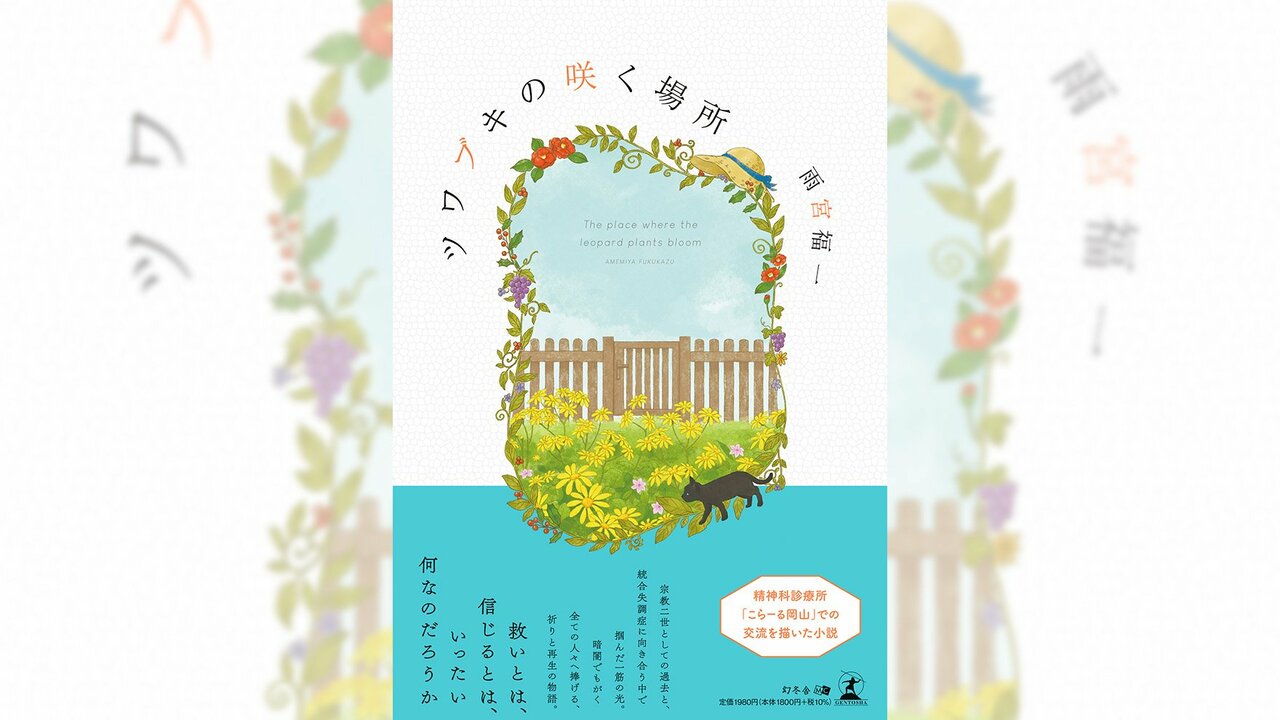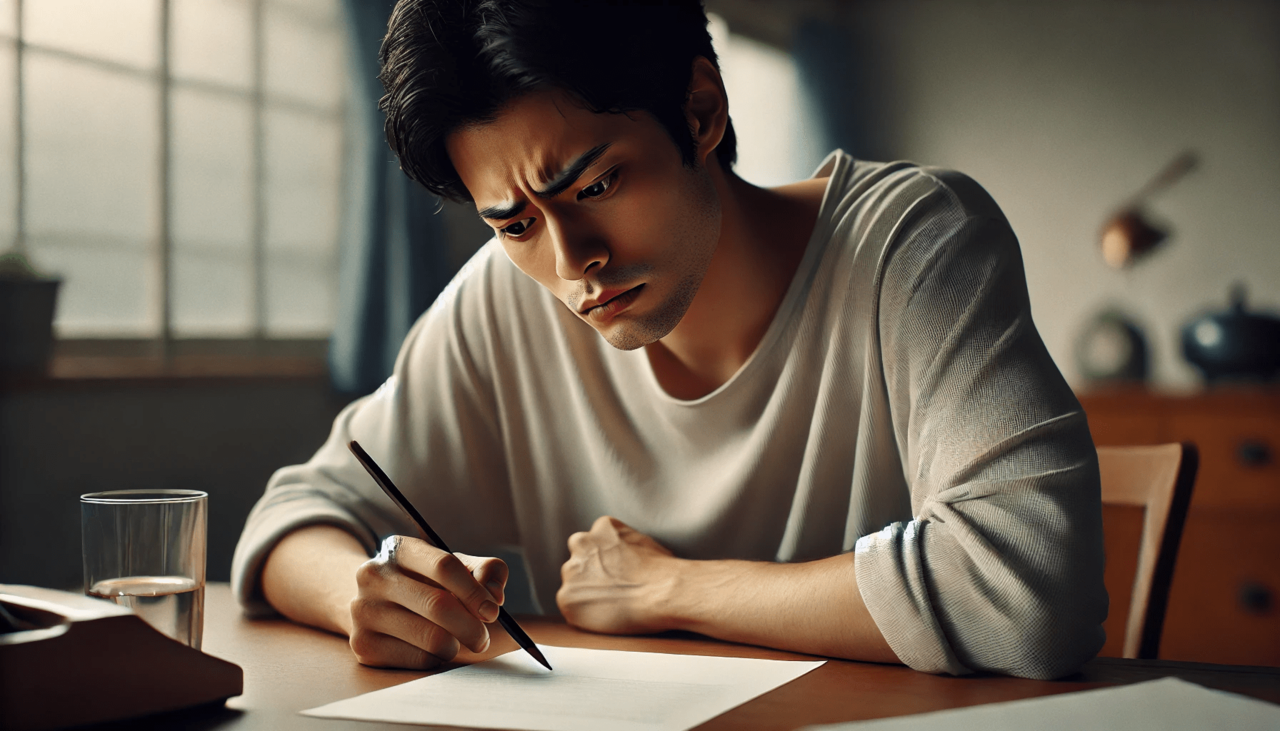【前回の記事を読む】統合失調症に苦しみ、生きていた。誰かに自分の考えが読み取られているような、そんな感覚にとらわれていた。
第一章 靴
【 一 】
この家は、近くに郵便局がある。小さな郵便局で、午後五時にはもう店じまいだ。私はごくごくまれに、その郵便局で、葉書や便せんを購(あがな)っていた。山本先生が年賀状や見舞の挨拶状をくださるので、それへ返信するためである。
「今の時代、手書きの文字ってなかなか見ないだろう? 菅野の詩集も手書きだったけれど」
「そう言えば……」
思わず私は、菅野さんの詩や手紙を収めている、とある本棚を見た。束の間、難しい数学の問題の解法をひらめいた時のような感動が、それはもう鮮烈に、胸いっぱいに広がっていく。
そうだ。妹への返事なら、無理に電話でする必要なんかない。無視する必要はさらにない。時間は掛かっても、手紙で返事すればいいじゃないか。
「そうか、その手があった」
「何が?」
「ああっ、えーと。き、昨日から、本棚の整理をしていたんだ。どう整理したら本が取り出しやすいか、思いついたんだよ」
私は、きつね色に揚がった蓮根を引っくり返しながらそう答えた。永ちゃんは微笑みながら、私のほうを見ている。
(いつもみたいに、何か考えごとをしてたのだな……)と思わせたかもしれない。
私は少しだけ気恥ずかしくなって、火の通った野菜を一度皿へ上げ、フライパンに調味料を加える。もらった唐揚げに甘酢あんを混ぜ合わせ、味が衣に付いたところでフライパンに再度野菜を戻す。
そうしておいて、先ほど思い付いた「手紙にする」ということを、いつもポケットに入れているメモ帳へ書き付ける。折々のメモが書き込まれた百均のメモ帳は、かさが膨れ上がってパンパンになっている。
「うーん、いい香り」
鼻をひくひくさせながら、永ちゃんは食器棚から二人分の箸と皿を用意する。私は冷凍ご飯を二人前、電子レンジに入れた。解凍されて熱々になるタイミングで甘酢和えを皿に盛る。
ご飯は椀に盛り付ける。
「よし、それでは美味しく召し上がれ」
「それじゃ遠慮なく」
「もとはと言えば、永ちゃんが唐揚げを持って来てくれたところからだったね」
「あはは、そうだな」