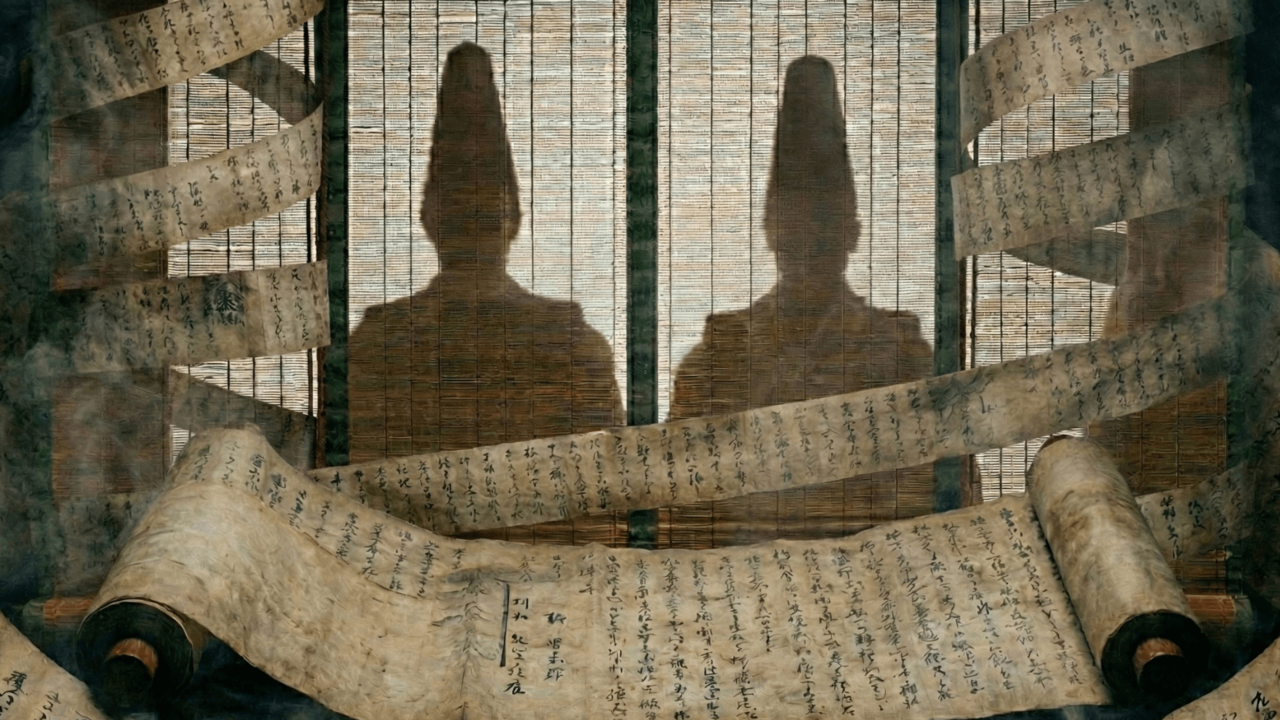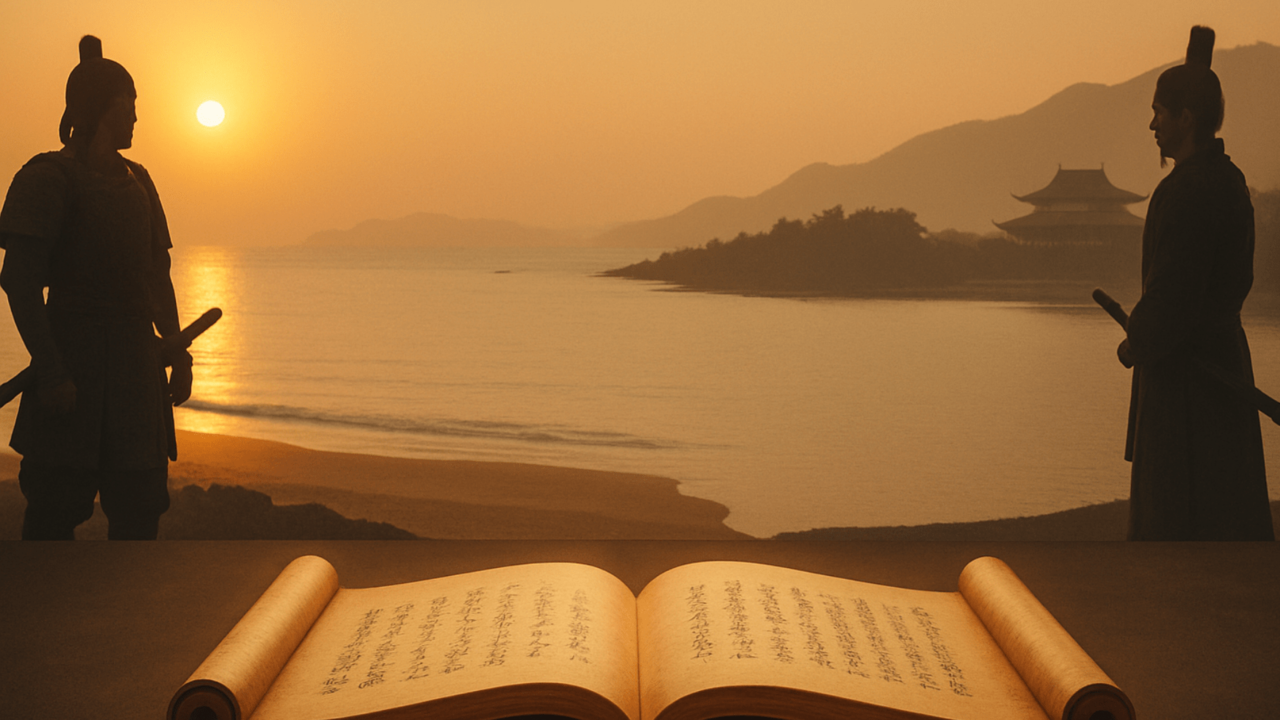読み下せば「東に毛人の五十五国を征伐し、西に多くの夷六十六国を服従させ、海を北に渡って九十五国を平らげる」となる。日本列島東西への征服譚と読めることから、列島の中央部つまり近畿地方に「倭の五王」の所在地がある、すなわち「大和天皇家」がそれにあたると三段論法的に考える学者は多い。
前述した「倭の五王」=「大和天皇家」説の支持根拠⑦について、ここで否定する。まず近畿の王が海を渡ってどこを平らげたのか。
海を琵琶湖と解釈する学者がいる。湖を渡って北陸の国々を平らげたとの考えだ。『記紀』では琵琶湖周辺を「淡海」の国と表記しているが、琵琶湖を海、北陸を海北と表現した例はない。また北陸へは陸路も拓かれており、ことさら海路を主張することもあり得ないので、海北=北陸説は考え難い。近畿の北、若狭湾の前には広い日本海があり、対岸ははるか遠くにある。
したがって海北の国々は朝鮮半島にあったとする方が納得しやすい。しかし近畿の王が西を征服した後九州から北の朝鮮半島に渡ったとするには、上表文の表現は不十分であり、恣意的すぎる。
倭王の所在地を考える上で重要な鍵は三つの文字、東の「征」、西の「服」、北の「平」である。これらの三文字はすべて征服を意味するのだが、明らかに時間的な、あるいは支配力の違いがある。
「征」とは従わない者を討伐に行くことであり、今まで勢力外だった東方の毛人の国に倭王が討ち入ったのである。実際に戦いがあった史実は不明だが、毛人の国は政治的に倭国から独立していたと読み取れる。
毛人の国が「毛野(けぬ)国」(『記紀』表記は上毛野、下毛野)だとの推測は、「第一七話」で述べるつもりだ。「毛野国」を含む関東一円は古墳が多く、西日本の国々との経済的、文化的交流は深かったと考えられる。
「服」とは命令や意に従うことで、西日本の六十六国は倭王に服従していた。古墳時代は経済力のある豪族が各地に存在する群雄割拠の時代だと考えられる。この点については「第一〇話」において詳しく論じる。