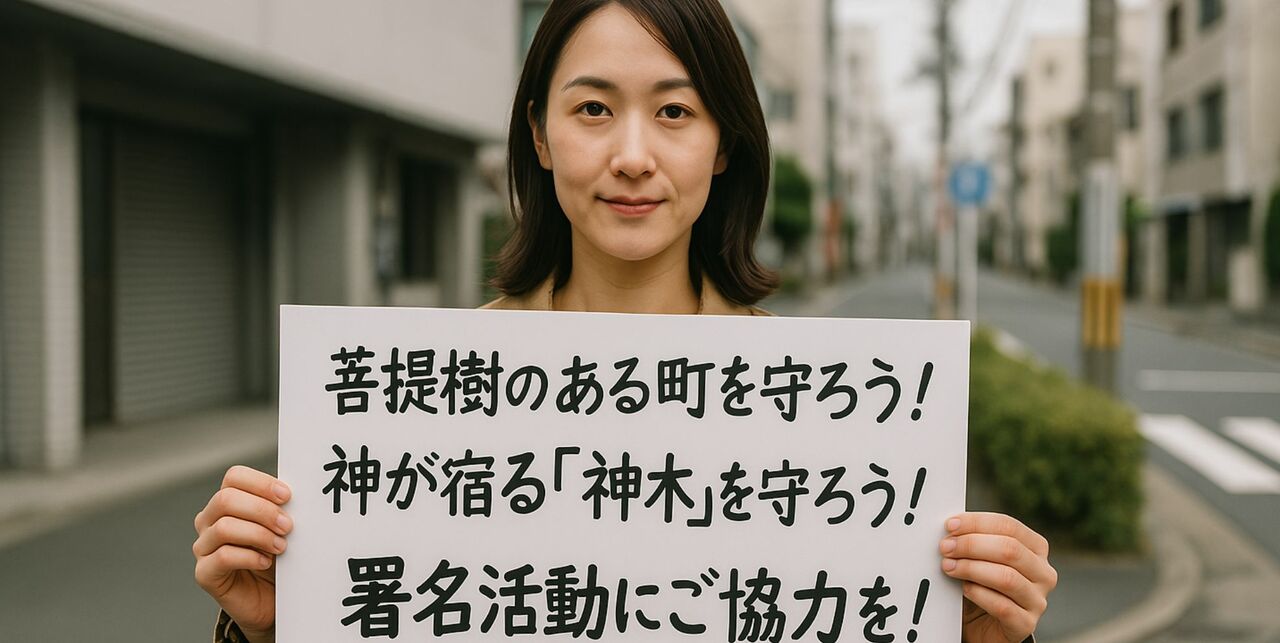そんなおもいが夕子のなかでぐるぐると回っていた。
(これが希望的観測や。そうおもわな、やってられへん)
ようやく夕子らしく腹をくくり始める。
「仕事休んで、車で病院へ連れて行くさかい。麻美は保育園の時間延長を頼むで、だいじょうぶえ」
そのおもいが通じたのか、桜子が夕子の都合も聞かずに言った。夕子も都合を聞かれたって困るだけだったから、桜子が夕子の決断を促した結果になった。
夕子は涙が出そうになった。
「ちょい冬桜観てくるわ」
夕子は桜子の世話が嬉しくて涙を隠すために母屋の外に出た。
冬桜は花数を増やして晩秋の青空に映えている。冬桜は二月ごろまで咲き続けて、品種によっては四月になると、新たに春の花を咲かせるものもある。
夕子は寒さを感じるこのごろ、どんな結果が出るかわからないが、焦らずひっそりと治療しよう。
できるだけ長く生きて悠輔と夕子の桜の園を、誰かにしっかりと引き継ぎたいとおもった。血が繋がった者に継承することは今や、不可能に近い。がんなら計画的に引き継いで逝ける。夕子はそこまで考えることができた。しかし、もう少し若かったら、生に執着して落ち着いていられなかっただろう。
そんなおもいが途切れることなく湧き上がってきてはシャボン玉のように消える。
内視鏡検査の前日、決められたとおり夜の九時に下剤を飲み、二リットル以上の水を飲んだが、便意は一向に起きない。
内視鏡を肛門から入れること自体、もう用をなさないが、母と悠輔と産婦人科の医師、それに看護師にしか見せたことのない女性器の近くなのでとても恥ずかしいことだった。
その恥ずかしさに耐えるためにも大腸は、検査に耐えられるきれいさでなければならない。少しの便も残っていてはならないのだ。夕子は完璧でありたかった。