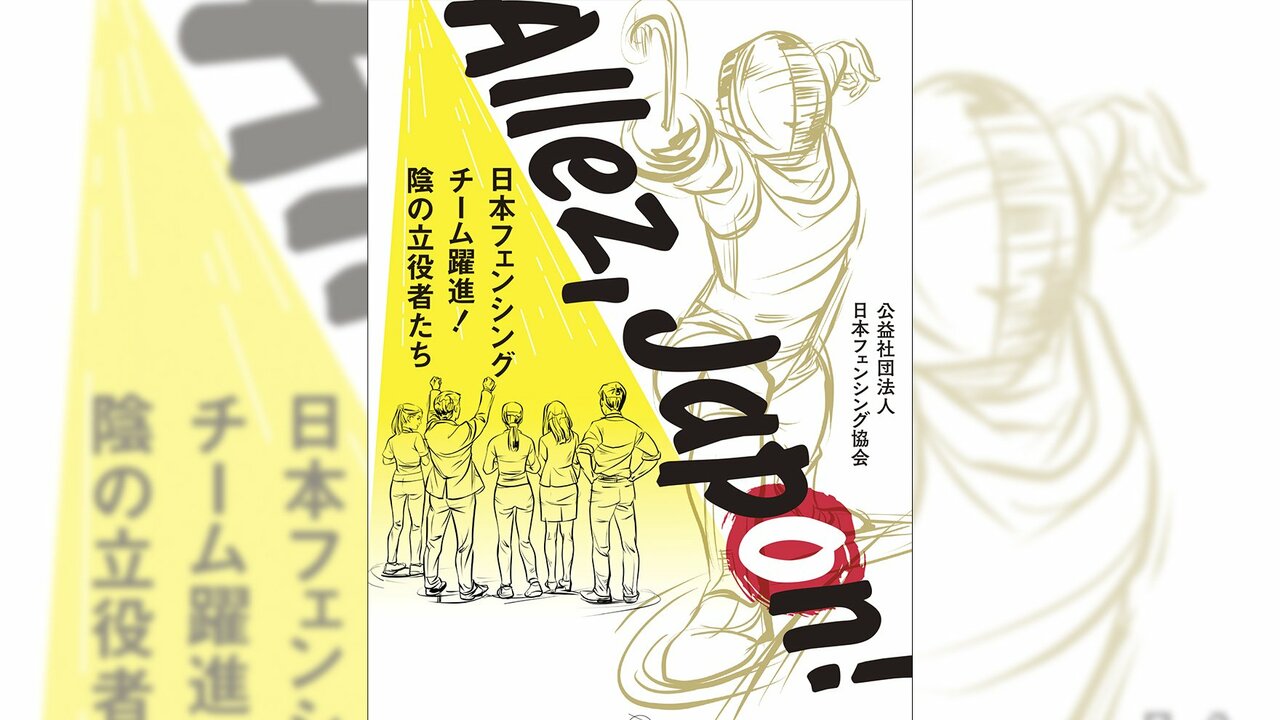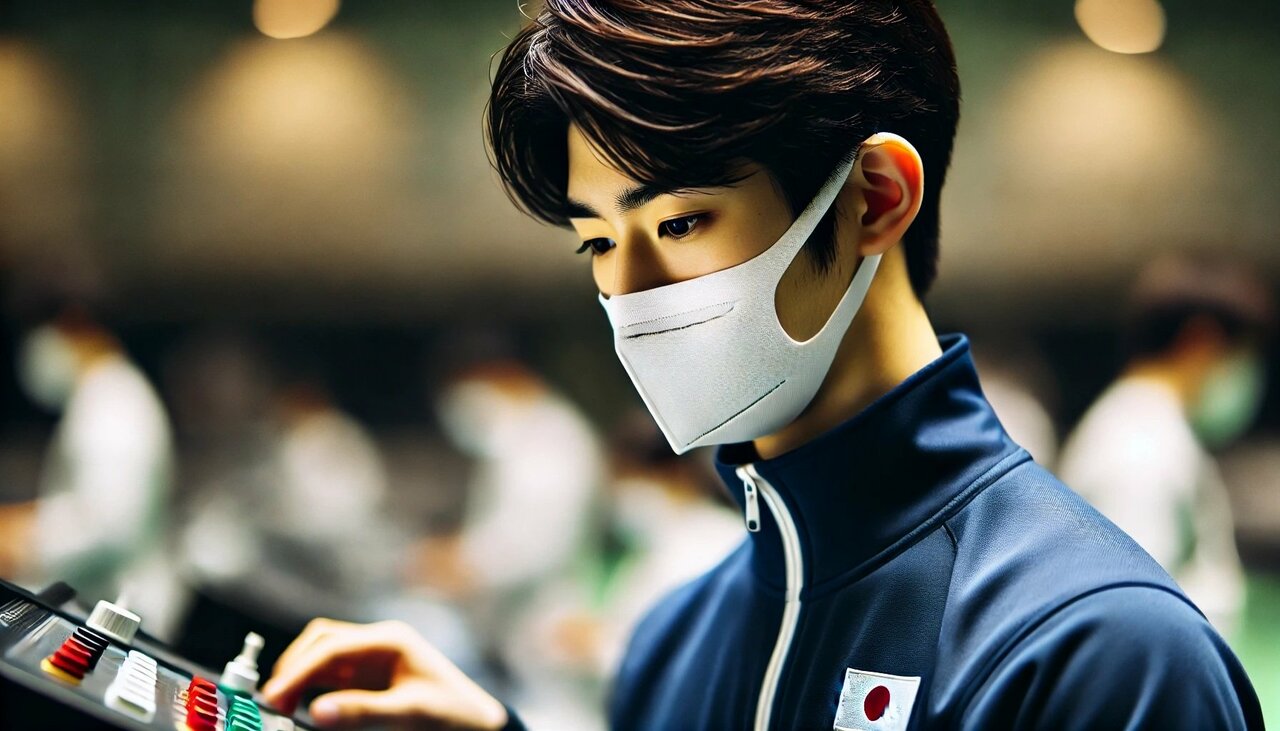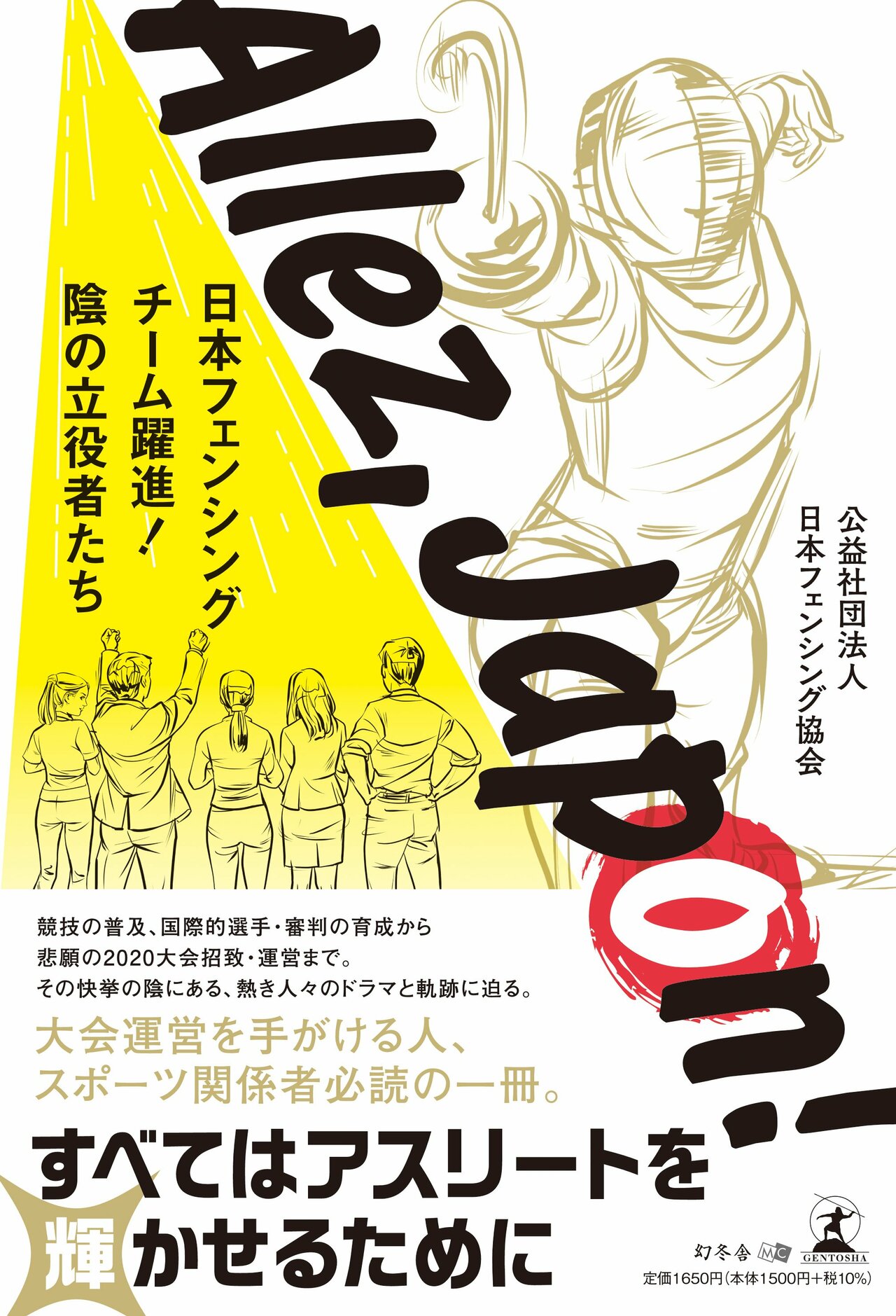【前回の記事を読む】試合直前に、審判からユニフォームへの指摘。生地を見ると明らかに薄い。選手の気持ちを考えたが、剣が貫通し、事故が起きたらどうなるか。
勝つためにすべきこと 張西厚志
「出場させてもさせなくても問題は生じる。でも安全という最大優先事項を考えて、出場を許可しませんでした。出してやりたかった、という思いは今でもありますよ。
バングラデシュ協会の方々とも関係性を築けていたこともあり、結果的にはその判断が正しかった、という結論に至ったのでホッとしました。ただ日本のため、日本が世界で勝つために、とこの立場に就きましたが、こんな責任ある立場は引き受けるんやなかった、とあの時は心底思いましたね」
数多くの経験を誇る張西にとっても、自国開催の五輪に携わるのは初めて。21年の東京五輪も困難の連続だった。
大会期間中、武器検査に関わる24名を選出すべく18年に応募をかけたが、やりたい、と手を挙げたからといって誰でもできる業務ではない。五輪という最大規模の国際大会で武器検査が担える人材となりうる定数がすぐには埋まらなかった。
時間をかけ、組織委員会の精査のもと、ようやく24名が選出され、全日本選手権やアジア選手権、男子フルーレの高円宮杯など5大会に派遣し、訓練した。
現場ではテクニカルオペレーションマネージャーの髙橋理恵が中心となり、武器検査のオペレーションや人材配置を担う中、監督官という立場で、いわば武器検査におけるしんがりを務めたのが張西だった。
「みんな一生懸命やってくれていましたが、経験は違うので、当然わからないことが出てきます。そこでわからないままにするのではなく、必ず聞きに来るように、というのはこれまでの世界大会と同様に徹底してやってきました」
大会が近づき、準備が進む中、予期せぬ事態も起こる。最も困難を極めたのが、新型コロナウイルスの世界的大流行だった。
20年に行われるはずだった東京五輪は前代未聞の延期決定が下され、直前まで、開催するのか、しないのか。そもそもこれほどの世界的危機に開催していいのか。さまざまな世論もぶつかり合う中、当初武器検査のスタッフとして参加するはずだった人員の中にも辞退を希望する声も上がった。