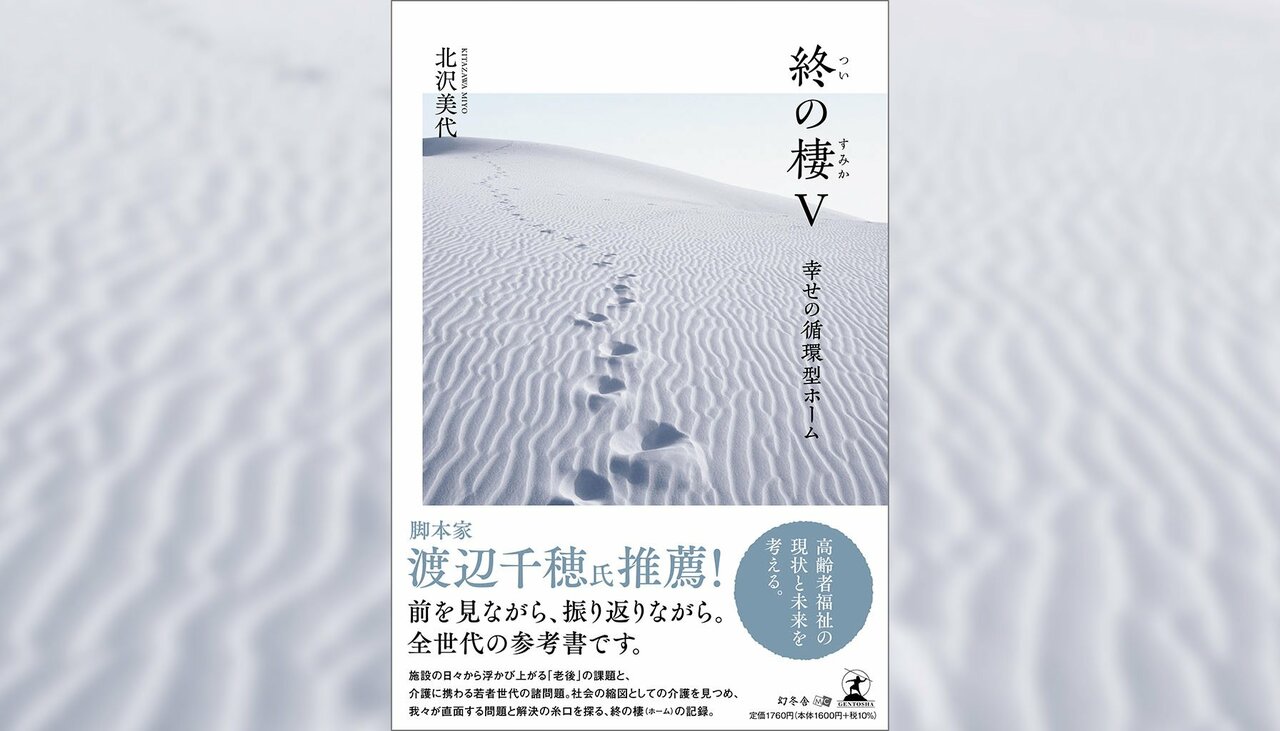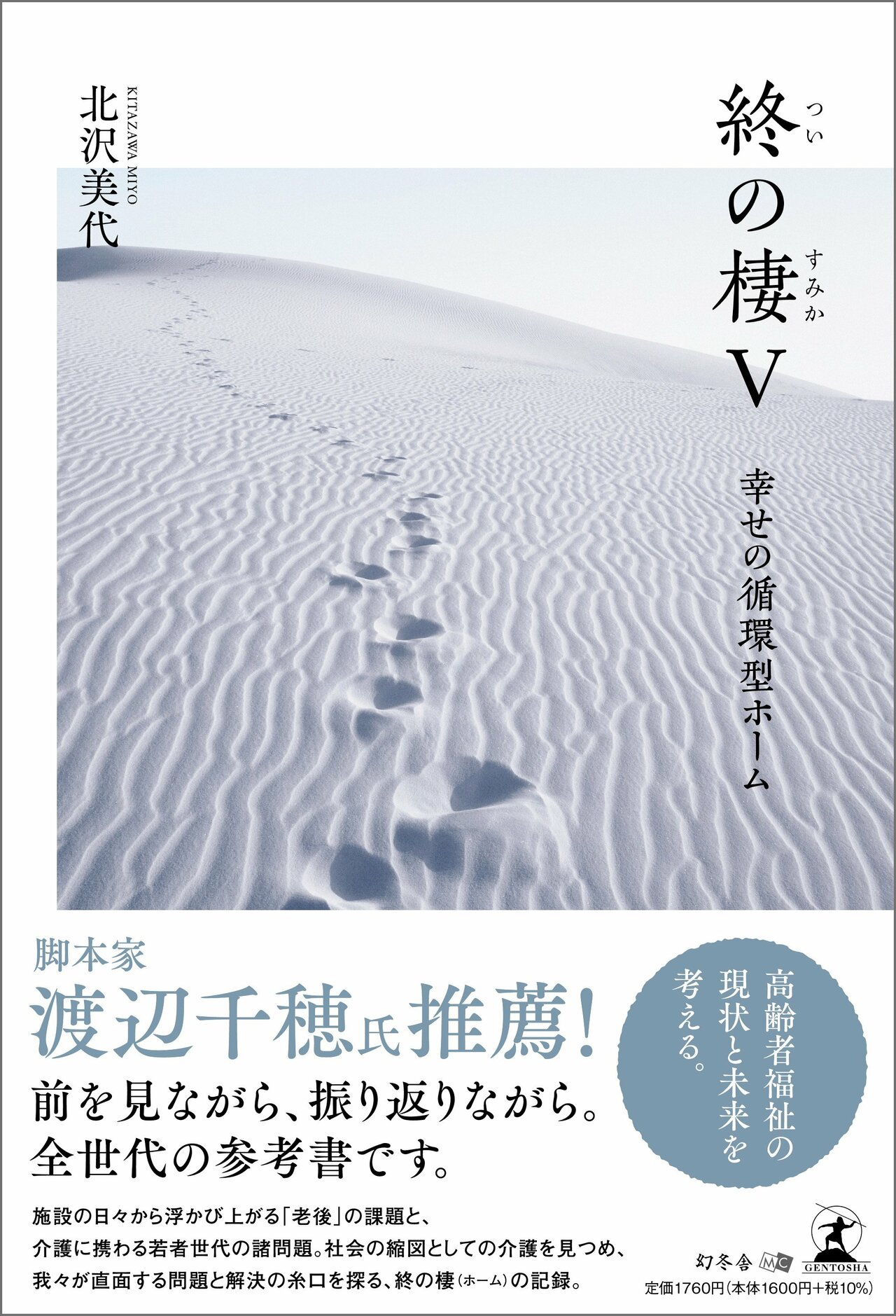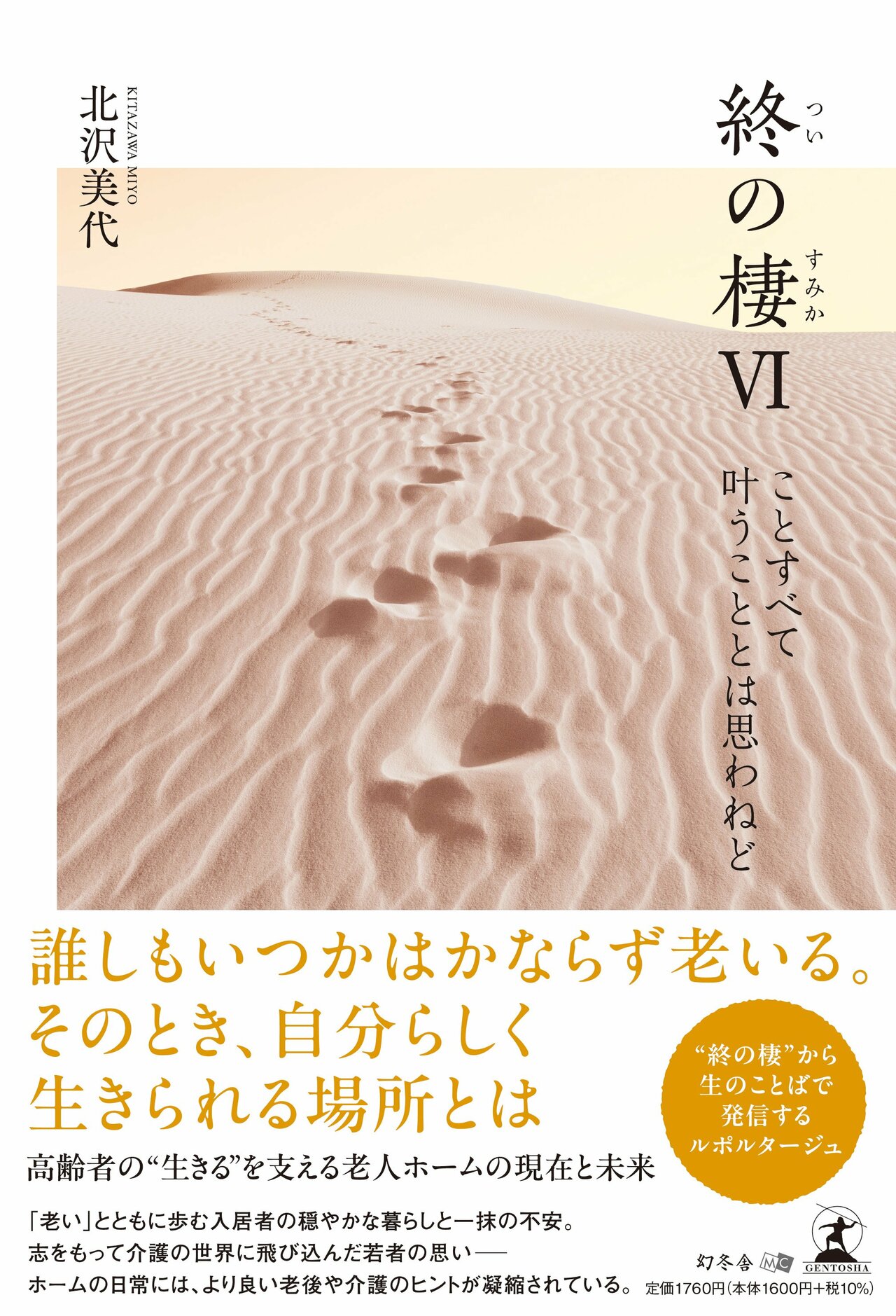第一章 介護は一方的に提供されるものではない
人生一〇〇年時代
ホームの看護師藤戸さんが「北沢さん、参加なさいますか」と言って一枚のチラシを見せてくれた。「人生一〇〇年時代を考える」のセミナーである。私が日頃関心を持っているのを知っていて彼女は私に声をかけてくれたのだ。私は即答。
私はまだナースコールを押したこともなく、直接看護師のお世話になったこともない。しかし彼女は私をよく見ていてくれた。
私も時には気持ちの落ち込むことがある。人間関係でさみしく思っていた時のことだ。彼女が廊下ですれ違いざまに「北沢さん、何かあったんですか」と声をかけてくれた。自分では気付いていなかったが多分私の表情は沈んでいたのだろう。彼女のその心遣いがとてもうれしかった。私だけでなく他の入居者からも彼女への感謝はよく聞いていた。
ましてやこの四月からこのホームでもメディカルを導入することを聞いていた。多分彼女がその中でリーダー的な役割を果たすだろうと思った私は信頼と安心をもって期待していたのだ。職員と入居者が信頼でつながることはホームの質を高めていくからだ。
このセミナーの講師は老年学(ジェロントロジー)の研究者秋山弘子氏だという。私は老年学という学問があることさえ知らなかった。「時代だな」というのが私の率直な実感だった。と、もう一つこのジェロントロジーだ。八十三歳の私はカタカナ文化になじんでいない。頭の中で一度日本語、それも漢字に翻訳してはじめて納得する。こんなやっかいな手順がいるのだ。
カタカナを受け入れるセンサーがないので現代社会では苦労が多い。今さら聞くのもなんとなく気後れし、だろうなというあたりですませていることも多い。そんなわけでこの「ジェロントロジー」をインプットさせるまでには日を要した次第だ。こうした高齢者を対象にしなければならない時代に生まれた学問なのだろうとセミナー当日までにこぎつけたというのが正直なところだ。
実際のセミナーを聴いて私が理解できたことを少々綴ってみよう。
まず私が思っていた老年学は顕微鏡で「老年」を拡大して見ることだと思っていた。納得できたことは「人生一〇〇年時代」を考えると「老年」だけに焦点を当てるのではなくそれを支えていく若者、国の問題でもあるということだ。
当り前と言えばそれまでのことだが、人生五〇年時代から一〇〇年時代に移行してきた時は「余生」ではなく「セカンドライフ」なのだと知った時、私は下の世代の後輩たちが「老人ホーム」をすでに自身のライフプランとして位置づけており、それはまさに「セカンドライフ」だった。
本を書くことによって同世代の友人、知人、そしてさらに広がってその下の世代の人たちの生き方を知っていたので、この日のセミナーの内容が一層納得できた。
セミナーの内容が盛り沢山だったので、聞き流してしまったことの方が多かった。それにしても今、すでに「協働」ということが行われているのだ。つまり、大学、企業、行政、市民の「協働」である。
そしてその中で、平均寿命から健康寿命、さらに貢献寿命と将来を見すえて動き始めているということに納得もし、大いに期待するところだった。