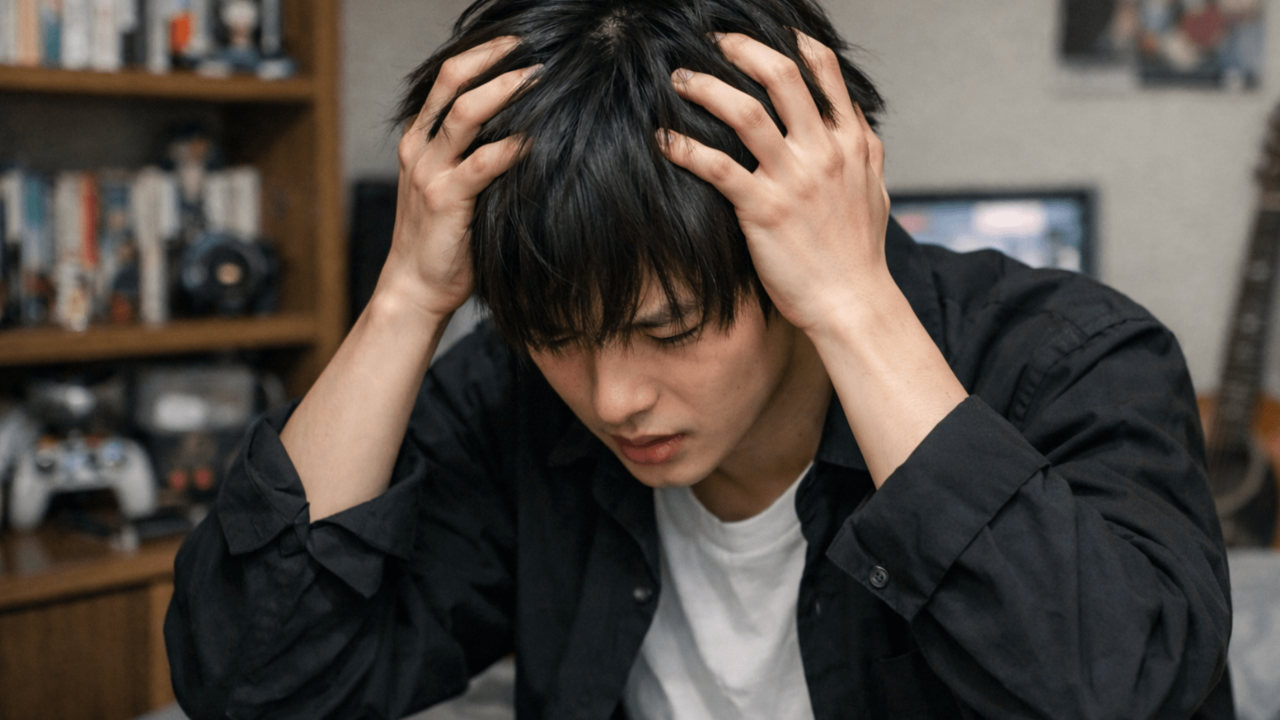「いつもこの駅使ってるの? あ、あたしの会社は二個先の駅なんだけど、今日は遅番の午後シフトでね、それで、この町にいつも世話になってる叔母(おば)さんの家があって、今からあいさつに寄るとこなの。
あ、あと、せっかくだから、手みやげを見つくろうついでの買い物ね。こういう田舎町の薄ぼんやりした商店街ってなぜか朝早くからあいてるし、意外な掘りだしものがあったりするじゃない? まあ、決戦前の気晴らしってのもあるけどね。決戦ってのはさすがにちょい盛っちゃったけどさ、親戚まわりなんて要はそのくらいの気分でしょ?
うちってさあ、けっこうこの手の親戚づきあいが面倒なんだよね。あとでしっかり親にも報告されちゃうし、なにかと気をつかうわけ。あ、それよりさ、ほら、覚えてるかなあ――」
田舎町とか薄ぼんやりした商店街とか、ひどい言いようである。こぢんまりとしてるし都心のような賑わいはないけど、一応は東京郊外のそれなりにひらけた町なんだが……。
とにかくこの人、わたしがなにも言わなくても、自動おしゃべりマシンのように勝手に話し続ける。ああ、確かにこういう子だったなあ、と記憶の奥のわたしがうなずく。
趣味も嗜好もまるでかみあわなかったのに、なんだかんだとつきあいを続けられたのは、適当に相槌(あいづち)を打っていればこちらはなにもしなくていい、ある意味すごく楽チンな相手だったからだ。少なくとも彼女は、相手をいやな気持ちにさせる人ではなかった。
そんなわけで、今日もまたあのころと同じように「へえ、そうなんだ」「うんうん」「なるほどねえ」と愛想笑いを返しているうちに、程よく時間が経過した。
ところが、“さて、そろそろ”と話を切りあげるタイミングをさぐりはじめたところで、彼女は、まるではかったように、予期せぬ爆弾を投下してきたのである。
「ね、ね、三吉さん、すごくスマートになったよね」
……へ? 今度はこちらがぽかんとしてしまう番だった。
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。