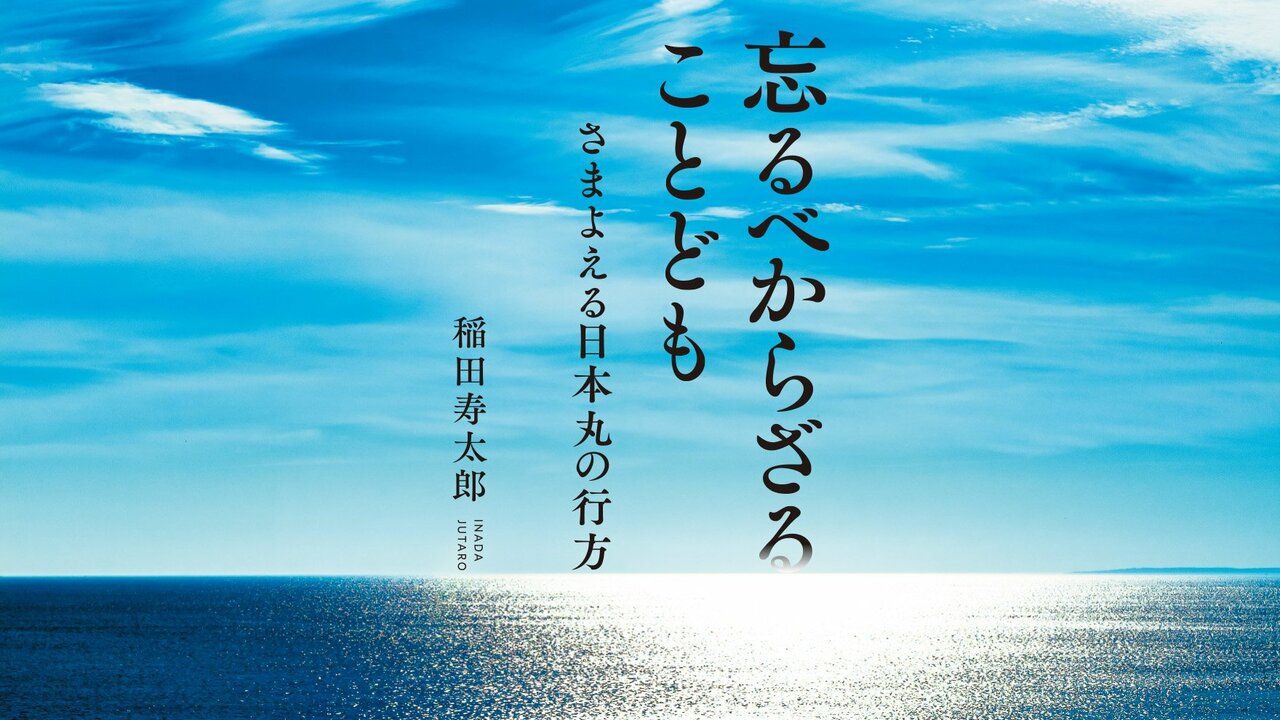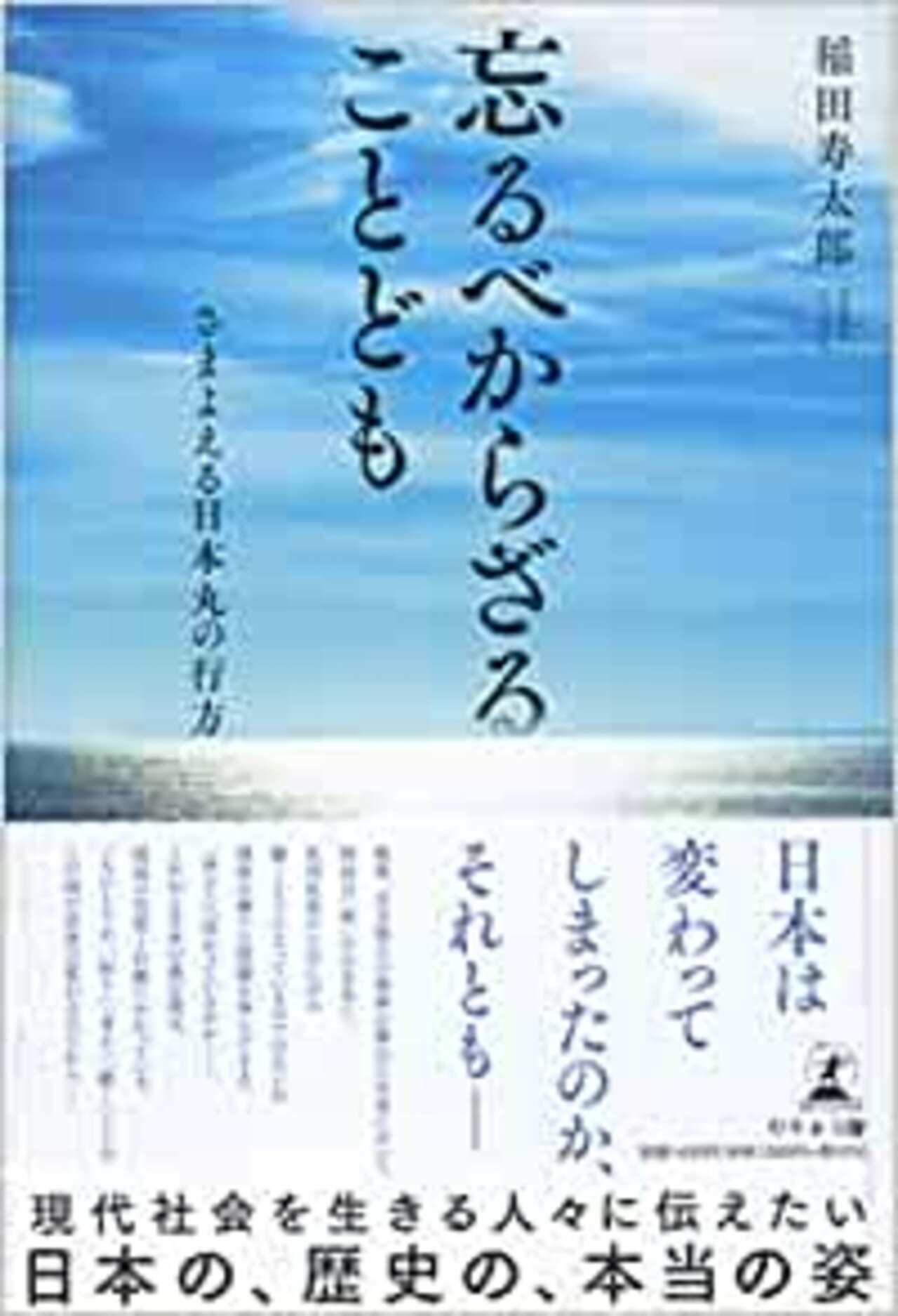第二章 歴代中華王朝における華夷秩序の変遷
今日に至る日朝関係
こうした朝鮮側のかたくなな対応に対して日本国内に征韓論が芽生えてくる。「征韓論」は西郷隆盛が唱えたとされているが、必ずしもそうではない。西郷は朝鮮を良導する(体を張って説得する)つもりであったかもしれないが、陸軍大将の地位についていたために勇ましい征韓と結び付けられたのであろう。
なかなかこちらの意図を理解してくれない朝鮮や中国に対して日本国内世論は、「脱亜入欧論(だつあにゅうおうろん)」に傾斜していく。
遂に海軍大輔(だいふ)川村純義等の建議を受けて二隻の軍艦が朝鮮沿岸に極秘裏に派遣される。その後も測量目的で数回にわたって派遣される。
こうした情勢下明治八年(一八七五)九月二十日、江華島砲台から砲撃を受けて交戦状態となる(江華島事件)。事件終結後、江華島条約(日朝修好条規:一八七六年)が日朝二国間において結ばれる。
その第一条に「朝鮮国ハ自主ノ国」と明記されて条約上朝鮮は清の属国から解放されたことになった(ただし清は認めていない)。本条約締結後、一八八二年宗主国清の斡旋によって「米朝修好通商条約」が締結されて名実ともに朝鮮の鎖国政策は撤廃される。
この条約は米朝間で交わされたのではなく、米国と大清帝国間で交わされた条約案文を朝鮮側が事後承認する形で締結されている。
清のは李鴻章(りこうしょう)朝鮮は依然として清の属国であることを案文に明記しようとしたけれども米側が拒否し、朝鮮側から清の属国であることを認める文書をあらためて提出させるよう要求している。
本条約締結後朝鮮は宗主国であった清の干渉(認可)を受けて欧州諸国と次々に条約を結ぶことになるが、これが不平等条約(最恵国待遇ではない)の先駆となってしまう。
米国と交わした条約には「斡旋(あっせん)条項」として第三国(日・中・露等)に脅された場合、米国に助けを求めることができると明記されていた。しかし米国は何度も助けを求められたが応じることはなかった。
同年親清派と親日派間の争い壬午(じんご)の乱(京城事変)が起こり、清国が朝鮮への内政干渉を強める。一八八四年、親日派によるクーデター、(甲申(こうしん)の乱)が発生する。
これは科挙試験に合格した開明派の金玉均(きんぎょくきん)を中心とした近代化運動であった。彼は儒教を基本とする朱子学にどっぷり浸かっていた朝鮮の文明開化を望み、高宗の勅命を得て日本に留学し、福沢諭吉の支援によって慶應義塾に居候する。
諭吉の斡旋で井上馨から借款して朝鮮人の日本留学を進める。また朝鮮で初めての新聞発行も手がけている。