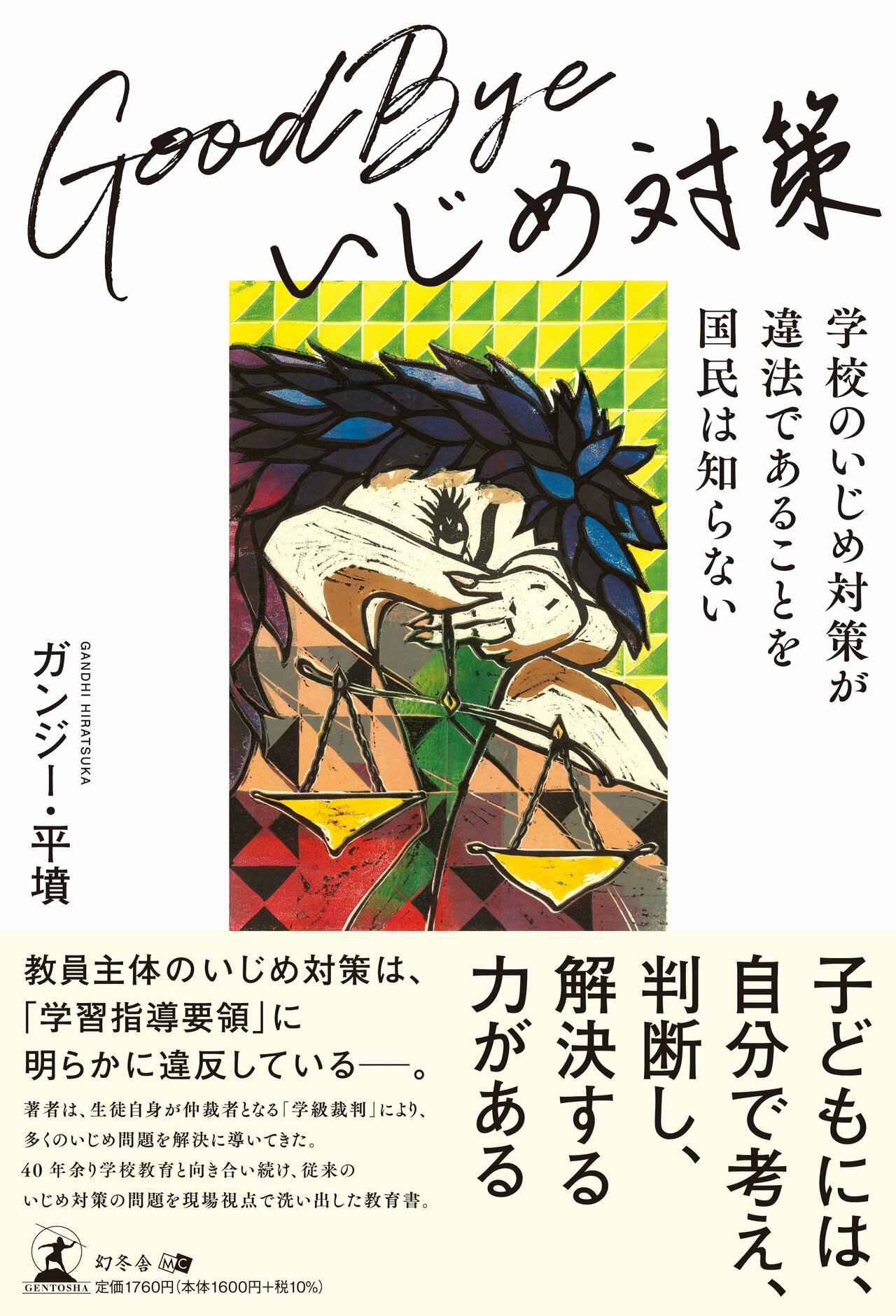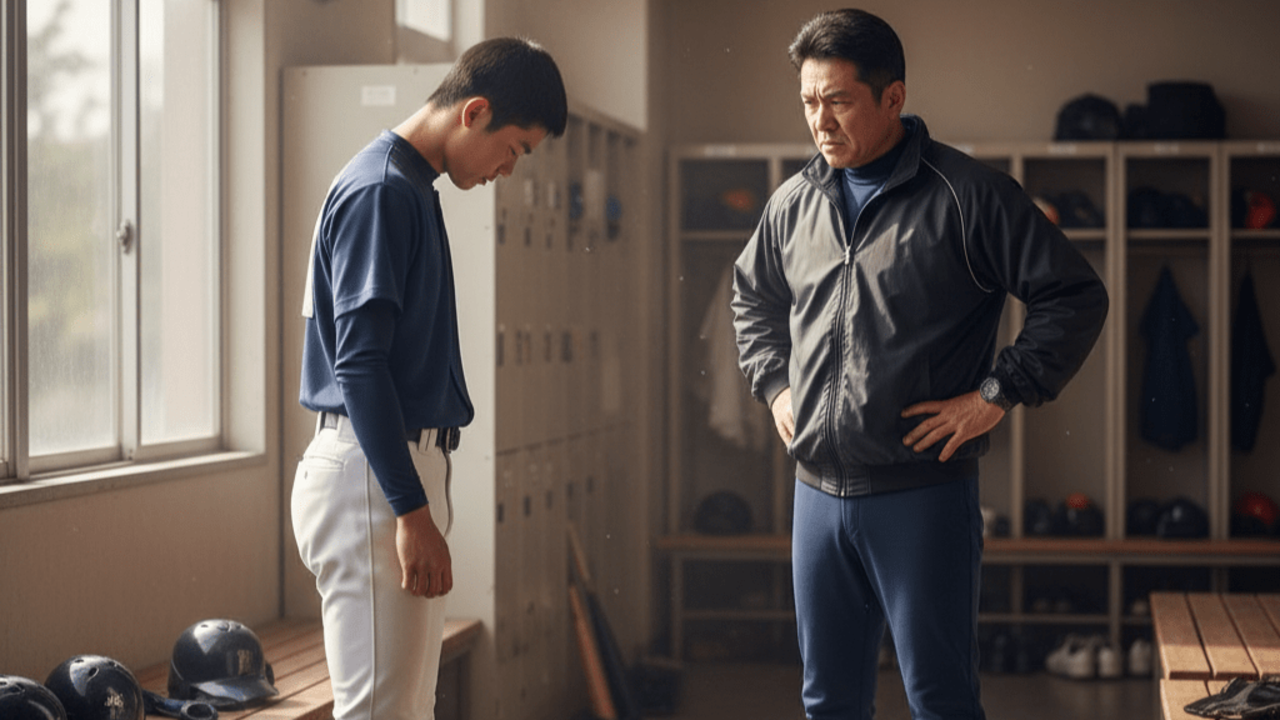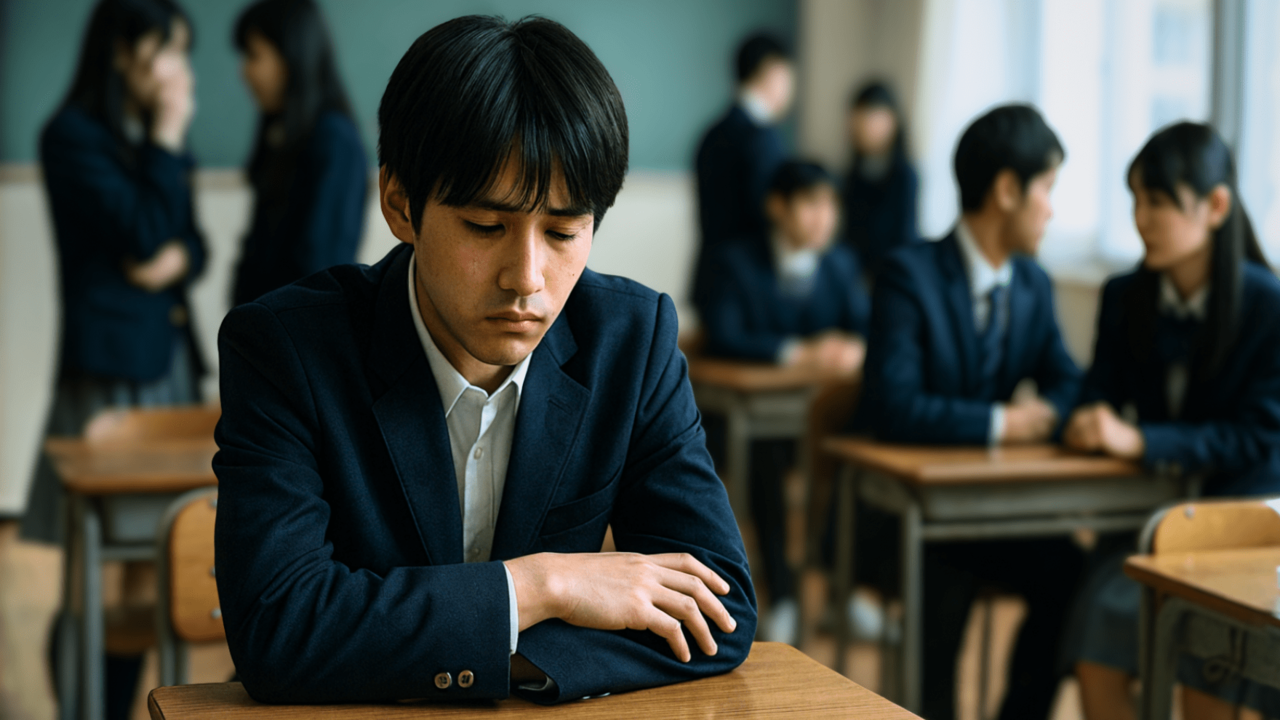学校の用心棒
学校では、「ダメなことはダメ」とか「違反行為は絶対に許さない」などと、先生が威厳を持ってビシッといい聞かせることがよしとされ、生徒指導で慣例として引き継がれてきました。
今でもそんな先生は「毅然(きぜん)として迫力ある先生」とか「学校の用心棒」などと重宝がられ、とくに荒れた学校では生徒指導の中核となって生徒や先生を仕切っています。
しかし、ことはそんなに単純ではありません。生徒からは「怖い先生」と恐れられて、ツッパリ生徒もその先生の前では借りてきた猫のようにお行儀よく振る舞いますが、先生がいなくなると元のように乱暴に振る舞うようになります。ましてや普通の生徒にしても、そんな怖い先生に悩みを相談することはありません。
やさしい先生ならば問題がないかというと、そうでもありません。「子どもの冤罪(えんざい)」が問題になっています。子どもは、「やさしい先生に心配をかけてはいけない」と、つい「私がやりました」と心の思いとは違うことを口にしてしまうのです。
外国を見渡すと、たとえばアメリカのアイオワ州の中学校では、「友だちの悪口を言う(ヘイトスピーチ)」や「廊下を走り回る」や「ものを投げる」などのいじめや規律違反などに対し、生徒が問題解決の担い手(仲裁者)となり話し合いにより解決しています。
有名なティーンコート(10代の法廷)は、少年犯罪の比較的罪の軽いものについて 10代の少年たちが問題解決の仲裁者としてその罪を審議する仕組みですが、教育効果が高いとしてアメリカのほとんどの州で実施されています。