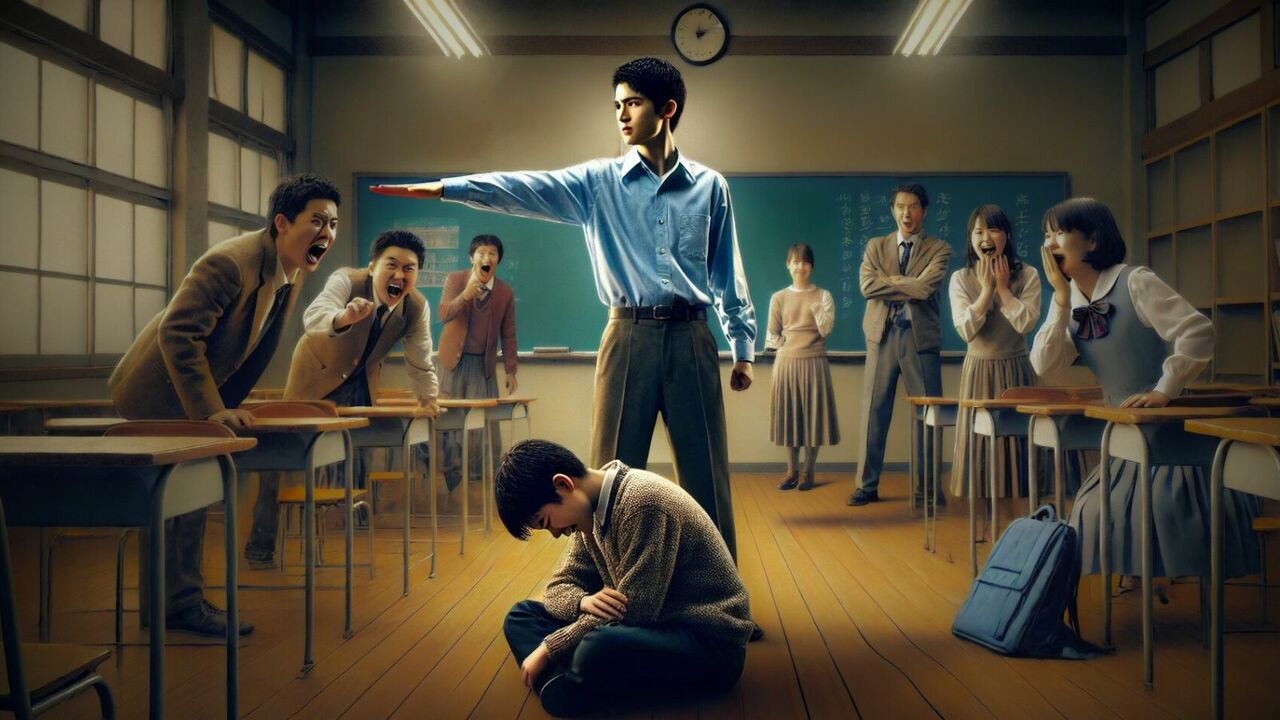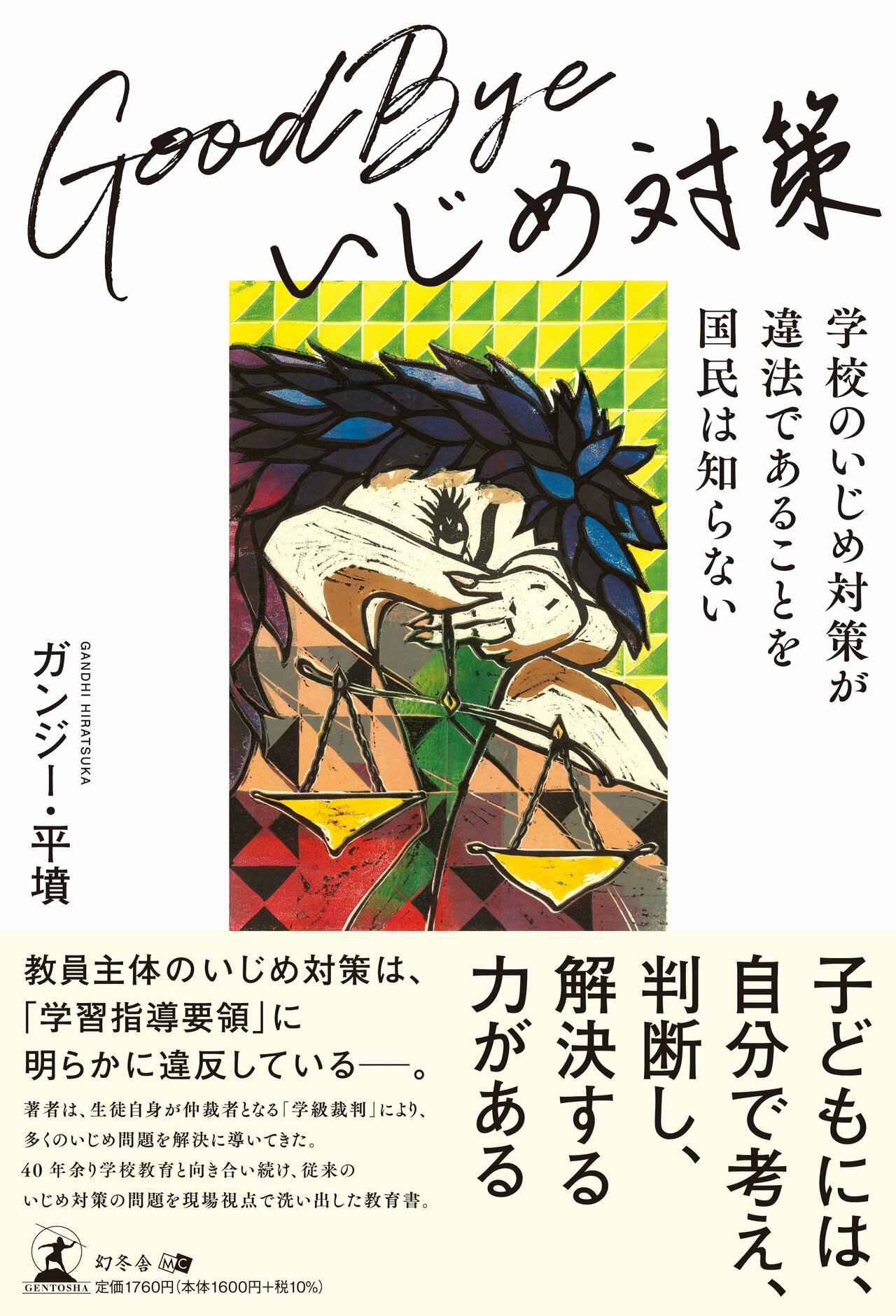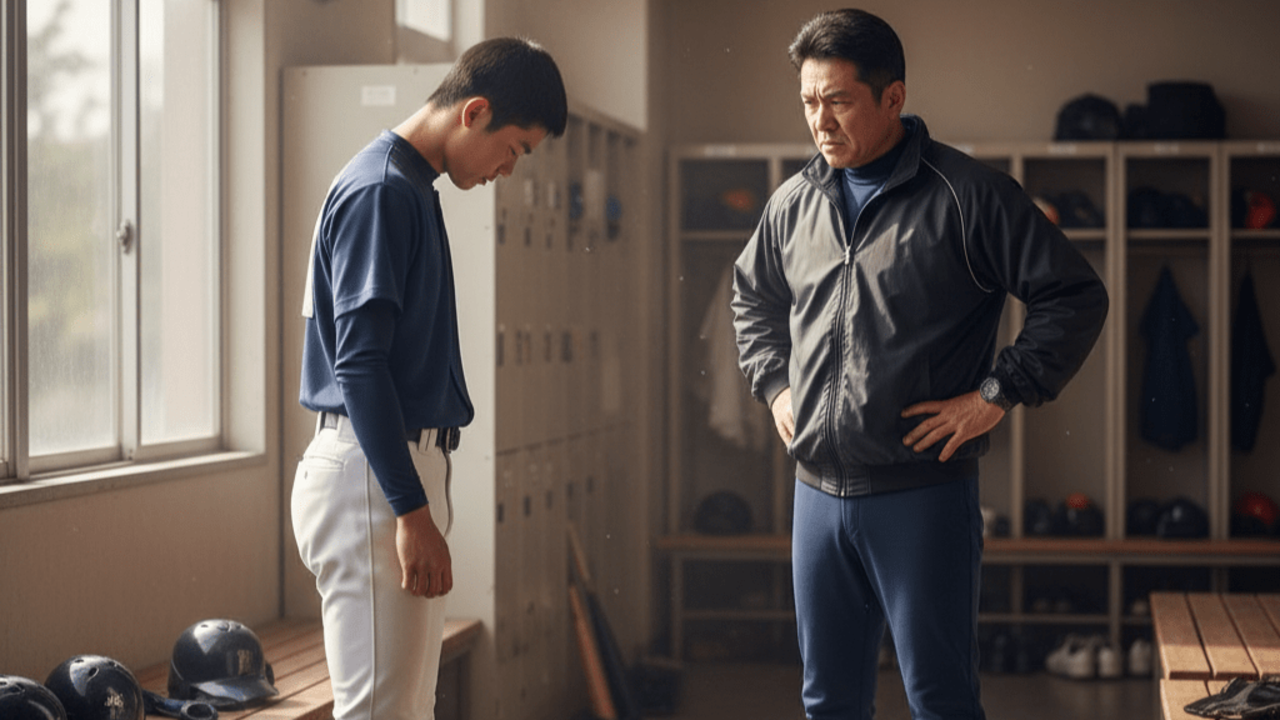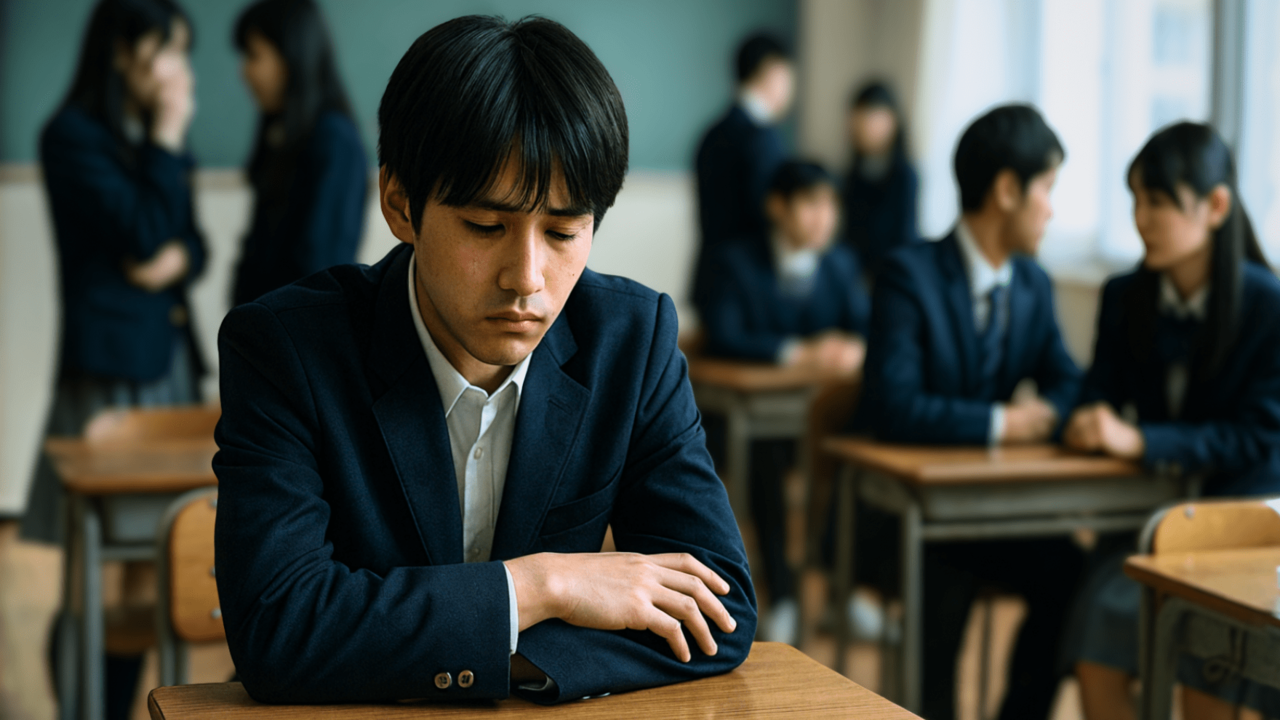第一章 だれがいじめを解決するのか
―学習指導要領といじめ解決―
いじめや暴力、差別や偏見の解決
さらに学習指導要領解説には、学級の諸問題について具体的に「学級内の人間関係のあつれきの対処の仕方」「係や当番などの仕事の遂行に伴う悩みの解決」「教科の学習にかかわる問題」などを示しています。
いっぽうで、学習指導要領は手引き書という考えもあります。
1948年の学習指導要領は「教師自身が自分で研究して行く手引きとして書かれた」ものでしたが、1955年からは「手引き」という記述がなくなりました。
さらに全国統一学力試験への反対運動である1976年の旭川学力テスト事件の最高裁判決により、「学習指導要領には法的基準性がある旨の判決」がなされ、文部省(当時)は「学習指導要領は法的拘束力を有する」とした経過があります。
そのために教育研究者のなかには、「そもそも法的拘束力という考え方は教育に馴染まない」「学習指導要領は手引きとして作るべき」との考えもあります。
しかし、学校で教える内容は年間指導計画に組み込まれていますし、教科書は学習指導要領にそって書かれ、教材や各種プリントやテストも学習指導要領にそった中身となっていますし、入学式や卒業式の「日の丸・君が代」にしても、年間行事に位置づけられて式次第に組み込まれています。子どもたちの前でひとりだけ着席して歌わないわけにはいきません。
さらに学級活動は、毎年の年間計画が決まっています。職員会議で特別活動部会の部長から「4月は学級目標と学級組織を決めてください」「5月はいじめ防止月間です。各学級会でいじめについて話し合い撲滅宣言を採決して、教室に掲示してください」などと資料が渡されます。
それを「私はそんな資料はいらない、別のことをやる」などと突き返すことなど考えられません。現場の先生からすれば、手引きというとらえ方は余りに非現実的です。