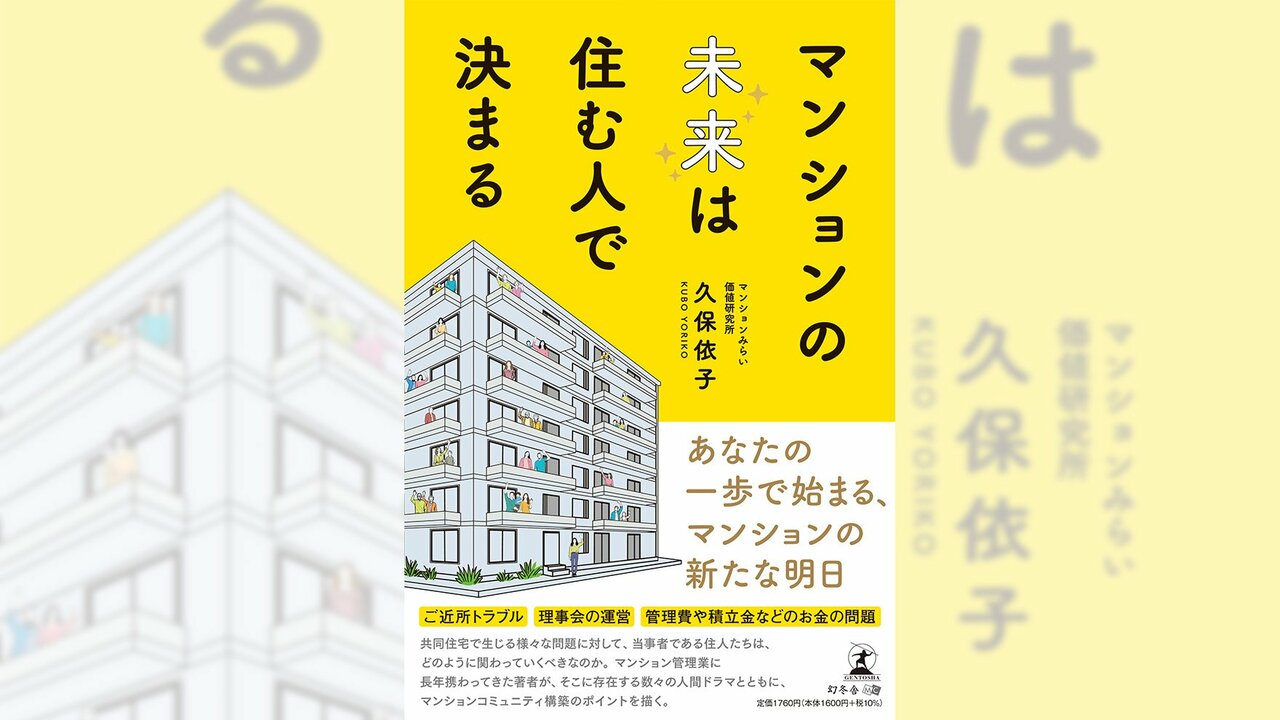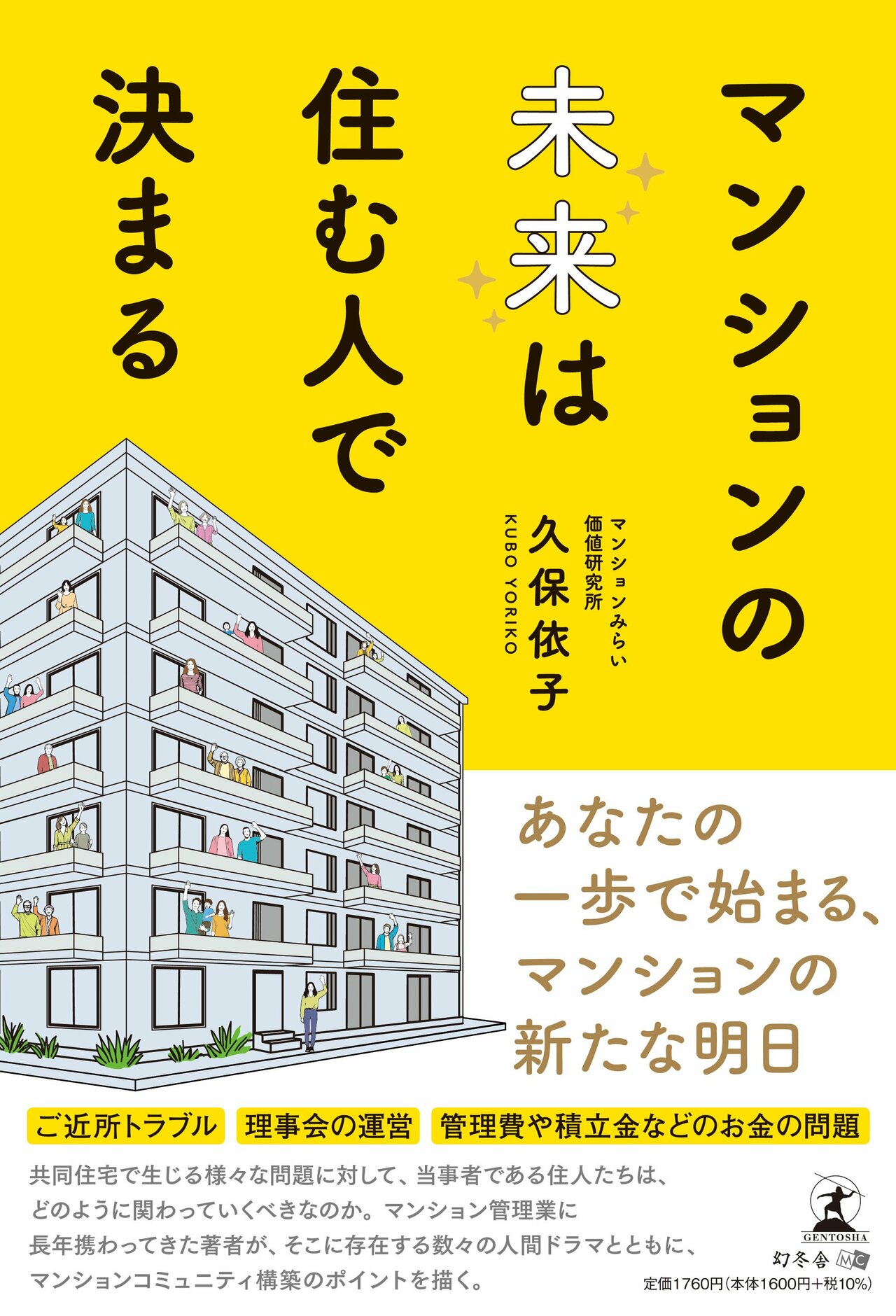第5章 建物の老朽化が止まらない
私が社会人になった当時はバブル経済真っ只中であった。マンションは飛ぶように売れ、人気のある部屋は抽選倍率が何倍にもなっていた。販売の場に立ち会うこともあったが、落選した購入希望者が家族で号泣しているというシーンに遭遇することもあった。
あの当時、誰もがバブル景気が続くことを信じて疑わなかった。私もマンションは永遠に値上がりし、売れ続けると思っていた。
バブルが崩壊して30年超。すでにバブル経済の夢跡は思い出されることもなくなった業界もある。この当時から働く社員が「バブルの頃はよかったな」などと発言すると、バブル経済期を知らない世代から疎んじられるという。
しかし、マンション管理の世界の事情は少し異なる。建物はひとたび建築されれば、数十年から建物によっては100年存続する。過去の歴史を背負う建物は多く、今もなお、随所にバブル経済の亡霊が見え隠れする。
典型的な亡霊の例が、積立金が不足し、修繕のできないマンションの存在だ。なぜそうなってしまったのか。それには、最初にマンションを購入した人の思惑が理解できると分かりやすい。
・このマンションには長いこと住むつもりはない。年収が上がれば、売却してしまおう
・売却すれば、自分より若い世代が購入するだろう
・若い世代は、年収は将来にわたり右肩上がりで増加する
・マンションは、こうしてどんどん若い世代に入れ替わっていく
・建物が古くなっても修繕に必要な費用は次の世代が背負ってくれる
今となっては「風が吹けば桶屋が儲かる」という話のようにも聞こえるが、あの当時は真面目にそう信じられていた。こうした世代交代を前提としていたのだから、当初の所有者は将来の修繕費用など関心すらなかったというのもうなずける。
ところが、バブル崩壊とともにマンション価格は下落し、自分自身の年収も上がらない。このまま、マンションに住み続けるという選択をせざるを得なくなってしまう。
さらに年数が経過して、年金生活者ともなれば、もっと支出は減らしたいだろう。そのために、積立金の値上げには反対する、お金のかかる修繕には反対する、という逆の思考サイクルが回転し出す。修繕ができないマンションの存在にはそうした時代背景がある。
よく「建物が老朽化することは、最初から分かっていることなのに、なぜ、今になって問題になるのか、もっと前から手を打つことはできなかったのか」という質問を受ける。
昔から今のように、マンションを終の棲家として考える人が多ければ、それはおっしゃる通りだ。今のマンションからは、あてにしていた次世代の支える人がいなくなってしまったのだ。日本の年金制度の構図に似ているようでもある。