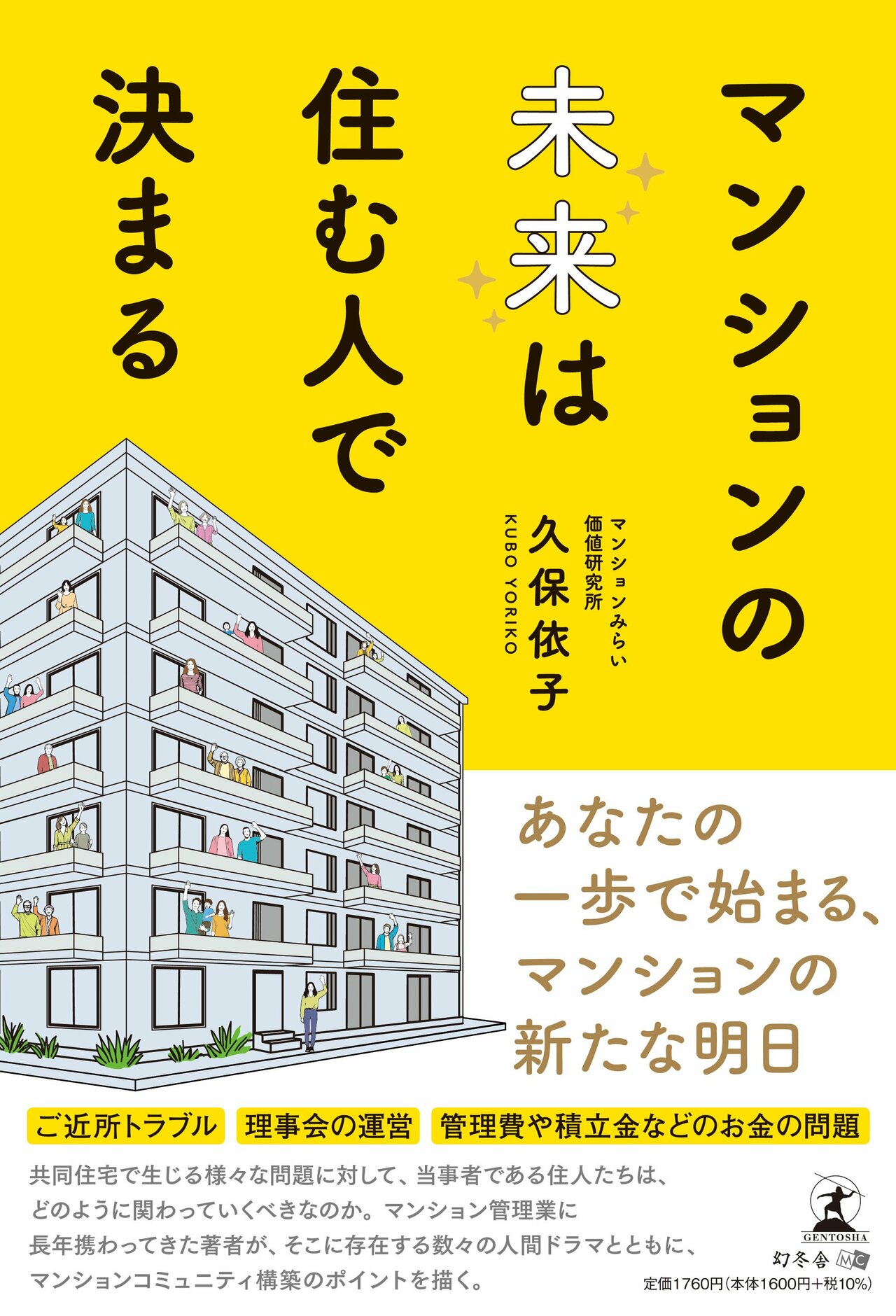孤立死の問題は二段階に分けて考える必要がある。はじめに、孤立死にならない環境を作ること、次に孤立死が発生した場合、早く発見できるようにすることである。
孤立死にならない環境をつくることは、コミュニティの希薄なマンションの中ではなかなか難しい。集会室などで高齢者向けのカフェを運営したり、居住者同士で安否確認をするといった先進事例が紹介されてはいるものの、全部のマンションでそのような取り組みをすることは不可能だろう。
しかし、早く発見することはできる。マンションみらい価値研究所でアンケート調査をしたところ、孤立死が発生した場合に、「最初に居住者の異常に気が付いた人は誰か」という設問の回答で最も多いのは管理員であった。
郵便受けにチラシがたまっている、廊下に宅配物が放置されている、長いこと姿を見かけない、そうしたことが孤立死の発見につながっている。
また、管理員の他、宅配弁当会社、新聞配達員、ガス会社のメーター検針員が気付くこともある。宅配弁当会社は配達した弁当が食べられていない、新聞配達員は配達した新聞がたまっている、ガス会社はガスのメーターが動いていないなど、それぞれの業務を行う上で「何かおかしい」と気付いたのではないかと思われる。
ただし、たとえ「何かおかしい」と思っても、関わり合いたくないと思えば無視することもできたはずである。それをせず、その異変の情報を関係者につないでいる。
今、いろいろな業種で高齢化社会に向けて何ができるのかを検討しようという機運が生まれてきている。あちこちで、世の中全体で高齢者を見守ろうとする人が増えている。マンションの居住者にもこうした機運を高めていくことが、これからのマンションに必要となる。
【前回記事を読む】「また、失敗してしまうのではないか」ゴミを出すことが怖くなり、部屋をゴミ屋敷にしてしまう認知症高齢者の心理とは...
次回更新は1月28日(火)、8時の予定です。
【イチオシ記事】「歩けるようになるのは難しいでしょうねえ」信号無視で病院に運ばれてきた馬鹿共は、地元の底辺高校時代の同級生だった。