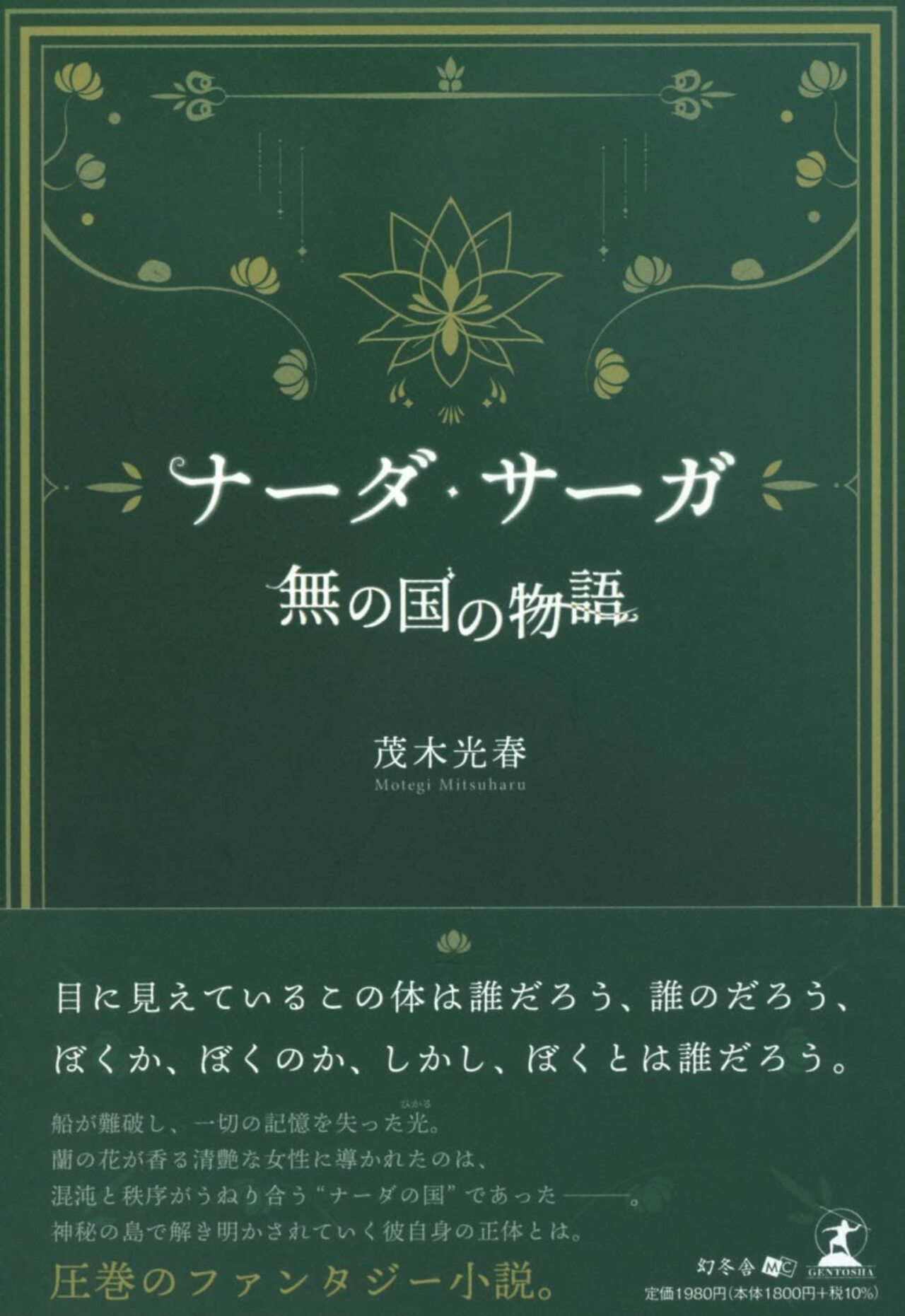それは分からない。しかしそんな釈迦が極めて親しく身近に感じられてならないことだ。
自分は今釈迦の道を歩いている、いや、そうじゃない、むしろ、釈迦が自分の道を歩いている、釈迦がぼくとなってその道を歩いているという気がしているほどなのだ。
牡丹園の遠くでセイレイ嬢がぼくの方を見て、手を振っている。半透明の薄物の白いサーリーのごとき衣を風に揺らせながら、婉然としなやかに手を振り、笑顔をほころばせているのである。
しかも何か不思議なことに、牡丹園の中には女性らしき姿が何人もいて、どれもセイレイ嬢に似ているということなのだ。そっくりであるばかりか、どの姿も実に美しく艶やかで、サーリーの中にすらりとした肉体をうごめかせ、どの顔にも輝くばかりの笑顔を湛えていることなのだ。
もしかしたらそこに実際に立っているのはセイレイ嬢だけであり、すうっと二人になり三人になり、複数に分かれ、分身して歩いているように見えているだけなのかもしれない。なぜだかそんな気がした。
「待たせてしまって申し訳ありません」
セイレイ嬢がふたたびこちらにやってきて言った。
「さあ、それでは次のところへ行きましょう。ランチの時間ですものね」
その顔はかすかに汗ばみ、濡れて光っている。顔から花の香りのごときものが漂って来るのが感じられた。
「あのう、いいですか」
ぼくは初めてぼくの中に一個の意志のごときもの、欲求のごときものが目覚めていることに気が付いた。
「何でしょうか」