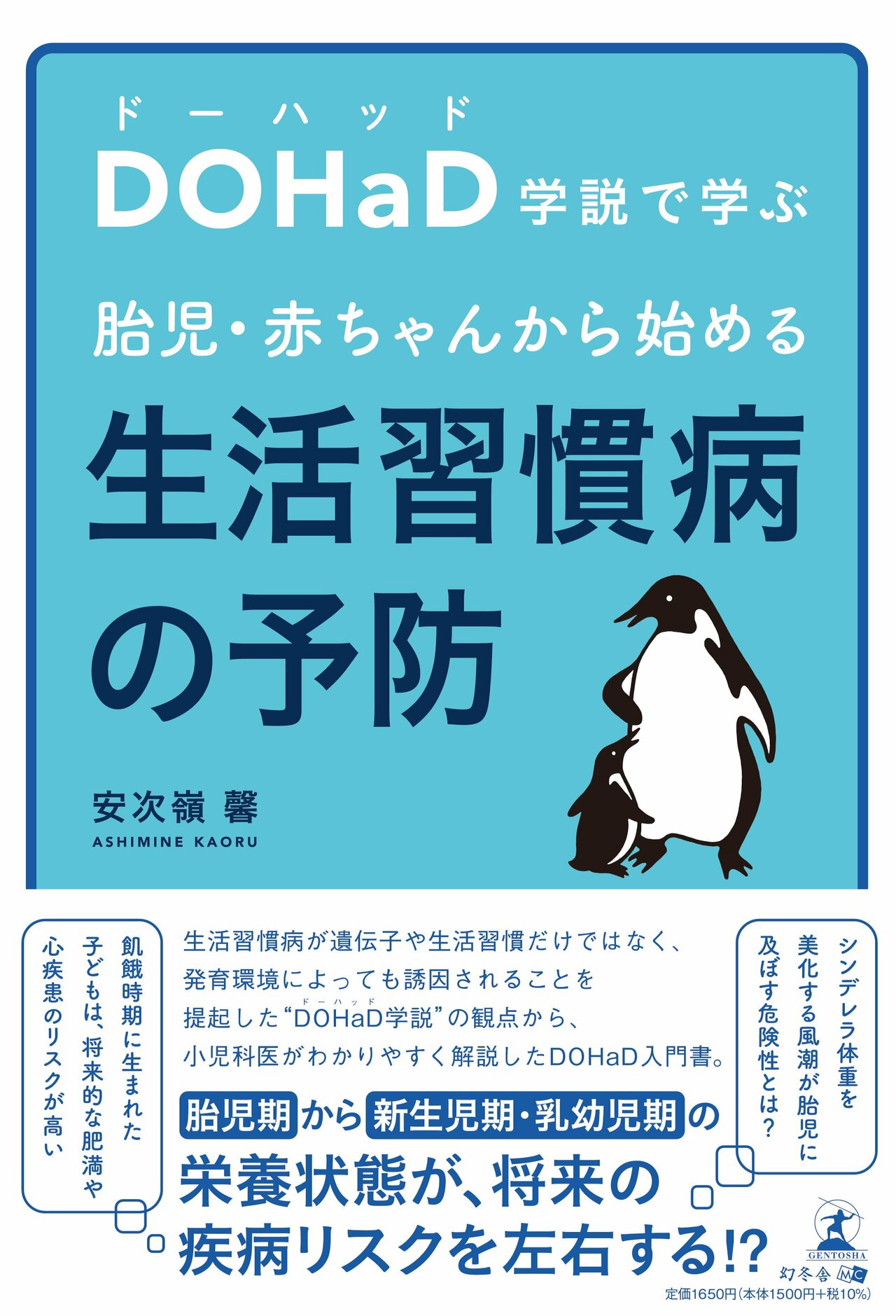3│鵜木元香・佐々木裕之/もっとよくわかる!エピジェネティクス
(2020羊土社、p12–17 )3
17世紀ごろまでは、精子の中に子どもがいて、それが子宮の中で大きくなるというプレフォーメーション(前成説)が広く信じられていた。18世紀になり、受精卵から発生が進んでいく過程で、次第に生物の体が作られていくというepigenesis( 後成説:epi=後、 genesis=創造)の正しさが広く認識された。
1942年、英国の発生学者コンラッド・H・ウォディントン(Conrad Hal Waddington)博士は、エピジェネシスの機構を探求する学問として「エピジェネティクス」という言葉を造語した。
博士は、エピジェネティクスの概念を山頂から谷間へ転げ落ちる球体になぞらえて表現した。山頂が最も未分化な状態で、細胞は分岐した谷間へ転げ落ちるように、一方向性に分化して、元に戻れなくなるという概念である。
4│井村裕夫/医と人間
(岩波新書、2015、p104)4
従来、後天的に獲得したものは遺伝しないと言われていたのですが、一部は次の世代から3代くらいまで遺伝するのではないかと考えられています。それは、エピジェネティクス(epigenetics)という考え方に基づくものです。
人間は、2万ちょっとの遺伝子を持っています。ところが、全ての細胞でそれが全部働いているのではなく、一つ一つの細胞では発現を調節して、5,000~6,000個くらいしか働いていないのです。だから、初めの胚細胞から皮膚の細胞ができたり、神経の細胞ができたりするわけです。それを、エピジェネティックな変化といい、ある遺伝子の発現を抑えている状態です。
そうやって、それぞれの細胞の特色を作っています。それが胎生期に決まるのです。だから、胎生期の栄養が悪いとそこに変化が出ると考えられています。