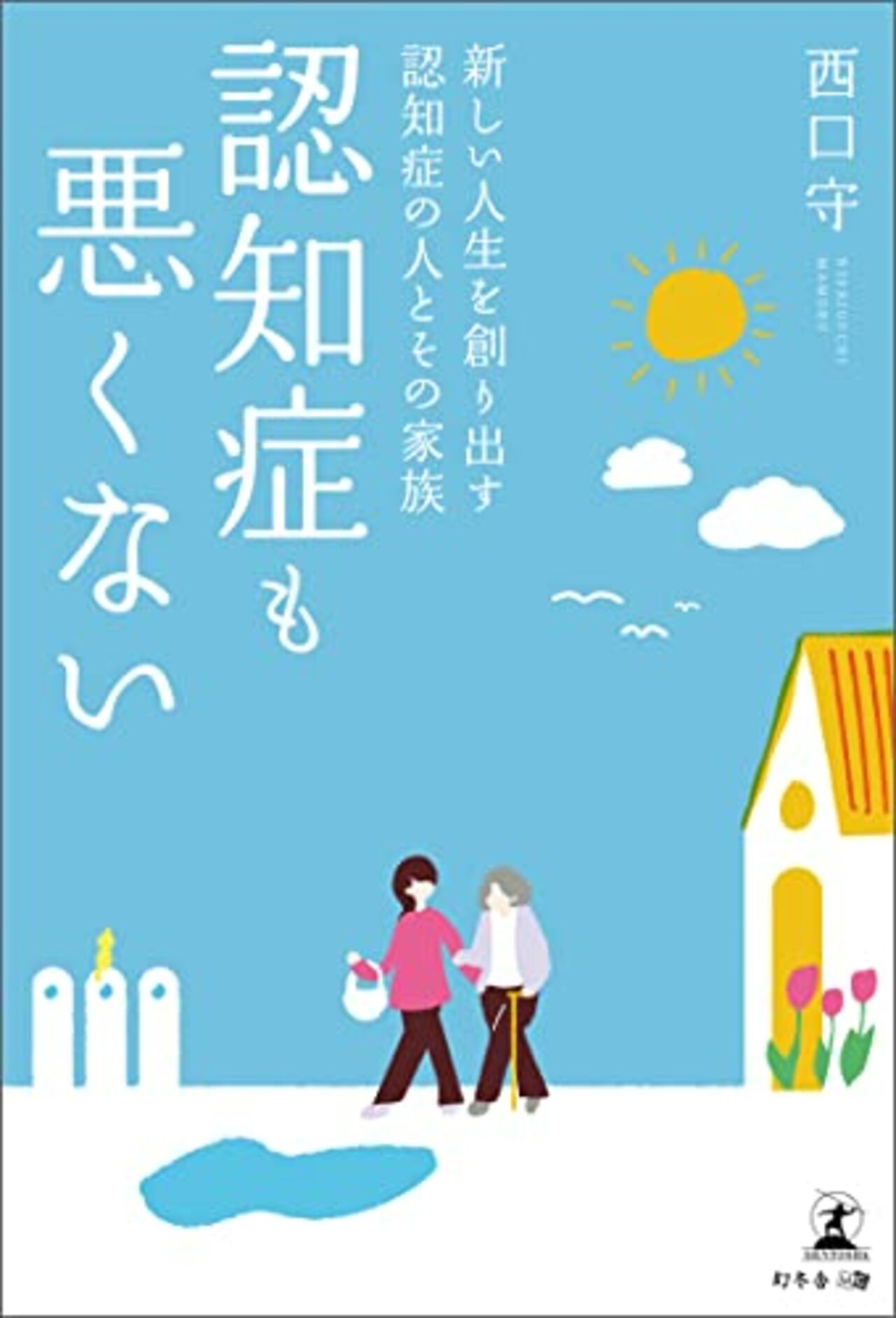あんなに嫌がっていたデイサービス。嬉々として通い、ショートでは大脱走を試みる。ガッツあるな?
デイサービスは母にとってはあまりいい思い出がないかもしれません。そうです、「こどもじみた」場所という感情は根っこにはあったのではないかと思います。
同居を始めてから、デイサービスはどうだったか? なんと「楽しい」と言って嬉々として通所しているではないですか。今度のデイサービスが「子どもじみて」いないかどうかは、なかなか難しいと思いますが、幼児教育に使うような塗り絵に象徴されるプログラムからどのように考えるか?
私は「子供じみている」ことのすべてを否定するつもりはありませんが、なぜ高齢者が「こどもじみている」と感じるのか、それがどのような意味を持っているのかは、サービスの質を考える視点では大切ではとも思います。
私も大学に身を置く者なので他人事のようなことを言うのも失礼かと思いますが、大学で高邁な理論を教えるのと同様に、研究者は、高齢者のこうした生活の足元の問題にもっと切り込んでいく必要を感じます。
今の大学には現場に立ち入り、現場から学ぶ、また現場へのリスペクトという視点や思想が決定的に欠如していると感じるのは、「勉強不足」の私の戯言でしょうか。1 私を横切った(遠藤周作)人との一回きりのの出来事に感情移入する力が決定的に枯渇しているように思えてなりません。
私は大学の授業が無機質で理想もなくそして現実も知らないものが支配する教室を離れて「現場」から発信するフィールドワーク主体2 の形に早くなって欲しいと思っています。そうでなければ日本における大学の存在意義は見いだせなくなるように感じています。