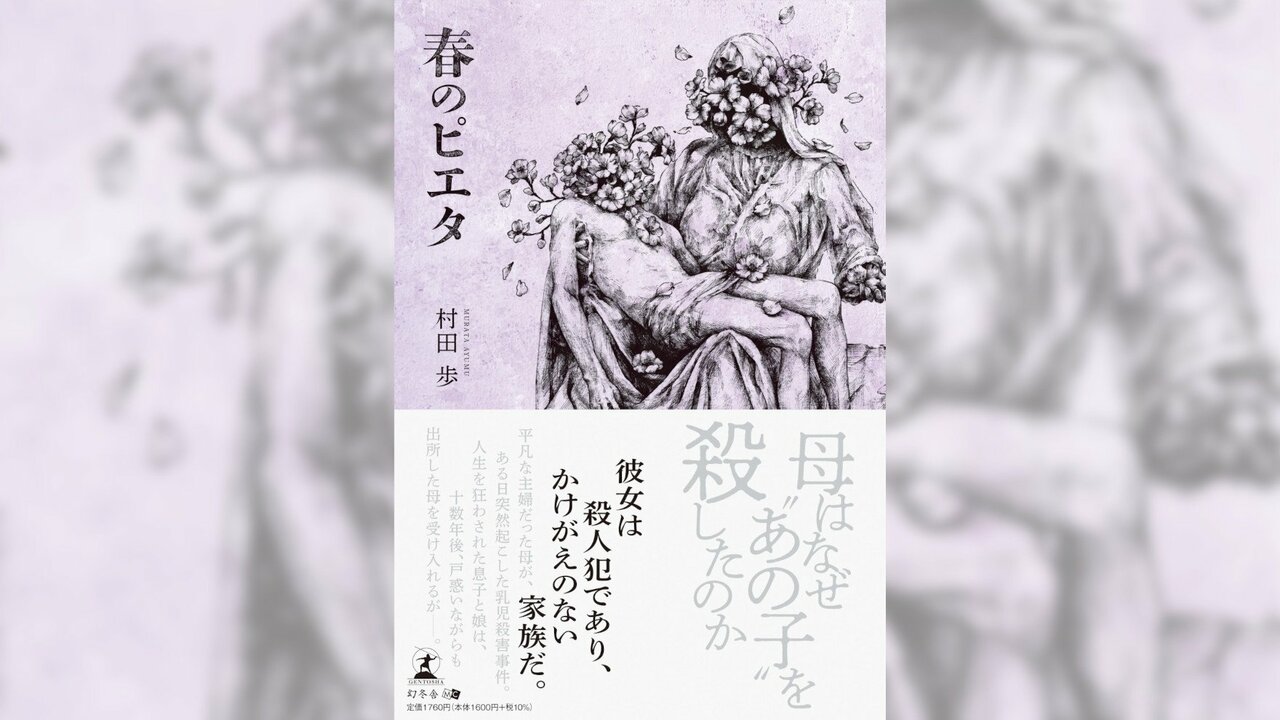劉生 ―秋―
「……」
「ねえ、良知先生。妹さんは妹さんなりに、お母様のことと真剣に向き合っていたんじゃないかしら。自分で納得できる答えが欲しかったんでしょう、きっと。その答えが得られたかどうかはわからないけれど、戻ってきたお母様を、覚悟を持って受け入れたのはたしかだわ」。
俺がベッドから立ち上がると、先生は話すのを止めた。きっと俺が気分を害したと思ったのだろう。
カーテンの隙間から表通りへと続く薄暗い私道を見る。誰もいない。
先生が見たという女は、本当に婚家の差し向けた人間なのだろうか? だとしたら、いったいなにを探ろうとしているのか? 先生の暮らしぶり? 子供が毎週末やってくるのだから、おおよそのことは想像がつくはずだ。それとも男? 先生の男ならここにいる。
「俺がどんなときに自由を感じるか、わかる?」松嶋先生は黙っている。
「俺はその気になれば悪いこともできる。思いっきり残忍にもなれる。そういう確信を持っている。こうしようと思えばなんの躊躇いもなくできるなって考えながら、あえてそれをしない。というか、気まぐれにそれをしない。そういうとき、俺はとてつもなく自由だと感じるんだ」
電信柱の陰から黒い人影が枝分かれした。女だ。